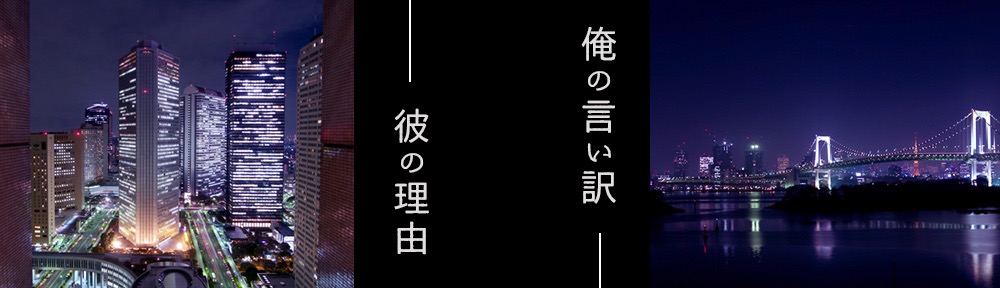俺の言い訳彼の理由4
思わず小さく声があがってしまう。壁に寄りかかるような格好でぐったりしている男をよく見てみると、グレーのスーツの足の間から血が染みて色を変えてい た。視線を上げれば、釦が引き千切られたYシャツの隙間から覗く男の胸には陵辱されたような跡が赤く残っているのも確認出来る。
鞄を握ったまま気を失っているのか、玖珂が側に来たことにも男は気付いていないようだ。
玖珂の足下には点々と付いた血痕と取れたボタンが何個か散らばっており、目の前の男に何が起きたのかが生々しく想像できる。足元には、この男の物であろう眼鏡が透明なガラスを砕けさせて散っていた。
──誰がこんな酷い事を………。
玖珂は屈んでレンズが外れフレームだけになった眼鏡をそっと拾い上げる。そして座り込んでいる男の顔を覗き込んでみた。歳は弟と同じくらいかそれより少し上なのかはわからなかったが、もともと色白なのだろう肌が血の気を失って紙のように蒼白になっていた。
玖珂は男の頬に涙のあとがあるのに気づき親指でそっと辿ってみる。触れた肌はとてもなめらかで、そして氷のように冷たかったのに戦慄を覚える。
「おい、君、大丈夫か?」
玖珂は驚かせないように声を少し落として肩に触れてみる。外気はこんなに暑いのにここまで冷え切っているという事は数時間はこのまま放置されていたと考えていいだろう。
冷たい肩の下には自身できつく握っていた為についたのだろう指跡が残っていた。もう一度声をかけたみたがやはり意識は戻らなかった。
暫くどうしたものかと玖珂は考えていたが、このままにしておくわけにはいかないと思った。こんな場所でこれからくる夜の時間を過ごしていては危険なのは目に見えていた。
それに、自分がこうして彼を見つけたのが偶然ではない気がしてならなかったのだ。少しの迷いを振り切ると、玖珂は男を自宅マンションへと連れて帰ることにした。
店舗の場所を確認するのは後日に回す事に決め、胸元のポケットから携帯を取り出す。
まさか電車に乗って帰るわけにも行かないのでTAXIを呼ぶことに決めた。自分が車で来なかった事を後悔しながらTAXI会社の番号を呼び出す。ざっと辺りを見渡すと丁度電信柱に住所が書いてあったのでその住所を告げ携帯を閉じた。
丁度近くを流していたのか、電話を入れてから5分ほどでTAXIが到着した。さすがにTAXIも路地までは入ってこれないので出口で待っていてもらう様 に告げ、玖珂は再び男の所まで戻ると周りにある男の鞄。そして、さきほど拾い上げた眼鏡をズボンのポケットに入れて、ぐったりしている男を抱き起こした。
思い立って自分の着ていたスーツの上着を脱ぐと男の胸を隠してやるようにかけてやる。抱き上げてTAXIに乗り込む際、一応怪しまれないように運転手に「連れが泥酔している」事を告げる。
都会のTAXIはあまり詮索をしてこないとはいえ、明らかに様子がおかしいとなれば話は別なのかもしれない。
運転手は発車したあとも時々フロントミラー越しに好奇の目線をちらちらと向けてきた。
しかし、結局は玖珂のマンションまで運転手は一言も口を開かなかった。
釣りはいらないと多めの札を運転手に残し、玖珂は男を再び抱き上げてどうにか自宅へと辿り着く事が出来たのだった。
さすがに女ではないので抱き上げて運ぶには重い。それに意識がないので、その重さがよりいっそう増していた。オートロックの暗証番号を素早く押し、開いた自動ドアから足早に中へと身を滑らせる。
あまり人に見られていい状況とは言えなかったからだ。運良く一階へと止まっていたエレベーターに乗り込むと、玖珂は詰めていた息を吐いた。回数表示を見上げながら、腕の中の男に視線を向ける。男は未だに目を覚ますことはなかった。
漸くたどり着いた玄関のドアを開け中に入るとドアに背中を預ける。安堵し力を抜いた瞬間、抱いている腕の中で身体が少し動いたのに気付いた。意識が戻った事に少し安心し胸をなで下ろす。
男は目を何度か瞬き何処か痛むのか顔を顰めたが、意識は完全に戻ったようだ。自分の置かれている状況を把握した男は視界に玖珂が映ると怯えたような表情をした。とりあえず説明をする前に男を玄関の中にそっと降ろし座らせ距離を取る。
「だ……誰……何する、つもり………」
玖珂を目の前に男は強張った表情で見返し、掠れた声で呟いた。ただ怯えていると言うよりその瞳には敵意がこもっているのが感じ取れる。あんな酷い事をされたのだから見知らぬ男に敵意をむき出しにするのは仕方がない。
玖珂は怖がらせないように自分も同じように座って目線を合わせると、身体には触れないようにして話しかけた。
「安心していい。たまたま君が倒れていた所を通りかかった。それだけだから。俺は、何もしないよ。約束する」
男は疑いの眼差しをあからさまに向けていたが、少しして自分の胸を隠すように玖珂の上着が掛かっているのを見ると小さく頷いた。自分を襲った男とは関係がない事を確信したのか、その後、張りつめていた空気を少し解いた。
目を覚ました男の瞳のまっすぐな視線に玖珂は惹きこまれ、言葉を返すのを忘れていた。同性であったとしても純粋に綺麗だと思える透明さがそこには存在している。意志の強そうな黒目がちの瞳は肌の白さと対照的で鮮明なコントラストを映していた。
「………………ここは?」
男が周りを見渡し口を開いたことで玖珂も我に返る。
「俺のマンションだ。意識がなかったからな……ここまでTAXIで運んで貰ったんだ。それより、身体はどうだ?何処か痛くないか?もしあれだったら病院に……」
「…………それは……」
男はそれは出来ないとでも言うように首を振り、先程自分がされた行為を思いだしたのか俯いて胸元を隠すようにかきあわせた。さっきは気付かなかったが男 の手の甲にも抗った時についた傷が血を滲ませていた。何故こんな事に巻き込まれたのか。真面目そうな会社員に見える目の前の男に聞きたいことは山ほどあっ たが、今は聞いてはいけない気がして玖珂はその言葉を飲み込む。
「傷を洗った方がいいな。取りあえず中へ入ったらどうだ?」
男は黙って首を振る。
「………そこまで、見ず知らずのあなたに迷惑をかけるわけにはいかない………」
玖珂の申し出を断り、目の前で立ち上がると一瞬痛みに膝を折りそうになったが、それでも壁に手をつき身体を支えると玄関のドアノブに手を掛ける。
男は、玄関のドアを開ける前に一度振り向いた。視線は以前下を向いたまま…。
「汚れた上着はクリーニングに出してお返しします。色々と……迷惑を掛けて申し訳ない」
「………君、ちょっと待って」
玖珂が思わず男に手を伸ばす。出て行こうとする腕を掴むと、男の身体がビクリとなったのがわかった。振り払われはしなかった物の、毅然と見えた態度とは裏腹に押し殺すように小刻みに震え続けているのが伝わる。
──怖いのだ。
玖珂は咄嗟に思った。
いくら玖珂が男を襲った男と関係ないというのがわかったとしても、相手が男だと言うだけで身体が恐怖で竦んでしまうのかも知れない。外気が生ぬるく暑いというだけではないように男の額には玉のような汗が浮かんでいた。
身体の傷は勿論だが精神的なショックの方が大きいのかも知れない。一体誰が…。こんなに傷つくまで追い詰めたのか、理由もわからないままに玖珂は相手の人間に静かな怒りを感じざるを得なかった。
依然俯いたまま震えるスーツ姿の男からそっと腕を離す。力なく落下していく男の腕が宙を切り、男の足元にはポタポタと滴が落ちた。長い前髪で隠されているその瞳から零れているだろう事は容易に想像がつき、玖珂は下唇を噛んだ。
最初に男を連れてきた時には、そこまで深く思い入れていたわけではなかった。あの場所に放って置けなかったから連れてきた。それ以上は考えていなかったはずだ。それなのに……。
玖珂はもう一度そっと男に腕を伸ばし、マンションのキーを男の掌に乗せた。
『え?』という風に見返す男に玖珂は優しく頷いてみせる。
「俺は明け方まで戻らないから、俺が出ていったら鍵を閉めればいい。そうすればもう誰も入ってこない。そんな身体じゃ、家まで戻れないだろう」
男は大丈夫だと言おうと思い顔を僅かにあげたが、その瞬間まだ体内に残っていた見知らぬ男の精液が再びトロリと足を伝わったのを感じて、思わず足に力が入らなくなり玄関にしゃがみこんだ。
玖珂の腕が咄嗟に倒れ込みそうになる身体を支える。
「おっと、大丈夫か?」
「……っ、すみません」
「無理をするな。シャワーを浴びるだけでも気分がスッキリするから」
だいぶ迷っていたようだが男は玖珂の好意を受け取ることにしたらしく、後ろ手で今出ていこうとしたドアを閉めた。玖珂は優しく微笑むと一度部屋へ戻り、男にあがってくるように促す。
男は黙ったまま靴を脱ぎ、廊下を進んだ所で立ち止まった。目の前で着替えとバスルームなどの場所を説明している玖珂の姿を追いながら、自分の置かれている状況に理解がついてこないのか頭を何度か振った。
「少し休んでいくといい。ここをでる時は鍵を一階のポストに入れておいてくれ」
「………何で、そんなに俺を信じられる……。名前だって名乗ってないのに……」
「ん?」
「俺がもし……物取りだったらどうするつもりなんだ……」
掠れた小声でそう呟く男は、自身の滲んだ涙をスーツの袖で乱暴に拭うと真っ直ぐに玖珂に視線を向けてきた。この世の全てを信じていないとでもいいたそう なその視線に玖珂の胸がドクンとなる。男の言う事は正論で、何も間違っていない。だけど、酷く寂しい考え方だと玖珂は思った。同時に抱いた感情が、同情と いう言葉だけでは済まされない事にも気付く。
玖珂は真っ直ぐに自分をみつめる男に歩み寄り、静かに言葉を告げる。
「そうだな……しかし、世の中には偶然なんてないと俺は思っている。だとしたら、きっとこうやって君と出会ったのも何かの縁かもしれない。君が物取りだったとしてもそれはそれでしょうがないんじゃないのか?……俺に見る目がなかったというだけだ」
「………そんな」
「名前は君が教えたければいつでも聞くが、無理にきくつもりはない」
玖珂はそう言うとゆっくり靴を履き部屋をあとにした。男はその背中に返す言葉もみつけられず、ただ玄関が音を立てて閉まるのを呆然と見ているしか無かった。
* * *
どれくらいそうして立っていたのかわからないが、残された渋谷は下唇を噛んだ。自分のとった行動を思い返し、今更恥じる。こんな見知らぬ自分を信じてくれ、気を遣い、自宅だというのに渋谷に好きにしていいと鍵まで渡していった。
なのに自分はどうだ。
ろくに礼も言わずに挙げ句には恩を疑ってあんな事を言ったりして‥‥‥。
──偶然ではない………か
一晩で対極の人間と出会った事で渋谷は動揺していた。他人にこんなに侮辱を受けた事もなかったし、彼のように見返りのない優しさをかけてもらった事もない。
渋谷は改めて一人になって部屋を見渡す。
綺麗に整頓されたリビングには、ゆったりとしたソファが置かれ、デザイン性の高いローテーブルが添えられている。間接照明のみの室内照明は落ち着いた雰囲気で、壁一面の窓から一望できる夜景までもが絵画のように馴染んでいた。
普通のサラリーマンにしては相当豪華な部屋だ。
──どんな仕事をしているのだろうか?
渋谷はふとそう考えて頭を振った。詮索等するのはよそうと、もう関わることはないのだから
互いの事を知る必要もない。
とりあえず渋谷はシャワーを借りる事にして風呂場へ向かう。嫌な汗をかいたせいでまとわりつく衣服を肌から一度放したかった。彼が出してくれた新しい下着の着替えの横にバスローブが用意されている。
使った物はあとで全て買って返す事にしようと思っていたため、ブランドなどを少し調べ頭にインプットする。リゾートホテル並のバスルームに足を入れるとバスタブの横の大きめの鏡に自分の姿が映った。
ところどころ赤く鬱血したあとを残している。足に流れた血はすでに固まって無惨な筋になっていた。渋谷は目を閉じるとフラッシュバックしてきそうになる先程の場面に、バスルームで軽い目眩を感じて座り込んだ。ずっと立っている事すら苦痛である。
ぬるめのシャワーで身体を流し皮膚が擦りむけそうなほどゴシゴシ洗った。
水が流れるだけで激しく刺すような痛みが沸く後孔も出来る限り丁寧に洗う。
何度洗っても汚れがとれないような気がして渋谷は夢中で流した。
「………くそっ………」
明日が土曜で会社が休みだった事だけが不幸中の幸いだった。誰とも顔を合わせたくなかった
誰もこの事を知らないはずなのに社内で皆が自分を見て眉を顰める場面を想像してしまう。
──男に犯されたんだって 可哀想じゃない?
女子社員の好奇心を含んだ同情の言葉がリアルに再現される。上司の冷ややかな視線。部下の汚れ物をみるような視線。
何故こんな事になったのか、頭からシャワーを浴びながら渋谷は冷静になった頭で様々な可能性を思い浮かべる。フと渋谷の脳裏に藍子の顔が浮かんだ。
こんな事になって待ち合わせをすっぽかした形になってしまったのだから連絡を入れなくてはいけないのではないかと考える。
そこまで考えてさきほどの男が言っていた言葉が思い出される。
確か、依頼がどうとか言っていたのではなかったか?という事は誰かの故意で………?一体誰が?
どんどんわき上がる疑問に答えはすぐに見つからない。しかし、その先を考えるには今は疲れすぎていた。
渋谷は最後に冷水を頭からかけるとバスルームを出た。
下着だけを用意されたものに着替えるとまた汚れたスーツを身に纏う。朝まで戻ってこないような事を彼は言っていたが、シャワーを借りたらそれで帰る事に決めていた。
まだ痛みが激しいが、これは待っていて治るようなものではない事はわかっている。
取りあえずゆっくりと歩けばどうにか通りのTAXIを拾って帰ることくらいは出来そうだった。
部屋に置かれている時計を見ると、11時半を過ぎた頃であった。
しばらく迷ったが渋谷は自分の名刺をやはり置いていく事にし、鞄から取り出す。電話の横にあったメモ帳に礼の言葉と一緒にTAXI代と並べて置いておいた。
そして、身の回りの物を持つと部屋を出た。借りた鍵できちんと施錠し、ドアノブを回して確認する。表札に玖珂と書かれているのを見つけ、彼の名前を知る。この階は二棟しかないらしく隣のドアはやけに遠い。
眼鏡をなくしているため視界がぼんやりとしか見えない。新宿の夜景が滲んで見える。
エレベーターの前まで辿り着いてここが最上階の三十階である事を初めて知った。
──ここは何処なんだ
具体的な住所もわからない。渋谷はエレベーターの重力に身を任せ背を預けると一階につくまでのしばらくの間、目を閉じた。
* * *
その頃 玖珂は行きつけのバーで時間を潰していた。自宅マンションから歩いて20分と少しの場所にある。明け方帰ると言ったので、4時頃まではどこかに いる必要があった。一度自分の店に顔を出そうかとも思ったが、何となく一人でいたいような気もしてそれは今晩はやめておく。
こうして馴染みの店で酒を飲んでいる方がじっくり考える時間も取れそうだと考えたからである。マスターとはもうそれこそ玖珂が10代の頃からの知り合いで、色々な相談にも乗り合う仲だったので気心は知れている。
来た時には他に客もいて一人で呑んでいたのだが、1時を回った頃には客は偶然にも玖珂だけになっていた。趣味でやっているからいいのだとマスターは早々と店を閉め、今は玖珂の前のカウンターで自分も一杯やっている。
お互い何本目かの煙草に火をつけた所でマスターが静かに口を開く。
「亮、何かあったのか?急に朝までいさせろって」
肩をすくめグラスを傾けると視線を玖珂へと向ける。
「あったといえば……あったかな」
「随分意味深な言い種じゃないか。朝までいるのに女の所じゃなくてうちにきたんだ。何か話があるのかと思ったぞ?」
目の前の一杯になった灰皿をマスターが蓋をして交換しながら話しかける。ボトルキープしてあるウィスキーのボトルはすでに3分の1ほどしか残っていない。玖珂は自分でダブルの水割りを作ると透明な氷を指で回した。
琥珀色の満たされた中にカランと音を立てて氷が沈み波紋が伝わっては消えていく。
グラスを片手で口へと持っていくと一口喉を潤した
流してある髪を梳けば玖珂の付けているJ.Sの香りが微かに辺りに漂った。
玖珂は少し困ったような笑みを浮かべる。
「ちょっと拾い物をしたんだよ」
「拾い物?」
「あぁ」
「何処で?」
「今日、例の店の件で新宿に行ってたんだが、そこで」
マスターが自分のグラスにも酒を注ぎ新しい煙草を一本くわえる。玖珂が差しだしたマッチで火を受け取るとうまそうに煙を吐き出した。
こうしてマスターと個人的に話をするような人間はそうそういないらしい。客の愚痴はきいても余計な事までは詮索しない。こういう場所でのそれは一見の客や、詮索を嫌う客が多いせいだ。
玖珂が特別な相手なのは、接する態度を見ていてもわかる。
「どうして拾ってきたのか自分でも不思議なくらいだ」
「ほう。そんな綺麗なモノだったのか?」
「あぁ、そうだな。傷だらけなのに綺麗だった。多分俺が今まで見てきた中で一番かもな」
そう言って玖珂は男を思いだしていた。もう帰ってしまっただろうか。それともまだ休んでいるのか。想像して、煙草に火をつけた。
──………何で…そんなに俺を信じられる
──名前だって言ってないのに
先程の言葉がリプレイする。
そうだ、名前も何も知らないのに‥‥‥。
玖珂はそう考えて自分のポケットの中に眼鏡のフレームが入っているのに気付いた。レンズが砕けてなくなったそれは、渡そうと思って忘れてしまった物だった。
「マスター」
「んー?」
「割れた硝子は……治すことが出来るのか、どう思う?」
「直せなかったら新しく作ればいいんじゃないか?そうだな。今度はもう割れないようなやつをな」
「………なるほど……そうだな」
時計の針がやっと2時を廻った頃、ほんの少しまわった酒の余韻を楽しむように玖珂は最後の煙草に火を灯した。