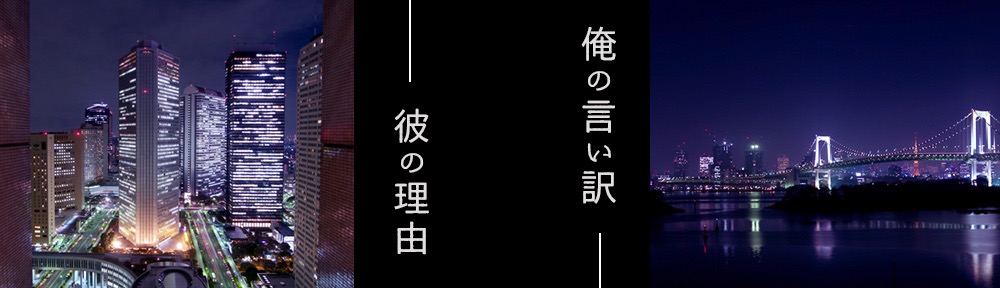俺の言い訳彼の理由13
玖珂が帰ってしまった後は何もする気になれず、渋谷は、いつもはあまり付けないテレビを見るともなしに眺めていた。外が暗くなる頃に一度だけ夕飯を買い に近くのコンビニへ行ったが、特に食べたい物も無く、材料を買ったとしても作る気力もなかったので、結局ビールだけを買って帰ってきた。
風呂上がりなどに一人で飲む事はたまにはあるが、こうして早い時間から酒を飲むのは珍しい。家にあったスナック菓子をあけ、それを食べながら買ってきた ビールを飲む。それが終わると以前にもらった日本酒をあけて飲んだ。慣れない日本酒は何処かの名産品らしいが美味しいのかどうなのかさえわからない。
つけっぱなしにしているテレビは幾つかの番組を終え、次々と新しい番組に切り替わっている。見た事も無い歌手が、入れ替わり立ち替わり歌を披露しているが、どれも同じような曲に聴こえる。渋谷はリモコンを向けると、テレビの電源を落とした。
部屋からは一切の音が遮断され、時々唸るように聞こえる冷蔵庫のモーター音だけが響く。やはりアルコールは一種の麻薬だと渋谷は思う。あんなに滅入って いた気分もいつしか少しずつ遠のき、まるで普段と変わらないように麻痺してくる。時間が経って酔いが覚める頃には忘れていた事実が余計に重くなってのしか かってくるのは理解していたが、ただただ眠気が襲ってくる体をそのままソファへと倒し時が過ぎるのを待った。「俺は平気です」玖珂に無理して告げたその台 詞に自嘲的な笑みが落ちる。
「しっかりしろよ……俺……」小さく声に出して呟き、渋谷はそのまま浅い眠りへ落ちた。
渋谷が目を覚ましたのは明け方になってからであった。まだ起きるには早い時間だったのでそのまままた目を閉じる。朝になり、目覚ましの電子音が鳴って、 漸く渋谷は身体を起こした。スッキリとした目覚めとはほど遠い体調なのは昨夜柄にもなく酒を飲み過ぎたせいだろう。今日からまた一週間が始まる。
少し痛む頭に眉を顰めながら、浴室へと向かった。気持ちを切り替えるために熱めのシャワーを浴び着替えを済ませる。人間とは不思議な物で日の昇る朝にな れば夜よりかは幾分前向きになれる。マンションを出て駅へ向かう頃には仕事の事だけを考えるようにした。毎日揺られる満員電車の中で人波に身を任せ、「い つもと同じだから」と何処かで言い聞かせる。
一日は始まったばかりで先は長い。
相変わらず仕事が忙しいのも今日ばかりは考え事をしなくて済むので有難いと心から思っていた。何かに集中していれば時間は結構早く過ぎるし、他の事に気持ちを引きづられる事もない。渋谷が最後の顧客を回り帰社した頃には夜の8時を過ぎていた。
日報を書き、デスクワークを終えて時計を見る。
時刻9時30分
案外早くに終えてしまった仕事に溜息しかでない。とてもまっすぐ帰る気になれない今、他にしておく事がなかったか考えを巡らせる。その後、納期にはまだ 余裕がある見積もりや報告書にも手を付けたが、それも片づいてしまい、ほとんどの社員が帰った閑散としたフロアを見渡して、渋谷は一人肩を落とした。
情けない自分をあざ笑うかのように時間はゆっくりとしか過ぎてくれない。巡回の警備員が「お疲れ様です」と言葉をかけてきて、漸く渋谷はもう時計が10 時半を回っていることに気付いた。さすがにそろそろ帰った方がいいだろう。そう思い、警備員に「遅くまでお疲れ様です」と挨拶をし、会社を出る。
ビルから一歩出れば蒸し暑い空気が途端に体にまとわりつく。不快なそれを払うように足早に駅へと向かうと終電より何本か前の電車に乗り込んだ。
デート帰りなのだろうか、幸せそうに手を繋ぐ恋人達を横目でチラリと見ながらつり革につかまる。外が暗いせいで窓にはくっきりと自分の姿が映っている。渋谷は映る自分の姿を見ないように目を伏せた。
ただ一ヶ月前に戻っただけ。
それだけだった。
失ったとはっきり言えるほど、確実に玖珂を手に入れていたわけではない。玖珂へきちんと自分の言葉で返事をしたわけでもないのだから、失恋と呼べる場所までも辿り着いていない。だから、何も失って等いないのだ。
自宅最寄りの駅へと電車がすべりこむと、吐き出される人混みに混じって改札を出る。それぞれが自宅への方向へ散っていく中、渋谷は駅向こうの繁華街へと足を向けた。このまま自宅に帰って過ごすには時間があまりに長すぎる。
少し路地を曲がればあまり環境がよくないとされる昔からの飲み屋街になるのは知っていたが、足を運ぶのは初めてだった。結構な時間にも関わらず、その通 りは多くの店が営業中らしく、眩しいほどの電飾看板があちこちで点滅している。途中の自販機で煙草を買い、ゆっくりと通りを歩いていると、何軒かの店の前 で客引きに声を掛けられた。
「お兄さん、今日新入りの子が入ったからどう?」
軽い感じの男が、馴れ馴れしく渋谷の前へと回り込んで顔を覗き込む。渋谷は店の前で足をとめ上を見上げる。けばけばしいピンクの文字を見てキャバクラである事に気付き視線を客引きへと戻した。
「……遠慮しておくよ」
一言だけそういうと先へ進む。背後で客引きが舌打ちをしたのを背中できいて渋谷は2軒先のバーのドアを開けた。騒々しい飲み屋には行きたくなかったので、窓から見た感じ少し落ち着いて見えたこの店を選んだのだ。
案の定常連がカウンターに数人いる以外は客のいない店内を進む。「いらっしゃいませ」と声がかけられて壁際の一席へと案内された。とりあえずウィスキーの水割りを注文すると渋谷は席へと座り、さきほど買ってきた煙草を取り出した。
玖珂に以前もらって以来吸っていないが無性に吸いたくなったのだ。銘柄はなんでもよかったのだが、渋谷の指は自然にKOOLを選んでいた。ライターを持参していないのでマッチをもらい、運ばれてきたウィスキーを飲みながら煙草を吸う。
きついソレに肺が反応するように咳き込みそうになり、抑えるためにウィスキーを一気に煽る。
入口が開いて、また一人の客が入ってくる。薄暗い店内ではたがいの顔を見ることも無い。渋谷は、流れる静かな曲を聴きながら、ガラス越しに通りを眺めていた。
ウィスキーの甘い後味を味わいながら渋谷はもう一本煙草を取り出して火を点ける。真っ赤に灯った煙草の先が目の前で滲む。その味と共に思い出すのはやはり玖珂の事で……。
携帯を胸ポケットから取り出してアドレス帳を開いてみる。私用で使っているその携帯のアドレス帳には数えるほどしか登録されていない。【K】の所まで指をすべらせ、玖珂のページを開く。玖珂と交換したそのページには住所や名前、電話番号が記されていた。
『玖珂 亮』
そういえば、玖珂の名前は一度も口にしたことがないなとフと思う。「とおる」と読むのか「りょう」と読むのかそれさえもわからない。そんな事すら知らな いような関係だったのだと改めて思いながらも、名前の読み方等よりもっと大切な沢山の事を教えてくれた玖珂の文字を指でなぞる。「りょう」のほうが玖珂に 似合っているかな……。そんな気がして渋谷は小さく声に出してみた。
亮さん……。
昨夜充電をしていなかった携帯のバッテリーが赤くなっている。節電設定が働き暗くなった画面を渋谷は耳に押し当ててみた。繋がっていないはずなのに玖珂の声が聞こえてくる気がして……。
グラスに口を付け喉を潤し、目を閉じる。
渋谷君……渋谷君……。
自分を呼ぶ玖珂の声が脳に残っている記憶を揺さぶる。残りのウィスキーを飲み干すと渋谷はそっと目を開けた。ピーという電子音の後、力尽きたように携帯の充電が切れる。それを内ポケットへと入れると渋谷は立ち上がった。
* * *
その頃、玖珂は渋谷の携帯へと電話をかけていた。時間をおいたほうがいいと頭ではわかっているものの、昨日の別れ際に見た渋谷の表情がどうしても気に なって頭から離れなかった。渋谷相手に気の利いた言葉の一つもかける事が出来なかった不甲斐なさに嫌気がさす。かけようと思った言葉は口にすると、どれも が意味をなさない言い訳になるような気がして口を噤むしか無かった。
大丈夫ですと気丈に振る舞う渋谷は全く大丈夫なように見えず、玖珂はその言葉と裏腹な渋谷の様子に胸が締め付けられた。彼は今どうしているのか……。一番大切にしたいはずなのに、自分のせいで彼の笑顔を消してしまった事実が玖珂に重く突きつけられる。
玖珂は繋がらない携帯を握りしめていた。まだ仕事中なのだろうか、それとも電源を切っているのか。何度かけてみても渋谷には結局連絡がとれないままである。
腕時計を見ると、もう12時を過ぎている。仕方無く携帯を仕舞うと席へと戻る。玖珂は仕事の後、時々足を運ぶ馴染みのバーへと足を運んでいた。クローズが近い店内には玖珂ともう一人の客しかいない。
いつも自分が座る席に腰掛け、カウンターに頬杖をついて煙草に火を点けゆっくりと吐き出す。漂う紫煙が空気に溶け込んで消えていく様を目で追いながら、思うのは渋谷の事ばかりだった。
渋谷を最初に街で助けた日にもここにきて酒を飲んでいた。あの頃はまだ互いに名前すら知らなかったのだ。そんな事を思い出しながら、それからまだそんな に時間がたっていない事をぼんやりと考える。自分なりに彼との距離を縮めていったつもりでいたが、今夜はその距離が出会った日まで戻ってしまったようにも 感じ、その遠さに今日何度目かの溜息をついた。自分の気持ちが変わった訳ではない。寧ろ愛しさが増すばかりだというのに、彼を不安にさせているのもまた自 分なのだ。
グラスを磨くキュッキュッという音が耳に届き、暫くして目の前にカクテル差し出される。
「……ん?」
「俺からのサービスだ」
「……オールド・パル?……頂くよ」
古い友人を意味するオールド・パルは、「話しなら聞くぞ」というマスターからの合図なのだろう。玖珂は赤く光るカクテルグラスを受け取り、口にする。微 かな甘さと苦みのある味が優しく口に残る。甘いのをあまり好まない玖珂に合わせてステアしてあるそれを飲みながらもう一本煙草を取り出す。
「有難うございました」
マスターが最後の客を見送る声で店に二人きりになった事に気付き、カウンターへと戻って来たマスターに声を掛ける。
「もう今日はおしまい?」
「一応な」
「じゃぁ、俺もそろそろ帰るとするかな……」
「何だ、俺の酒には付き合ってくれないのか?」
マスターがそう言ったのを聞いて玖珂は苦笑する。プライベートで酒の付き合いをするのに断る理由は何もない。自分のグラスに酒を注ぐと、マスターは玖珂 のグラスの前でそれを少し掲げた。「何に乾杯?」そう言って笑う玖珂に「理由のない夜に、それでいいだろ?」そう言って笑った。
相談に乗る事はあるが、自分の話し、ましてや恋の話しを出来る相手はそうそういない。先程のカクテルの礼を言い、話しを聞いてくれるのか?と聞いた玖珂にマスターは勿論と答えた。
「この前来たときに話してた美しい拾い物の先を知りたいね」
具体的に渋谷の事を話したわけではないのに、完全に見透かされているらしい。あえて「拾い物」という言葉で聞いてくるマスターは深く探りをいれてくるといった事はなく、玖珂の言葉を静かに待ちながら自らも隣へ腰掛けた。
「順調……とは言えない状態だな」
「そうなのか?」
「あぁ、相手の前だとうまい言葉がみつからなくてね。……傷つける結果になってしまった事を反省している……」
「……ほう」
マスターはそれ以上は何も聞いてはこなかった。
「No1ホストでも落とせない相手がいるなんてな……」
「よしてくれ、今はもうホストじゃないし……それに……」
「……それに?」
「いや、何でもない……難しいもんだな。色々と……」
「本当に、口ベタだな。元ホストの名が泣くぞ」
「元、ね。今はただの普通の男だから。……自分でも、もう少し上手に立ち回れると思っていたんだが……このざまだ」
「普通の男なら、仕方無いな」
「…………そうかな」
「そりゃぁ、反省するような事も起きるし、相手を傷つけることも、自分が傷つくこともある。だって普通の男なんだからな」
薄く笑う玖珂にマスターが酒をつぎ足す。話術で売っているホストを長年やっていたのに口ベタなど笑い話もいい所だと自分でも思っている。しかし、マス ターの言葉に少し救われた気がした。何でもうまくいく事ばかりじゃないのが恋なのだ。それが普通のことなんだと改めて思う。真剣に相手を想ってとった行動 に正解も間違いも無いのかもしれない。玖珂は注がれた酒を飲み干すとカウンターをたった。こういう気分の時に煽る酒はいくら飲んでも決して酔えない。
「明日は朝から用事があるんだ……。今日はもう帰るよ。ご馳走様」
「あぁ、お疲れさん」
スーツの上着を羽織った所で呼び止めるように声がかかる。
「……亮」
振り向いた先に見守るような眼差しを向けたマスターが玖珂を見ていた。
「怖がる必要なんてないんじゃないか。お前の思う通りにやってみてダメだったらまたその時に考えればいい」
「……そうかもな。有難う」
玖珂は笑って片手を上げる。マスターが玖珂の飲んでいたグラスを片づけるのをみて店を後にした。揺れるドアが閉まる時、CLOSEDの看板が風で音を鳴らす。
「怖がる必要は無い……か」何処かで聞いたような台詞をよくよく考えて玖珂は昔を思い出し苦笑した。その台詞は昔、マスターに自分が言った台詞なのだ。
今の奥さんを口説くのにマスターが玖珂に相談をしてきた事があった。当時で40を過ぎていたため、一回り下の彼女に告白する勇気がないと言っていたマス ターの姿が思い浮かぶ。その時、同じ台詞を言って背中を押したのは自分だ。点滅しだした逆方向の信号を確認すると玖珂は家路へとゆっくり歩き出した。
いつもならTAXIで帰るのだが、今日は歩いて帰るのもいいかと思い直し玖珂はそのまま歩き続ける。人通りの多くない道では、誰ともすれ違うこともな く、自分のアスファルトへ下ろす足音だけが聞こえている。途中で暑くなって上着を脱ぎ片手で背中へかける。指でネクタイをゆるめれば少し空気が入って暑さ が和らいだ。
自宅近くの角をまがりマンションのエントランスに入る。鍵を探すためにポケットに手を入れた所で、玖珂の背後から声がかかった。その声に玖珂は驚きを隠せない。
聞き間違うはずがない、ここにいるはずがない。
玖珂がゆっくりと振り向いた先には、渋谷が立っていた。
「…渋谷…君……」
何故彼がここにいるのか、玖珂は鍵を握ったまま動けないでいた。
「こんばんは……インターホンを押したんですけどいないみたいだったので、待たせてもらいました」
「……いつから?」
「あ、でも。俺もさっききた所です……」
「そうか。ちょっと寄っていたから。悪かったね……待たせて、電話くれればよかったのに」
「いえ。丁度充電が切れちゃって……。それに、直接会ってお願いしたいことがあったので……」
「……お願い?」
少し酒を飲んでいるのだろうか頬が上気している。渋谷は玖珂の側にくると俯いたまま呟いた。
「明後日……玖珂さんお休みだって前に仰ってましたよね。……もし時間がとれるようだったら付き合って欲しい場所があるんです。用事があるなら断ってくれて全然いいんですけど……」
「明後日?別に構わないが……渋谷君は仕事じゃないのか?」
「俺は……休みを取ってあるんです」
「そうなのか……時間は?」
「夕方くらいに……」
「わかった。じゃぁ時間をあけておくようにするよ。場所は……今はきかないほうがいいかな?」
「……ええ」
渋谷は顔をあげて少し微笑んだ。笑っているのに寂しそうなその表情は、出会った頃よく渋谷が見せていた表情だ。どこに付き合って欲しいのかはわからなかったが、まだ渋谷が自分から離れていない事に玖珂は心から安堵する。
「待ち合わせの時間は明日メールします。今日はこれで……」
「もう時間も遅い。電車、ないんじゃないのか?」
「大丈夫です……。タクシーを拾って帰りますから」
自分が酒を飲んでいなければ自宅まで送ることも出来たがそうもいかない。もどかしく思いながらも玖珂はそのまま見送るしかなかった。
「わざわざ有難う」
「いえ、俺の方こそ勝手なお願いを押しつけてしまって」
「いや、いいんだ」
「じゃぁ。明後日に」
「あぁ。メール届いたら返信するよ」
「お願いします。じゃぁ……おやすみなさい」
「あぁ、おやすみ……」
玖珂は渋谷の背中が見えなくなるまでエントランスを出て見送った。すぐにTAXIを拾えるといいのだが……。
渋谷がいなくなった後、玖珂はフと空を見上げる。真っ暗な中にくっきりと三日月が浮かんでいる。
対照的なその存在の分かれ目を見つけるように、玖珂はしばらく空を見続けた。