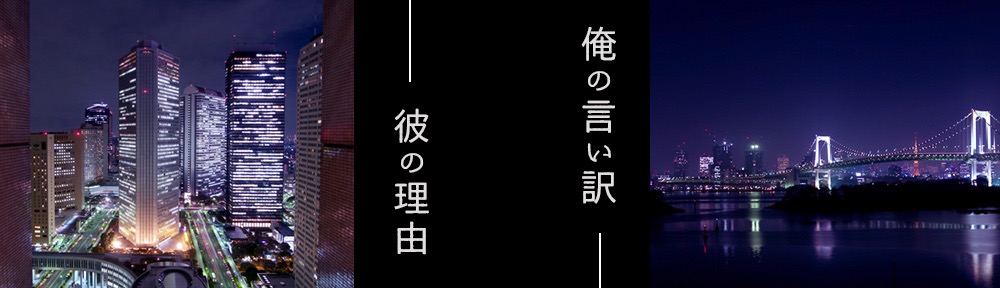俺の言い訳彼の理由6
土曜の朝、久々の休日にゆっくりと目覚めた玖珂は、カーテンの隙間からすでに昇りきっている日差しに目を細めて窓を開けた。強く差し込む日差しが窓ガラスに反射して虹色の光を室内へ導く。
昨夜はあんな事があったせいで中々寝付けず、眠る前にナイト・キャップを煽ったのだ。そのグラスがそのまま窓際のツールに置かれているのを見て玖珂は再 び昨日の出来事を反芻する。いくらか靄がかかったようになっている頭を軽く振ると、何も羽織らない姿のまま立ち上がり、ベッド脇にかけてあるバスローブを 纏った。
普段スーツをかっちり着こなすせいか休日を家で過ごす時は自然とゆったりとしたものを選ぶことが多いのだ。無造作に散らばった前髪を手櫛でかき上げると フと息を吐いた。どちらかというと朝に弱いので、洗面所で一通りの行動をしないとうまく頭が回らない。歯磨きの後、冷たい水で顔を洗い、漸く目が覚めた所 で玖珂はリビングへと向かった。
喉の渇きを癒すために冷蔵庫へと向かい8割が酒で埋まっている中からペットボトルを取り出す。
── 渋谷君か…。
昨晩の名刺を卓上に置き、手にしたミネラルウォーターのボトルキャップを開けながらソファに腰を降ろした。玖珂の中で渋谷と重なったその人物の姿を思い出す。声も、その身体の柔らかな感触も、何もかも。まるで昨日の事のように蘇ってくる。
── 何処かに写真がなかっただろうか……。
ローテーブルから一本煙草を抜き取り燻らせながら、その所在を思い出そうと考える。記憶の確かさを確認したかったのだ。このマンションへと越してきてか らかなり経つが、過去の写真を見ようと思う機会も今までなく、はっきりとした収納場所が思いつかない。しかも、引っ越しをする度に、昔の物は処分してし まっている為あるかどうかさえ怪しいのだ。
玖珂は思い立ってクロゼットの中を引っ張り出してみることに決め、最後まで吸い終わった煙草を灰皿へと落として立ち上がった。
寝室に戻り3帖ほどあるクロゼットの奥にあるダンボール箱を開けてみる。長らく触れる事のなかったそれは埃を被っており、中には様々な物が並べてしまわ れていた。日頃、こんな昔の感傷に浸ることはまずないし、また引っ越しでもしない限りは触らないであろう物だ。卒業アルバムや子供の頃の家族の写真が入り 交じっている。
まだ小学生の弟と一緒に写っている何枚かの写真を懐かしく手に取った奥にそれはあった。玖珂は奥にある大きめの白い封筒へと手を伸ばす。【写真】とだけ自分の字で書いてある。
周りのスーツを少し脇によけ、そのままクロゼットの壁に背を預けた。10年以上も前の物なのにその封筒は汚れてもおらず真っ白なままだ。心の中の思い出と共にしまわれたそれを開くのには少しだけ恥ずかしいような気分も伴う。
開いてみた中には5枚の写真が入っていた。玖珂はその写真を見て暫し呆然とした。息を飲んで5枚の写真を順に見返す。
写真は玖珂が母親を亡くした後で大学を中退する前の時期の物だ。その少し前から、大学の友人に誘われて個人塾の講師のバイト をしていた事があった。バイトはそれだけでなく、他のものを掛け持ちしていたが、塾講師のバイトは時給もよく、教育学部だった事もあり勉強にもなると思っ て引き受けたのだ。元々子供好きだったので塾の講師のバイトはとても性にあっており、誘ってきた友人が辞めた後も、玖珂はそのまま続けていた。
バイト先の塾は個人で経営している規模の小さいもので、通ってくる子供達は有名進学校を目指しているというわけでもなく、学校の授業の補助的に通っているというスタイルだ。
家族経営だったので、経営者でもある塾長の妻が、授業が終わると子供達にジュースを作ってきたりとアットホームな雰囲気だった。ちょうど母親を亡くした ばかりだった玖珂はその雰囲気がとても居心地の良い物に思えて、自分の持ち授業がない時でも時間があれば手伝いに行ったりしていたのを思い出す。
しかし、居心地が良かったのはそれが理由なだけではなかったのだ。親切にしてもらっている塾長の妻でもある女性に玖珂はいつしか好意を寄せるようになっ ていた。その頃で一回り以上年上なのは間違いなかったが、無邪気な性格の女性でとても可愛らしく生徒だけでなく玖珂ら講師陣達にも親切で優しかった。
母親が他界した後、頼れる身内もいなかった玖珂が弟を養い、そして自分の生計を立てるために、大学を辞めてホストになるとうち明けた時も、誰よりも心配してくれたのも彼女だった。
皆で授業を終えた後、飲みに連れ出してくれたりと二人で過ごしたことも数回ある。
そして、密かに想いを寄せる中、バイトを辞めることにした最後の日。
彼女に家庭がある身なのをわかってはいたが、日増しに募っていく想いに当時の玖珂は悩んだ末、ついに告白をする事に決めたのだ。
ただ、それは付き合って欲しいという類のものではなく、最後に自分の気持ちを伝えておきたい。それだけのつもりであった。うまく話をつけ、最後の日二人 きりで食事に行く機会を作った玖珂は、そこで決めてきた通り告白をした。今思えば自分の気持ちを押しつける形での告白はただの我が儘だったと思う。そして その後、玖珂の予想していなかった展開が訪れたのだ。
玖珂の告白を聞いた彼女の口から思いもかけない言葉が出てきた。
「私も…………私も貴方が好きよ」
彼女がそう言った時の表情まで今も思い出すことが出来る。少し恥ずかしそうにうつむいた彼女はいつも見ている優しい塾長の妻ではなく、一人の女性だった。
しかし、好きだと言いながらも付き合うことは出来ないとその後に続いた。まだ学生だった玖珂に彼女を奪うほどの経済力があったわけでもなく、自分の立場もわかっていたはずだった。
いっそ想いが通じなかったらそこで諦めもついたのかも知れないし、今ならもっと違う選択肢を選べたかも知れない。だが、相手も自分に好意を寄せている事 を聞いてそれでも身を引く事が出来るほどに我慢強かったわけでも、大人だったわけでもなかった。高揚する気持ちを抑えられず出た言葉。
「だったら今日だけ……今晩だけ、俺の物になってくれませんか」
強く掴んだ玖珂の腕に自分の手を重ね、だまって頷いた彼女は今思えば相当の覚悟がいったのだろうと思う。こうなる事を予想していたのかも知れない。人目を避けて少し離れたホテルへ向かう道すがら、彼女は相づちを打つ以外は一言も喋らなかった。
玖珂と彼女はその夜を共に過ごした。
ずっと焦がれていた彼女の肢体は想像していた通りしなやかで…夢中で肌を重ねたのを覚えている。薄暗いホテルの灯りの中で何度も口付けをし、時間を惜しむように…繰り返し彼女の名を呼んだ。
「……朝子さん」
同年代の女達が皆くだらなく思えるほどに彼女は成熟した大人の色香を纏っており、玖珂の猛った欲望を優しく包み込んだ。
限られた時間だけというのが火を付けいっそこのまま何もかも捨てて彼女を奪ってしまいたくなったのも本当だ。
そして、何度か交わり最後に見た彼女の目には涙が浮かんでいた。その涙の理由は最後まで結局聞かせてもらえなかった。彼女もまた一晩限りの契りを、それとも玖珂を、放したくなかったのかも知れない。
朝になって目が覚めるとホテルにはもう彼女の姿はなく、一人残された玖珂は冷たいシーツを握りしめて彼女を思い出しながら、終わってしまった恋を必死で繋ぎ止めた。夢だったのではないか…。そう思いながらも身体の芯に籠もった熱で真実だった事を思い知る。
渋谷 朝子
思い出されるあの頃の想い。玖珂が今までで一番愛した女性の名前だった。
写真の中の笑顔はまるで生き写しのように渋谷にそっくりだった。玖珂より少し下の息子がいると一度だけ話をきいた事がある。それが彼であることは写真を見る限りもう間違いはなさそうだった。重なる偶然と、その出会いに驚きを隠せない。
彼を最初見た瞬間に惹きこまれたのはそのせいだったのだろうか。彼女に生き写しだから……?
玖珂はそう考えて首を軽く振った。彼は朝子に似ていても、朝子ではないのだ。
だとしたら、自分は確かに彼自身に惹かれているのだろうか。
── 例えそれが今は自分の言い訳だとしても……。
* * *
渋谷は朝になって着替えもせず眠ってしまっている事に気付き、うっすらと目を開けた。見慣れたリビングの天井が視界にうつる。疲れ切って寝てしまったせいか目が覚めたばかりだとは思えないほど身体がだるい。起きあがってみると頭が酷く痛んだ。
こめかみを指で押さえながら立ち上がり、そのままスーツを脱ぎ捨てる。週明けのゴミの日に全部捨ててしまうつもりでいた為、そのまま丸めて袋へと押し込んだ。そして、自分が履いている見慣れない下着を見て昨日のことを思い出す。
ポストに鍵を入れた際に名字だけは知ることが出来た。彼の名は玖珂というらしい。この下着も、そして椅子にかけてあるスーツの上着も、玖珂という男の物なのだ。
話し方や雰囲気を考えても自分より年上な気がするが、はっきりとはわからない。物腰の柔らかさからして客商売か何かなのかもしれないなと渋谷は予想する。
昨日の出来事の中で酷い記憶より玖珂の記憶の方が色濃く残っているのは何故なのだろうとぼんやり考える。あまり人に感心を示す性格ではないはずなのに、昨日に続き様々な事を憶測してしまう自分がいた。
── 優しさにほだされたのか……。
そう考えて自分を嘲笑する。この歳になって、そんな安っぽい感情を抱くとはまるで冗談のようにも思えた。人は弱っている時に手を差し伸べられると自然にそれを掴んでしまう弱い生き物なのだ。だから自分も……そうに違いない。
渋谷はあまり馴染みのない自分の感情に、何処かでそう言い聞かせ納得しようとしていた。
着替えを取りに行こうとして立ち上がった瞬間、痛みに眉を顰める。何か薬を塗ったりした方がいいのだろうが、自分の指でさえそこへと振れる事に恐怖を感 じてしまう。出来るだけ安静にして過ごして自然に治癒するのを待つしか無いと渋谷は考えていた。気持ちを逸らそうと何か別のことを考えようとする思考を整 理する。
キッチンへと向かい、何か食べようかとも思ったが、昨日の昼食を軽く摂って以来食事をしていないにも関わらず、腹がへっておらず食欲も全くなかった。常 備してあるゼリー飲料を仕方なく口に運ぶ。食欲がないのは熱があるせいもあるのだろう。体温計できちんと計ったわけではないが、自分の掌を額にあててみれ ば熱があるらしい事だけはわかる。頭痛薬には解熱作用もあるので、取りあえず規定量を服用して様子を見ることにした。
仕事が休みの日は、普段からあまり外出をする事はなかったが今日もその予定である。一人暮らしのため、必要があれば自分で買い出しに行かなくてはならな いが、その必要も今のところない。玖珂から借りている上着をクリーニングに出したいが、今日出掛けるのは止めておいた方が良いと判断し、渋谷はフと今まで の休日を思い返していた。
思い出す限り、誰かと休日にでかけたりした事が無かった。前は月に一度くらいは藍子が休日に訪れる事はあったが、渋谷は終わらない持ち帰った仕事を片付ける為にPCへと向かい全く相手にしない為、最近は彼女が自宅へくる事もなくなっていた。
いつも予定など何もない。それを寂しいと思った事もなかったはずだった。
渋谷は気持ちを誤魔化すために書類に手を伸ばす。誰が何のために自分にあんな事を仕向けたのか、そしてそれは、本当に藍子と関係があるのか。考えることは 沢山ある気がするが、何より早くいつもの毎日へと時間を戻したかった。必死で書類の数値に集中することでどうにか冷静さを取り戻す。
どんな事が身に降りかかろうとも時間は止まってくれるわけではないのだから…。現実問題として週明けの水曜には、自分が手がけてきて去年から続いている プロジェクトの発表会がある。長らく暖めていた企画は渋谷を中心としてまわっており、責任者としてはその日に全てをかけて今まで準備をしてきたのだ。
くだらない感情に惑わされている余地は一寸たりともない。仕事以外に時間を使うのは無駄以外のなにものでもないのだから…。
書類を持ったまま渋谷はパソコンデスクへと向かい電源を入れる。鈍く続く頭痛に眉根を寄せて画面に集中するように目を細めた所で、それを遮るようにけたたましい音が鳴り響いた。自宅の電話がなった事で携帯の充電が切れていることに気付く。
自宅の電話機は、本体と子機が同じ部屋にあるので二重に鳴り響く電話の音を無視するわけにもいかない。渋谷は立ち上がると電話を取りに行き受話器を耳に当てた。休みの日にかかってくる電話等、勧誘か何かだろうと不機嫌な声を露わにする。
「はい、渋谷ですが……」
『……』
── 誰だ?
外から掛けてきているのか騒がしい雑音だけが耳に届く。
「もしもし?」
再度耳を澄ませても何も聞こえない。名前を名乗らない相手にため息をつき受話器を遠ざけた瞬間相手の笑い声が聞こえた。何人かいるのか男の声と女の声が混じったような笑い声だ。その女の声には聞き覚えがあった。
「藍子……なのか?」
名前を呼んで自分の声が喉にからまったように掠れているのに気付く。無理矢理に唾を飲み込み受話器を耳へと押し当てる。声の向こうから聞こえてくる音声がノイズに歪む。受話器を握る手が汗で滑りそうになった。
少し電波の途切れる音がした後女の声が途切れ途切れに聞こえた。
『…………さ……なら』
何とか聞き取れた言葉は確かに「さようなら」と言っていた。含んだ笑いを込め楽しそうに出されたその言葉は、本来のさようならの持つ意味など全く関係な いように使われている。渋谷はその言葉をきいた瞬間、神経を金属で撫でられるような寒気を覚えて通話ボタンを無意識に押して通話を切っていた。
掴んでいた力が抜けて受話器が床に落下する。転がった受話器からノイズとともに今も言葉が聞こえてきそうだった。
昼近い眩しい日差しが一瞬にして暗転したように感じる。受話器を床に落としたまま渋谷は吐き気を感じて口元に手をあてた。藍子の声がいつのまにかすり替わり一番愛しい者の姿と重なる。
さよならという言葉がショックだったわけではない。
藍子でなくなったそれはゆっくりと口を開き、笑顔のままで不釣り合いな言葉を渋谷に投げかけ迫ってくる。
『さようなら…さようなら、さようなら……お……ゃん』
耳を塞いでも渋谷の中に響き渡るその声は自分の罪なのだ。あの日の怯えたような視線が渋谷に突き刺さる。刺さった棘は未だに自分を縛る鎖のように絡まってくる。一日たりとも忘れた事のない己の罪。
── それが贖罪になるならとわざと忘れないようにしてきた感情。
バサッと音を立てて椅子に掛けてあったスーツの上着が落ちた事で渋谷は我に返った。胸が苦しく呼吸がうまくできない。はぁはぁと荒い息づかいを繰り返しながら、その場に力無く膝を折り部屋を見渡す。額から、じっとりと滲んでくる嫌な汗が流れる。
暫くして落ち着きを取り戻すと、部屋の中は眩しいほどに明るくて……。床へと転がる受話器を拾い立ち上がると、通りを通っているらしい人の話す声が小さく聞こえた。
── 何も変わらない、何もない日常。
── 何も変われない、何も持っていない自分。
息苦しさに思い切り開け放った窓から風が吹きつけ渋谷の黒髪を悪戯に梳いていった。