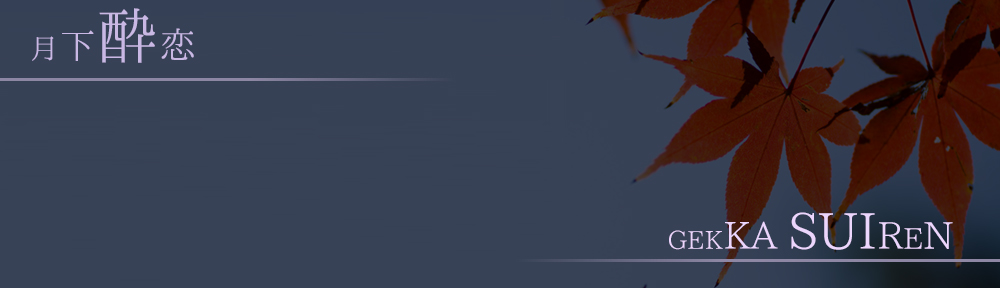
「そうか、……それで?」
穏やかな表情と静かな肯定。グラスを傾け先を促す玖珂に、渋谷はそのまま話しを続ける。アルコールのせいもあってやや饒舌になった渋谷が語るのは、ここ最近の仕事の話しである。熱の籠もった話しぶりに玖珂は嬉しそうに目を細め、横に座る渋谷の仄かに色付く頬を見つめていた。
付き合って間もない頃、渋谷は何に関しても遠慮がちで言葉も態度も何処か抑えている節が垣間見れた。勿論それが嫌なわけではない。だけど、一緒に居るときはもっと気を遣わずいて欲しいというのが玖珂の細やかな願いでもあった。「遠慮をするな」と言った所でそういう部分が治るわけでもない。
こういう事はやはり時間が重要なのだ。共に過ごす時間と比例して渋谷の硬さがゆっくり溶けていくのを待つのもまた楽しみでもあった。
しかし、今こうして渋谷の話に耳を傾けていると、以前より随分その距離が縮まったように感じていた。何事にも一生懸命で真剣に自分の仕事に取り組んでいる姿は同じ男として尊敬すべき物でもあったし、恋人として見ればそれはとても愛しく思えて、どんな話しでもずっと聞いてやりたくなる。
ゆっくりと流れる時間の中。玖珂の持つグラスに浮き出た水滴が磨かれたガラスの表面を滑り落ち、指を濡らす。一度テーブルへグラスをそっと置き、他の指で水滴を拭うと、玖珂は煙草を一本抜き出して口に咥えた。
月下酔恋 ――GEKKA SUIREN――
今夜は玖珂が贔屓にしているというフレンチレストランで夕飯をとり、その後都内のバーへ移動して、終電までの数時間、二人で夜の余韻を楽しんでいる所であった。
バーというと、カウンター席が多いイメージがあるが、今、玖珂達がいるのは完全な個室、世間一般でなぞらえるとしたらVIPルームである。――静かな場所で、祐一朗の話が聞きたいからね……――そう言って玖珂が連れて来たこの場所も、やはり玖珂の知り合いらしく、店内に入って一言玖珂が声をかければ、すぐに店長らしき人物が挨拶に来て奥の部屋へと通してくれる。
カウンターを通り過ぎ、店の奥にある扉を開く。端からみれば普通の扉に見えるし、ここから先は従業員専用の場所と思いそうな佇まいである。しかし、その扉を開くと、表の店内よりずっと豪華な調度品が並べられている廊下があり、その両面に個室がある作りだったのだ。普通の客がここへ足を踏み入れることは多分ないのだろう。
それでも、通り過ぎる部屋の中から先客の気配が確かにしている所を見ると、客は自分達だけではないようだ。
玖珂はいつも通り、周りを気にしている様子は無かったが、渋谷は毎度の事ながら驚きを隠せない。
音を吸収する絨毯を踏んで玖珂の後から続き、小さく声をかける。
「こういう場所……、普通の人はこれないんですよね?」
「そんな事も無いだろうが……、まぁ、存在を知らなければ来るのは難しいかもしれないな」
「玖珂さん、本当にお知り合いが多いですね……。顔が広いって言うか……」
「色々な客の好みに合わせて使う店を選んでいたから、自然にね……。選択肢が多いというのは便利な物だ」
そう言って微笑む玖珂に、渋谷はやはり感心せざるを得なかった。ホストの世界がどういったものか詳しくは知らないが、世間のホストが全員玖珂のように何処に行っても顔が利くとはとても思えない。だとしたら、やはり玖珂自身が社交的であり、人脈が広いのだろう。
壁に掛かる現代アートの絵画を眺めつつ、そんな事を考えながら歩いていると、玖珂と少し距離が出来ており先に行っている玖珂が渋谷を待っているのが視界へと入った。慌てて足を速め玖珂へと並ぶと、玖珂はドアを開いて渋谷を先へ迎え入れ、その後自分も個室の中へと足を踏み入れた。
室内へ入ってみると、二人で貸し切るには勿体ないほど奥行きのある空間で、その中に黒の革張りのソファがゆったりと置かれていた。深紅に輝く鏡面仕上げの床は綺麗に磨かれており、その表面に立っている二人の姿をくっきりと映している。やや落とした照明のせいで室内は暗く感じたが、目はすぐに慣れた。都会的な洗練された空間は、多分どこかのインテリアコーディネーターが手がけた物なのだろう。
渋谷がジャケットを脱いでソファへと腰を下ろすと、ドアがノックされ店員が入ってきた。玖珂がスーツのジャケットを脱ぎつつ店員へと振り向く。
「いらっしゃいませ、玖珂様。今夜はどうなさいますか?」
長年勤務しているのかロマンスグレーの髪をオールバックにしている店員はそう若くもない。穏やかに微笑む店員に玖珂が少し間を開けてから口を開いた。
「……いつもの酒と、何か軽くつまめる物を持ってきてもらおうかな。渋谷君は、どうする?」
最近は祐一朗と呼ばれている事が多いが、こうして外部の人間が居る場所では玖珂は以前と同じく渋谷君と呼んでくれる。そんな細やかな気遣いが出来るのも玖珂だからなのだろう。メニューがない店での注文に慣れていない渋谷は瞬時に返事を返せない。
「えっと……俺は、じゃぁ何か甘くないカクテルで……玖珂さんのお勧めがあればそれがいいです」
自分が相変わらず「玖珂さん」と呼ぶ事しかできないのは、自らの不器用さをわかっているからである。一度名前で呼んでしまうと、フとした瞬間にも切り替えられずそのまま呼んでしまう恐れがあるからだ。
「そうだな……、じゃぁ彼にはマンハッタンを用意してもらおうか。ベルモットはドライに変えて」
「かしこまりました。では、お待ち下さい」
深くお辞儀をした後店員が出て行く。
玖珂は大理石のテーブルへ煙草を取り出して置くと、渋谷の隣へと腰掛けた。
向かい側の席も空いているので、てっきり向かい合って座る物とばかり思っていた渋谷は、予想外に玖珂が傍に座った事で僅かに心音が早まる。
付き合いだしたばかりというわけでもないのに、どうしても慣れる事が出来ない。ネクタイを少し緩めた玖珂の胸元から、嗅ぎ慣れたいつもの香水が渋谷の鼻先を淡くかすめる。それだけで、まるで初恋の相手と会っているかのような気分になってしまう。一番落ち着く匂いでもあるのに、どこか胸がキュッと痛くなるような……。黙り込んでいる渋谷の顔を、玖珂が覗き込んだ。
「……勝手に頼んでしまったが、大丈夫だったかな?」
「え?……あ、……はい。大丈夫です」
渋谷は顔を上げたが至近距離の玖珂に視線を合わせられないまま、眼鏡を直す。
「マンハッタンは以前飲んだことがあるので……。でもベルモットをドライにというのは……?」
「……ああ、一般的なマンハッタンはスイートベルモットで作るだろう?」
玖珂はそんな渋谷に気付かず、煙草の箱から一本抜き出して火を点け渋谷とは逆の方向へ紫煙を吐き出す。
「そうなんですか?」
「あぁ。それをドライベルモットにすると少し辛口になる。さっきフレンチを食べてきたから、その方が口に合うだろうと思ってね」
「なるほど……、アレンジバージョンなんですね」
「そうだな。他のアレンジでセントラルパークというのもあるから、興味があったら後で飲み比べてみるといい」
「はい、玖珂さんとお酒を飲むようになってから、俺もちょっと詳しくなった気がします。披露するような場所も特にないんですが……」
渋谷はそう言って苦笑する。
間もなくして酒と、ちょっとした軽食が運ばれてきて二人で本日二度目の乾杯をした。
玖珂が勧めてくれたカクテルを一口飲むと、確かに以前飲んだ物とは少し違った。チェリーの代わりにオリーブが添えられており、後味もとてもよい。「美味しいですね」と感想を告げれば、玖珂は「それは良かった」と微笑む。渋谷はもう一口飲んで、喉を湿らせるとカクテルグラスをテーブルへと置いた。
「いつもの」と頼んでいた玖珂には予想通りウィスキーが運ばれており、玖珂はそれを自分でグラスへと注いでいる。玖珂のつけているYシャツの袖のカフスボタンを眺めていて、渋谷はフと前から聞いてみたかった事があったのを思いだし、玖珂へと振り向いた。
「あの、玖珂さんの着ているスーツってどこか決まったブランドの物なんですか?」
玖珂と会う時は仕事帰りが大半のため、互いにスーツを着ている事が多い。しかし、数着を着回している渋谷とは違い、玖珂は同じようであってもよく見ると若干違うスーツ姿なのだ。何度デートをしているか数えたことはないが、多分今まで同じ物を着ていた事はなかったように思う。
急にスーツの事を聞かれ、玖珂は徐に自分の着ているスーツを確認する。
「ん?俺のスーツ?……いや、ブランドの物を着る時もあるが、大半はテーラーの物だな」
「あ、じゃぁ、全てオーダーメイドなんですね。俺は既製品しか買った事なくて」
「サイズがあれば、それもいいと思うんだが……、どうやら俺は腕が普通より長いらしくてね。既製品でしっくりくる物があまりないんだ」
「なるほど……。腕だけに合わせるとサイズも大きくなりますもんね」
「そうなんだよ。スーツが身体に合っていないと締まらないからね」
「そうですね、俺も一回オーダーメイドのスーツとか作ってみたいな……。……ちょっと憧れるけど、一人で行くのは敷居が高くて中々……」
「じゃぁ……、今度俺と一緒に行って、祐一朗も一着揃えるといい」
「え?いいんですか?」
「ああ、勿論構わないよ。俺が行っている所でいいなら」
「楽しみです、その時は是非ご一緒させて下さい。……でも、そんな一張羅、何処に着ていこうかな」
渋谷が笑みを浮かべてそう言うと、玖珂は腰へ手を回し首筋へと唇を寄せる。何度かくすぐるように口付けを落とし、耳元で囁かれれば、渋谷の身体はそれだけで反応してしまう。
「俺と会う時に、着てくればいいんじゃないか?……でも……」
渋谷がくすぐったそうに肩を竦め俯くと、露わになった白い項をそっと指で悪戯になぞり玖珂が小さく笑う。
「最後は、……脱がせる事になるかもしれないから、勿体ないかな……」
渋谷の体温が一気に上がる。それを悟られまいとするものの、平然と返事を返せる余裕はやっぱりまだなくて……。渋谷は俯いたまま小さく洩らす。
「……玖珂さん、俺を困らせてからかってるでしょう」
「それは心外だな、普通の会話のつもりだが?」
渋谷は自分でも熱を感じて熱くなる耳に掌を当てる。隣にいる玖珂が優しく微笑み、近づいていた身体を離す。会う度に甘い台詞を言ってくる玖珂はいつも通りなのに、その言葉のひとつひとつはいつも決まって渋谷の胸を甘く疼かせる。
玖珂が4杯目の酒をつぎ、渋谷が3杯目のカクテルに口を付ける頃には、話しはいつしか渋谷の仕事の話になっていた。程よく酔いが回ってきて、心地よい時間である。
渋谷は酒を一口飲み真面目な表情で今回の自分が担当している件について話しを続けた。
「もう、昔みたいに都市型の展開だけではやっていけない時代なんですよ……。ブランド=それだけで価値があって売れる商品。のような絶対的な図式も今はなくなりつつあるので、ネット上も含めてもっと広い地域を視野に入れて展開しないと中々世間に浸透しないんです」
「そうか、……それで?」
「……それにはやはり実際手にとって貰う機会が必要になってきますよね。今回、俺の部署で担当しているのは新規のブランドだからまだ知名度もなくて、やはりそういう点でも地方にあるショップ等も視野にいれて展開したほうがいいんじゃないかって話しになっていて……」
「……確かに、祐一朗の言う通りかも知れないな」
一言一言に相づちを打ちながら玖珂は熱っぽく仕事を語る渋谷に目を細めている。
「あ……すみません。何か……、俺の仕事の話しばかり一人で語っちゃって……」
渋谷が、話しを途中で中止して少し恥ずかしそうに笑ってみせる。特にこれといって入れ込んでいる趣味もないので、どうしても自分が話す話題は仕事の話になってしまう事が多いのだ。
相変わらず目が回るほどの業務を毎日こなし、深夜残業に出張にと世のサラリーマンの多忙を一気に体現して見せていると言っても過言ではない生活を送っている。やっと重なった仕事帰りの時間にこうして玖珂と会っている時でさえ、仕事の話をしてしまうのは我ながらどうなのかと考えてしまう。
しかし、玖珂は会うとだいたい決まって一度は渋谷に仕事の話しを振ってくるので、その度に今の自分が担当している仕事に関して語る結果となる。玖珂にとっては、マーケティングの話題などそう面白くもないはずなのに渋谷の話を聞く玖珂はいつもとても嬉しそうで……、だけど、こうして自分の話を興味深そうに聞いてくれる事が、渋谷にとってはとても嬉しい事でもあった。
「祐一朗は、本当に仕事が好きなんだな」
「好きというか……それしか、俺にはないですから」
自嘲するようにそういう渋谷に玖珂は「そんな事はないだろう?」と優しく微笑む。
「俺は、祐一朗の仕事の話しを聞くのは好きだよ」
「そう……ですか?」
「ああ……仕事自体は大変だと思うし、色々嫌なこともあると思うが、とても楽しそうに話してくれるからね。それを聞くのは俺も楽しい、色々と勉強になるよ。それに……、男は仕事に魅力を感じなくなったら、そこで止まってしまうからな」
確かに、玖珂の言う事は尤もである。その気持ちの比重に差はあるかもしれないが、男である以上今の仕事に生き甲斐を感じなければ一生働いていくなんて到底無理だと思う。どんな職業でも辛い事や嫌な事はあるだろうが、それでもやる気になれるのは自分の仕事に誇りを持っているからである。
「そうですね……。大変だと文句を言いながらでも、何処かでプライドをもって仕事をしているのが普通なのかもしれないですね……」
「ああ、そうだな。……それに、案外男は不器用だって言うから、何かに入れ込んでいないと自分を見失うのかも知れないね」
とても不器用とは思えない玖珂がそんな台詞を言うので渋谷は思わず苦笑する。
「玖珂さんは、とても不器用には見えませんけど」
「さぁ……、それはどうだろうな」
玖珂が渋谷の言葉を受けて、わざと考え込むように腕を組む。唐突に渋谷の目をじっと見据えて少し微笑むと、渋谷はその視線から逃れるように残っている酒に手を伸ばし、冷たいグラスを握りしめた。熱くなっている頬に、この冷たいグラスを押し当てたいくらいである。
「もし俺が器用だったら……、今、祐一朗にもっと素敵な口説き文句を言えるはずなんだが」
「そ、それは……、……」
そう言って視線を逸らす渋谷を前に玖珂は冗談っぽく笑って見せた。こういう台詞を言う事で渋谷がどう反応するか、玖珂はお見通しなのだろう。そもそも、こういう事をサラッと言うこと自体が器用な証拠である。
渋谷は、いつのまにか乗せられる甘い言葉の旋律に今回もあっさりひっかかってしまった事を少し悔やんだ。どう上手く切り返したとしても元ホストである玖珂には叶わないのだと思い知る。
「何だか悔しいな……。俺も、玖珂さんみたいに、気の利いた台詞が言えればいいんですけど」
渋谷が自分の会話術の拙さにがっかりし肩を落とすその様子でさえ、玖珂には愛しくうつる。――そんな君だから、俺は愛しく感じるんだが――そう言いたい所ではあったが、小さく溜息をつく渋谷にこれを言うと本気で落ち込ませてしまうかもしれない。玖珂は言葉を胸の内へとしまってにっこり笑うと渋谷の横顔に視線を移した。