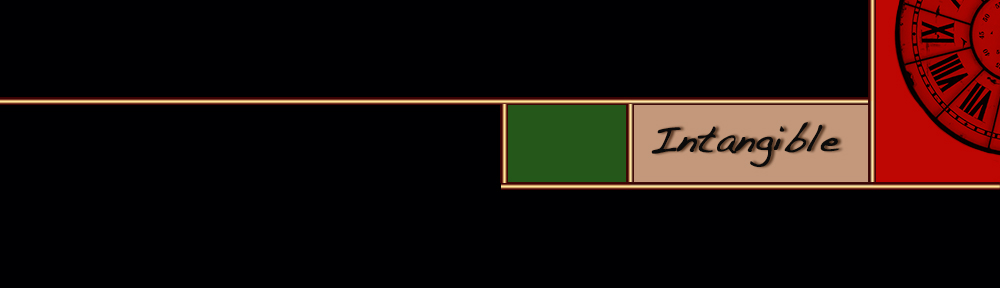
行き交う車の排気ガスを毎日浴び、うんざりしているであろう街路樹。
しかし、この季節ばかりは自身が街を彩る事にどこか得意げな様子がうかがえる。幹から伸びた、葉を落とした枝先で点滅する、スノーフレークを象ったイルミネーション。夜になれば並んだ街路樹は大通りごと全てを幻想的な世界へと変えてくれる。
そんなクリスマス当日、渋谷はトレンチコートの襟から入り込む冷たい風にほんの少し身体を震わせ白い息を吐いた。昨日までは暖かい日が続いていたが、今日は急に気温が下がっているようだ。
そろそろマフラーも出した方がいいかもしれない。
冷たくなった指先に一度ハァと息を吹きかけて擦り、通りの店の前で足を止める。
玖珂は甘い物があまり好きでは無い。それは知っているけれど、クリスマスにケーキがないのは少し寂しいのではないか。そんな事を考えながら、渋谷は帰宅途中にあるケーキ屋のショーケースに並ぶクリスマスケーキを眺めていた。
空を駆けるサンタを乗せたソリが、窓硝子に綺麗に描かれている。こんな小さなケーキ屋でさえクリスマス一色である。
土曜日の午後、天気は生憎曇り空で天気予報では雪が降るかも知れないと言っていたのを思い出す。
――……。
空を見上げるとその天気予報はあたりそうだなと思えた。
雨ではガッカリする恋人達も多いかも知れないが、雪となれば話は別だ。うっすらと街を覆う真っ白な雪は、街のあちこちに飾られたイルミネーションの光を柔らかく包む。交通機関が麻痺するほどの積雪は望まれていないだろうが、都心でのホワイトクリスマスを待ち望む声は少なくない。
――やはり、小さいのを買って帰ろうかな……。
もし玖珂が食べなければ、自分が明日も食べれば終わるようなサイズなら問題ないだろう。渋谷がケーキ屋のドアに手を掛けた瞬間、ポケットで携帯が振動した。
一度手を止め、少し道の脇へ寄って携帯を取り出す。画面を見ると玖珂からメッセージが届いていた。先程最寄り駅についてすぐ、『今から帰ります』と打ったので、それへの返信かもしれない。
クリスマスの土曜日でもある今日、本当は休日の自分がどうして仕事帰りなのか。
それには理由があった。
取引先の都合で、どうしても今日の午前中に現地を視察しなくてはいけなくなったからだ。急遽その為だけに朝から出社。昼に現地を視察してから一度社へ戻り、企画の書類を書き直してから退社した頃にはすっかり夕方近くなっていた。
本当は昼過ぎに出掛け、その後、予約している店のディナーに向かいがてら、玖珂と二人でイルミネーションを見に行く予定だったのだ。
仕事だから仕方がないとはいえ、急な予定変更に一番ガッカリしているのは多分自分で……。渋谷は、昨夜の事を思いだして軽く溜め息をついた。
明け方近くなって帰宅した玖珂は、一通り寝る準備をした後いつものように渋谷を起こさぬようにベッドへそっと入ってきて腕を回す。幾度か渋谷の身体を確認するように撫でて、そのまま眠りにつく。昨夜もそうだった。
渋谷は、うとうとしながらもベッドが軋む音で目を覚まし、今日の予定変更を伝えようと振り向いた。起きていたことに驚いた様子の玖珂は、一度手を止め、すまなそうに渋谷と視線を合わせた。
「起きていたのか? それとも、起こしてしまったかな」
「いえ、伝えたい事があって……。起きてようと思ったんですけど、ちょっとうとうとしちゃってました。おかえりなさい」
「ああ、ただいま。伝えたい事って? なにかあったのか?」
玖珂は優しい笑みを浮かべて渋谷の額へと軽く口付ける。それがくすぐったくて、渋谷は恥ずかしそうに肩を竦めた。玖珂の方へ身体を向け残念そうに口を開く。
「明日……あ、いやもう今日ですね……。俺仕事が入っちゃって……。夕方には帰れるので夕食は間に合うと思うんですけど……」
「そうなのか、大変だな。わかったよ。じゃぁ、大人しく待ってるとしよう」
「休みだって言ってたのに、すみません。なるべく早く帰ります」
そう言いながら申し訳なさに視線を落とすと、玖珂は囁くように「気にしなくていい。気をつけて行っておいで」と渋谷の頭を撫でた。
「はい」
「それじゃぁ、早く寝ないといけないね」
「そうですね……」
一緒に暮らし始めて数ヶ月、別々に暮らしていた頃より格段に玖珂といる時間が増えた。しかし、互いの生活リズムが変わったわけではない。
夕方に出て行き明け方近く、どんなに早くても日付が変わった後に帰宅する玖珂と、普通の会社員である自分との時間は中々合わず、互いに数日寝顔しか見ていないなんて日もざらだった。
それでもこうして、話したい時に側にいてくれるというだけで、一緒に暮らしていて良かったと思う。
「玖珂さん」
「んー? どうした?」
「まだ少し、髪が濡れてる……」
渋谷はベッドからごそごそと手を出すと、向かい合う玖珂の額へ落ちる毛先を指でつまんで笑みを浮かべた。
「そう? ちゃんと乾かしたつもりだったんだけどね」
「風邪、引かないで下さいね」
「大丈夫だよ」
もう少しだけ玖珂の声が聞いていたくて、寝起きの回らない頭で他愛もない言葉を探してしまう。あと数時間で自分は起きなければいけないのに。
「あの……、クリスマスプレゼントの件……本当に今年はいいんですか?」
「ああ、そう約束しただろう? 祐一朗と一緒にいられるだけで十分だよ」
「そうですか……。わかりました」
「ほら。もう寝た方がいいんじゃないか? 後少しで、起きる時間だろう」
「……はい」
渋谷を気遣って話を切ると、玖珂は「おいで」と言って自分の胸に渋谷をそっと引き寄せると静かに目を閉じた。少しして聞こえてくる玖珂の寝息に誘われ、安心したように渋谷も眠りに落ちた。
その二時間後に起床すると、玖珂は当然眠っていて、起こさぬようそっとベッドから出て支度をした。
渋谷は自宅にいるはずの玖珂からのメッセージ画面を開く。帰るときに何か買ってきて欲しいというメッセージなのだろうか。
画面には一言だけ書かれている。
『お疲れ様。帰宅する時、ポストを見てきてくれるかな』
すぐに『わかりました』と返信したが、それは既読になった物の返信がくることは無かった。少し不思議に思いつつも携帯をしまうと、渋谷はケーキ屋のドアを開いた。
入り口に付けられている鈴が軽い音を鳴らし、店員がいらっしゃいませと笑顔を向けてくる。
「私、このトナカイさんが乗ってるのがいい!」
「ええ? こんなに大きいの食べきれるの?」
「いいじゃないかママ、クリスマスなんだし、これがいいって言っているんだから」
耳に飛び込んでくる三人家族の会話。
先に店内にいた家族連れは、暫く話し合った結果、はしゃいでいる娘が欲しがった大きなホールのケーキを選んだようだ。会計を済ませる間、渋谷は腰を屈めて少し後ろから色とりどりのケーキを見つつどれにしようか迷っていた。
ケーキ屋の奥から漂ってくるのは焼き菓子の焼ける甘い香り。それだけで、幸せな気持ちになる。そんな自分も、目の前の子供と同じく随分とはしゃいでいるように感じて、渋谷は一人恥ずかしくなって頬を掻いた。
家族連れが店を後にし店員と渋谷だけになると、店内にかかっているクリスマスソングがやけに大きく聞こえた。
「お待たせしました。お決まりでしょうか?」
「ああ。……ええと、この中で甘さが控えめの物はどれになりますか?」
「うーん。そうですね……。こちらの二点は、ビターチョコレートを使用しているので他の物よりは甘さが控えめになっています。中のラズベリークリームに少しアルコールが入っていますが、大丈夫なようでしたらお勧めです。男性の方にも人気ですよ」
「なるほど」
店員がさした二点のうち一点はブッシュ・ド・ノエルで、もう一点はシンプルな見た目の大人っぽいホールケーキだった。サンタが乗っているような可愛いクリスマスケーキではないが、小さな柊とMerry Christmasのプレートが飾り付けてある。丁度大きさもそんなに大きくはないようだ。
「じゃぁ、このホールのケーキをいただけますか」
「かしこまりました。蝋燭もお付けできますがどうされますか?」
渋谷は一瞬迷った後「蝋燭は……、結構です」と断った。誕生日でもないし、何だか蝋燭をお願いするのが気恥ずかしかったからだ。
一度奥へとケーキを持っていき、綺麗な箱に入れて戻ってきた店員は、器用な手つきで真っ赤なリボンを包装紙の上へと飾り、レジ向こうから渋谷へと手渡した。
ケーキをいれる紙袋もクリスマス仕様で、サンタの格好をした雪だるまが描かれている。思わず「可愛いですね」と率直な感想を呟くと、店員は「今日までの特別仕様です」と言って笑っていた。
「有難うございました。またのご来店をお待ちしております」
軽く会釈をし、受け取ったケーキを手に帰路へ着く。
アルコールが入っているビターなケーキなら玖珂も食べるかもしれない。
一人暮らしだった頃はホールのケーキなど買った事も無かったが、こうしてホールのケーキを買うというのは思いのほか楽しい物だなと感じていた。
ずっしりとした重さ、それを手に持って自宅へ帰るというのは、待ってくれている人がいるからこそ出来る事なのだ。
「……あれ? ……雨?」
渋谷の着ているベージュのトレンチコートに数カ所雨粒がおちて色を変えている。空を見上げてみると、それは雨粒ではなく降り出した小雪だった。地上におりてアスファルトに辿り着く頃にはもう水滴になっているような霙まじりの雪だ。
傘を持っていないので、ケーキが濡れぬよう少しだけ足を速める。
自宅マンションへ着くと、肩の辺りはあんな小雪でもかなり濡れてしまっていた。軽く払ってからエントランスのポストへ向かう。
基本的に郵便物は玖珂がとってくるので、渋谷がポストを見る事は滅多に無いのだ。ダイヤルを回してロックを解除すると、中にはメモのような紙が一枚だけ入っていた。
――何だろう……。
半分開いている状態なので、中の文字が見える。
渋谷はエレベーター前で足を止めてメモを片手で開いた。
『家に入ったら、浴室のシャワーを見ること』
――???
字は玖珂の字である。全く意味がわからないが、とりあえずそのメモをポケットへいれてエレベーターへ乗り込んだ。直通で最上階へ上がるそのエレベーターは専用なだけあり、人と鉢合わせることはまずない。未だにそんな高級マンションが自宅だなんて信じられない思いである。
一人暮らしをしていた一般的なマンションとは何もかもが違う。
すぐに辿り着いた玄関の鍵を開けて中に入り、後ろ手で鍵を施錠する。日も落ちているので真っ直ぐ伸びる廊下は真っ暗だった。反応して点灯するセンサーを足に纏って進む。
「ただいま、遅くなりました」
どこかにいるだろう玖珂へと声をかけ、コートを脱いで手に持つとひとまず居間へと向かう。硝子のドアをそっとあけてみると居間は暗くて、渋谷が入ってきたことでやっと照明がパッとついた。
「玖珂さん……?」
声をかけてキッチンの方も覗いてみたが、玖珂の姿はない。少し遅くなってしまったから、買い物にでも行ってしまったのか。一瞬そう思ったが、何も連絡なしにそんな事をするのは考えられない。
そこまで考えて、渋谷はポケットに入れたままのメモを思いだした。そういえば、浴室のシャワーを見るようにとメモを受け取っていたのだ。
濡れたコートをダイニングの椅子へとかけて、すぐに浴室へ行ってみる。扉を開いて、乾いたタイルに足を乗せる。昨夜使用した後の残り香なのか、浴室はとてもいい匂いがした。
大きなジャグジーは疲れた身体を揉みほぐすのには最適で、この家で気に入っている場所の一つである。
一緒に玖珂と風呂へ入る日も週に数回はあるが、そんな日は決まって長風呂になってしまう。別にあがってから話せばいいのに、何だか風呂場だといつもより色々話したくなってしまうのだ。
メモの通りシャワーのノズルにまた何かのメモが貼ってある。
先程のメモと同じ玖珂の字で、そのメモには……。
『おかえり、祐一朗。次は、俺の自室の机の上を見て欲しい』
と書かれていた。何かのゲームのつもりなのかもしれない。
渋谷はまるで子供の頃にした宝探しゲームをしている気分で、思わず苦笑した。玖珂は十分大人の男だが、こういう遊び心も持ち合わせている。渋谷自身が考えた事も無いような事をたまにしてきて、驚かされたのは一度や二度ではない。
一度居間へ戻り、買ってきたケーキを冷蔵庫へしまってから玖珂の自室へと向かう。
普段あまり入らない場所ではあるが、指定されている場所がそこなのだから仕方がない。小さく「お邪魔します」と呟いて玖珂の自室へ入る。
綺麗に片付けられた部屋は主がいなくても、微かに玖珂のいつもつけている香水の香りがする。仕事で使うパソコンが設置されているデスクの下では機器が不規則に点滅していた。
壁に備え付けられた天井まであるオーダーメイドのコレクションラックに並べてあるのは年代物の酒だった。端の方には学生時代のトロフィーなども飾られている。あまりじろじろ見るのも失礼なので、渋谷は棚から視線を外すと玖珂の指定するデスクの前へ行った。
机の上には、前に見せて貰った事のある玖珂の家族の写真。
その横に、また同じメモが置いてあった。
『覚えているかな? 君からの最初のプレゼントはこの名刺だったね。今年のクリスマスも祐一朗と過ごせて嬉しいよ。さて、最後の場所はここには書かない。祐一朗自身で探してくれ。ヒント:ある約束をした場所』
メモと一緒に置かれていたのは、出会った日に玖珂に渡した自分の名刺だった。何年も経っているので、角が少し潰れている。そういえば、名刺を玖珂に渡したのはこの一回きりだ。大切に持っていてくれたことに嬉しくなる。
渋谷はそれを手に取って、当時を思い出していた。
夏の暑い日、まだ名前すら知らなかった玖珂に助けられてこのマンションへ初めて来たのだ。その原因は苦い想い出でしかないけれど、あの日玖珂と出会わなければ今の自分はいない。
どこかで誰かに心を開くわけでもなく、仕事も辞めていただろうし、新しい職場でひたすら職務だけをこなす何の楽しみもない人生を送っていただろうと想像できる。あの頃から、玖珂はずっと変わらず自分の憧れで、大切な人で……。
あの日は、まさか将来この家に玖珂と住むなんて思ってもいなかった。
「玖珂さん……」
冬の日が落ちるのは早い。
先程まではかろうじて夕暮れといった感じだったが、もう外は真っ暗だった。
渋谷はメモだけを持つと、居間へ戻り窓際へと歩み寄った。
小雪はいつのまにかしっかりとした雪になっており、地面は濡れているだけだが人が立ち入らないビルの屋上などはうっすらと白くなりはじめている。外灯の灯りの下だけ真っ白な雪が舞っているのが見える。外は相当冷え込んでいそうだ。
冷たいガラスに手を突いて、渋谷は遠くを見渡した。
徐々に雪景色へと変貌するその景色を見ていると、急に玖珂が今傍にいないことが寂しく感じた。
一体どこへ行ってしまったのだろう。
携帯を取りだして一度玖珂へと連絡してみたが電源をいれていないようだ。
――最後の場所……。
この自宅の中でという意味だろう。渋谷はスーツを脱ぐのも忘れたままキッチンを見渡し、その後エプロンの入っているクローゼットをあけ、居間のオーディオが置かれている棚を探す。だけど、メモは見つからなかった。
――どうしよう……。約束をした場所って書いてあったな……。
立ち尽くしたまま考えを巡らせていると、自分がここへ越してきた日に玖珂とした会話がふっと浮かんだ。
「祐一朗。お互い時間が合わないことが多いと思うが、一つだけ約束するよ」
「約束……、ですか?」
「ああ。どんなに遅くなっても、必ず祐一朗が目が覚めた朝。俺は君の隣にいる」
「……玖珂さん」
前に自分が「目覚めた時、玖珂さんが傍にいると凄く嬉しいんです」と言ったのを覚えていてくれたのだ。一緒に暮らし初めて一年も経っていないけれど、玖珂は、言葉通り渋谷が目を覚ます朝には必ず隣にいてくれた。仕事が忙しくて持ち帰ってきていたとしても、朝には約束を守ってくれていた。
――会いたい……。
今すぐ玖珂に会いたくて堪らなくなる。
渋谷は寝室へと足を向けた。玖珂が約束してくれた幸せの形。どんなに疲れていても、温かい玖珂の隣で目を閉じれば幸せで胸が一杯になる。
世界で一番安心出来る、その場所へ……。
寝室のドアはきっちり閉まっている。
ドアを開くと、正解を表すように寝室には最初から灯りが点いていた。閉められていないカーテンの向こうには眩い程の夜景。
そして、綺麗にベッドメイキングされたクイーンサイズのベッドの上には、最後のメモ。
渋谷は急いでベッドの側へ寄った。
『メリークリスマス。祐一朗、愛しているよ』
メモと一緒に置かれている小さな小箱、互いにクリスマスプレゼントを用意するのはやめようと決めたのに、どうやら用意していたらしい。
真に受けて何も用意しなかった事に少し慌てていると、再び胸元の携帯が着信した。相手は勿論玖珂である。渋谷は、玖珂が話し出す前に口を開いた。
「玖珂さん? 今、どこにいるんですか?」
『家の近くだよ。もうプレゼントは見つけてくれたかな?』
「それは……。はい……。でも、プレゼントはなしって約束したじゃないですか」
『俺も祐一朗から貰ったからね。それのお返しだよ』
「……え?」
『さてと……。それじゃ、俺も帰るかな。駅前の喫茶店にいたんだが、そろそろ君が恋しくなってきた所だ』
玖珂はそういって笑うと、「話の続きは帰ってから」と言い残して電話を切った。駅前にいるのなら、そうかからずに戻ってくるだろう。渋谷はプレゼントの箱をそっと開けてみる。中には腕時計が入っていた。この前料理をしている時に水の中に落としてしまい壊れたままなのだ。
修理に出すほどの高価な物でも無かったので、そのうち買い換えようと思いつつ今になってしまっている。
「……!?」
取り出してよく見て見ると、プレゼントの時計は玖珂の愛用している物と同じブレゲのものだった。ブレゲの時計は流行に流されないシンプルな物だが、シークレットサインとして刻まれた繊細な装飾や、風格のあるどっしりとした重厚感が玖珂にとてもよく似合っていた。自分には不似合いなほど高級な物だ。
腕にはめてみると、しっかりと馴染み、玖珂が選んだ物を身につけているという実感がわいてくる。嬉しいけれど、こんなに高級な物を貰うのはさすがに気が引ける。何せ、自分は本当に何も用意していないのだから。
暫く自分の腕をマジマジと見ていると、玄関が開く音が聞こえた。
――玖珂さん!
渋谷は立ち上がると勢いよく寝室のドアをあけた。
「おかえりなさい」
「ただいま。外をもう見たか? すっかり雪景色だな」
「さっき、ちらっと見ましたよ。かなり積もるかもしれないですね」
「そうだね。ホワイトクリスマスとは、神様も洒落た演出をしてくれるね」
玖珂はそう言って笑うと、自分が贈ったプレゼントを渋谷が腕に付けていることに気付き嬉しそうに目を細めた。
「早速してくれたのか? よく似合っているよ。気に入ってくれたかい?」
「それは、勿論ですけど。俺には不相応な気がして。……こんな高級な時計、貰うわけには……」
「何を言っているんだ。俺はそれ以上の物を先に貰っているんだから、気にすることはないよ」
「あの……俺、何も用意していないんです……。玖珂さんはさっきも俺に貰ったって言ってたけど、なんのことですか? 俺も何か用意すれば良かった……」
「祐一朗に送った物と同じ物を俺も貰ったぞ?」
「え?」
玖珂はそういってコートを脱ぐと、「ああ、寒かった」といって悪戯な笑みをこぼした。
「まずは一服してもいいかな? 喫茶店が全席禁煙だったんだ。喫煙者は本当に肩身が狭いな」
参ったとでもいうように眉を寄せる玖珂がおかしくて、渋谷も釣られて笑う。居間のソファに並んで腰を下ろす。玖珂の言うとおり、外はいつのまにか地面まで真っ白になっていた。
つい先程はそこまででもなかったのに。並べておいてある自分の煙草を取り出して、渋谷も隣で一緒に紫煙をくゆらせた。
「ちゃんと説明してくれないと受け取れないですよ。この時計、玖珂さんのしている物と同じものですよね」
困った表情を浮かべる渋谷を宥めるように、玖珂は煙草を指で挟んで渋谷の眉間に寄った皺に人差し指をあてた。
「わかったわかった。ちゃんと今説明するから、返すなんて言わないでくれよ?」
玖珂が笑って煙草を再び咥える。ゆっくりと肺の奥深くにいれた煙を味わってから雪で濡れた髪を手で整え、渋谷の方へ振り向いた。
「俺が残したメモのゲーム。結構大変だったんじゃないか?」
「いえ……。少し最後は迷いましたが。……楽しかったですよ。玖珂さんの残したメモを辿ってる間、色々な事を思い出して、ずっと玖珂さんの事を考えていました」
「そうか、それは嬉しいね」
「浴室で最初にジャグジーに驚いた事とか、出会った日に渡した名刺とか、あの日から今まで貴方と過ごした時間を思うと懐かしくて……。一緒に住むことになって……玖珂さんがしてくれた約束を思いだして、やっと最後の場所がわかったんです」
「なるほど、流石に勘がいいね」
玖珂は吸い終わった煙草を灰皿でもみ消すと、自身の顔の前で長い指を組んだ。
「Gifts of time and love are surely the basic ingredients of a truly merry Christmas.」
突然流暢な英語で話され、訳すのに頭が回らない。何とか意味を汲み取ると渋谷は確認するように呟いた。
「時と愛のプレゼントは、クリスマスの真の材料……って事ですか?」
「正解だ。アメリカの作家ペグ・ブラッケンの言葉だよ。時間と愛の贈り物は、楽しいクリスマスの基本、って意味だ」
「そうなんですね。初めて知りました」
「祐一朗は、メモを辿って探している間、ずっと俺の事を考えてくれていたって、言っただろう?」
「……はい」
「その時間と気持ちが、祐一朗からのプレゼントだよ」
「……それは」
「俺が贈ったのはただの『物』でしかない。だけど、祐一朗がくれたのは、君の人生の数時間だ。形は無いけど、俺にとってはどんな物より価値がある」
「…………玖珂さん」
「それに、俺は欲張りだからね。その時計を贈った意味はもうひとつある。身につけている間、時計を見れば俺を思い出すだろう? その時間も、俺が独り占めって訳だ」
玖珂が柔らかに目を細めて自分を見つめているのに気づき、渋谷は何度か瞬きをするとはめたままの腕時計に視線を落とした。細い秒針が、二人の間を流れる時間を細かく刻み続ける。
形のない贈り物を貰ったと、玖珂は言うけれど……。
「……俺の時間なんて」
「ん?」
「俺の時間でいいなら、何年分でも、玖珂さんにあげます。仕事以外では、俺、貴方のことばかり考えているから……。全部、独占して下さい」
「参ったな。……時計を贈ったのは、間違いだったかもしれないな」
玖珂が困ったように眉を寄せ苦笑する。
「……え?」
「だってそうだろう? そんな可愛い事を言ってくれる君の傍に、俺がいない間もいられるんだからね。時計に嫉妬するのは、多分人生で初めてだよ」
いつものように冗談交じりで返されたのは、この上なく甘い言葉で。ケーキ屋で感じた幸福感にも似ている。心がふんわりと包まれたような、優しい一時。それを噛みしめて、渋谷は笑みを浮かべた。
「……一生大切に使います。有難うございます」
「時計だけじゃなく、俺の事も、一生大切にしてくれるかな?」
「当たり前じゃないですか」
「安心したよ」
玖珂と顔を見合わせて笑う。
渋谷は時計の上に、大切そうに逆の掌を重ね目を閉じる。まるで婚約記念の贈り物を貰ったような気分である。時計は勿論、玖珂と一生共に過ごせるなんて、クリスマスだけの夢でも見ているようだ。
それが現実である事は、その熱でわかる。
目を閉じた渋谷の顎を軽く指先で持ち上げると、重なってくる玖珂の唇。角度を変えながら続く濃厚な口付けにあっという間に翻弄される。
「……んっ、珂さ、」
身体を触られているわけでもないのに、全身の力が抜けていく。質のいいソファの背もたれに身をもたれ掛からせれば、玖珂は口付けたまま渋谷の手に指を絡めて優しく握った。
口付けが解かれても、すぐには動けないほどの脱力感。
暫くして目を開けると、玖珂が間近で自分を見つめていた。色気を滲ませた玖珂の瞳に映り込んでいるのは自分自身。
「今年のクリスマスも君と過ごせるなんて、俺は幸せ者だな」
「……俺もですよ。俺も……、世界一の幸せ者です」
「おっと、大きく出たね」
優しい玖珂の隣にいると、今まで感じられなかった些細な事まで幸せを感じるようになる。そして、自分だけではなく、玖珂にもそう感じて欲しいと願ってしまう。恋をするという本当の意味は、そういう事なのかもしれない。
「そうだ……。俺、ケーキ買ってきたんですよ。なるべく甘くなさそうな物を選んだので玖珂さんも食べられるかも」
「そうなのか? どんなケーキかな。ちょっと見てみようか」
「ええ。冷蔵庫にいれてあるので」
二人でキッチンへ向かい包装したままの大きな箱を取り出して置く。真っ赤なリボンをといて箱から出すと、丁寧に持ち帰ったはずなのに、少しだけ柊が傾いていた。
玖珂が指先を伸ばしてそれをそっと立て直す。
「美味しそうだね。じゃぁ、帰ってきてから一緒に食べようか」
「良かったです。玖珂さんが食べられそうで」
「祐一朗が選んでくれたケーキなら、どんなに甘くてもちゃんと食べるぞ?」
渋谷がケーキを箱にしまう際触れた指先にビターチョコのクリームがつく。玖珂は渋谷の指を手に取るとクリームごと口に含んだ。
「玖珂さん!?」
指先にあたる玖珂の舌先。
「本当だ。そんなに甘くないね」
「き、急にこういう事をされると困ります……」
「どうして?」
「どうしてでも、です」
あまりからかうと祐一朗が怒るから、今日はこれ以上はやめておくよと玖珂は笑っていた。
今夜の夕食はフレンチのレストランを予約している。時計を見ると、そろそろ準備をして出掛けた方がいい時間になっていた。まだクリスマスの夜は始まったばかりだというのに、色々な事がありすぎて帰宅したスーツのままだった事に気付く。
「そろそろ出ますか? 俺、着替えてこなくちゃ」
「もうそんな時間か。そうだね、俺も準備するとしようか」
再びケーキを冷蔵庫に戻し、出掛ける準備をするために互いの自室へ戻る。有名なレストランなので予約が取れただけでも凄いのに、取った席はどうやら個室らしい。渋谷はクローゼットから一番仕立てのいいスーツを取りだして着替える。玖珂の行きつけのテイラーに一緒に行き仕立てたものなので、さっきまで着ていた吊るしのスーツと比べると身体に沿うようにフィットしていて着心地が違う。
腕時計にも、これなら合いそうな気がする。
大して変化しないが一応髪も整えておく。全ての準備を終えて自室を出ると、玖珂はもう着替え終えて廊下で待っていた。先程までと雰囲気が全然違う。ラフな格好の玖珂もいいが、やはりスーツ姿は玖珂の魅力を一番引き出すと思う。長めの黒いコートの袖から覗く、ブラックレザーの手袋。
タイトに固めたサイドの髪のせいで端正な横顔がより際立っており、渋谷はその横顔に見惚れていた。
「お待たせしました。……、あの」
「ん? どうかしたか?」
「いえ……、その、……。凄く、かっこいいです」
「そう? 有難う。祐一朗もそのスーツがよく似合っているよ」
「そ、そうかな。だといいんですけど……」
渋谷は照れくさそうに視線を逸らしコートを羽織る。寒そうなので持ってきたマフラーをその上から巻こうとすると、玖珂が腕を伸ばして代わりに巻いてくれた。
「それじゃ、行こうか」
「はい」
傘を持ち玄関を開けて外に出ると、見事に真っ白な雪景色が眼下に広がっていた。マンションを出るまでの束の間、玖珂と手を繋ぐ。
レストランのある新宿は本来なら電車で一駅離れているが、歩いてもそうかからない。ゆっくりと雪を踏みしめながら二人で歩く。
「東京でこんなに雪が降ることって少ないから、明日はきっとあちこちに雪だるまがありそうですよね」
「子供達が作るって意味かな?」
「ええ、そうです。玖珂さんも、子供の頃作った事ありますよね?」
玖珂が歩きながら側にあったガードレールの雪を手で掬う。
「勿論あるよ、弟と一緒にね。溶けるのが嫌だって澪が泣くから、小さな雪だるまを作ってやって冷凍室に沢山入れていたら、母親に怒られてね」
渋谷がそれを聞いて笑う。
「それは怒られますよ。冷凍庫はいいアイデアだと思いますけど、俺はやったことがないですね」
「祐一朗も、妹さんに作ってあげてたのか?」
「そうですね、小さい頃は。うちの妹は大きい雪だるまが好きで、妹と同じぐらいの大きさを作るのって大変だったんですよ。相当時間がかかっちゃって……。次の日風邪を引いて寝込んだことならあります」
「それはまた……。お互い苦労してるね」
「ホントに」
互いに離れた場所にいる兄弟を思いだし苦笑する。
玖珂が自分の傘を外側に傾けて渋谷との距離を詰める。片手の手袋を外して渋谷の手を握ると、前を向いたまま口を開く。
「傘も差しているし、誰も気付かないよ」
「…………そうですね」
すっかり冷たくなっている渋谷の手に、玖珂の温かさが伝わってくる。その大きな手を、渋谷もぎゅっと握り返し、照れくささに俯く。
マフラーに埋もれた口から吐く息が、眼鏡を時々曇らせて視界を白く染めた。美味しいディナーも楽しみだけれど、その帰りに、また手を繋ぐ事に期待している自分がいる。
――帰りは、自分から繋いでみよう。
そうしたら、玖珂は喜んでくれるだろうか。渋谷は横に並ぶ玖珂の横顔を見て、幸せそうに笑みを浮かべた。クリスマスの夜は、ほんの少しだけ魔法がかかるのかもしれない。
街ゆく人々にも、そして、勿論
自分にも……。
Merry Christmas to you.
しかし、この季節ばかりは自身が街を彩る事にどこか得意げな様子がうかがえる。幹から伸びた、葉を落とした枝先で点滅する、スノーフレークを象ったイルミネーション。夜になれば並んだ街路樹は大通りごと全てを幻想的な世界へと変えてくれる。
そんなクリスマス当日、渋谷はトレンチコートの襟から入り込む冷たい風にほんの少し身体を震わせ白い息を吐いた。昨日までは暖かい日が続いていたが、今日は急に気温が下がっているようだ。
そろそろマフラーも出した方がいいかもしれない。
冷たくなった指先に一度ハァと息を吹きかけて擦り、通りの店の前で足を止める。
玖珂は甘い物があまり好きでは無い。それは知っているけれど、クリスマスにケーキがないのは少し寂しいのではないか。そんな事を考えながら、渋谷は帰宅途中にあるケーキ屋のショーケースに並ぶクリスマスケーキを眺めていた。
空を駆けるサンタを乗せたソリが、窓硝子に綺麗に描かれている。こんな小さなケーキ屋でさえクリスマス一色である。
土曜日の午後、天気は生憎曇り空で天気予報では雪が降るかも知れないと言っていたのを思い出す。
――……。
空を見上げるとその天気予報はあたりそうだなと思えた。
雨ではガッカリする恋人達も多いかも知れないが、雪となれば話は別だ。うっすらと街を覆う真っ白な雪は、街のあちこちに飾られたイルミネーションの光を柔らかく包む。交通機関が麻痺するほどの積雪は望まれていないだろうが、都心でのホワイトクリスマスを待ち望む声は少なくない。
――やはり、小さいのを買って帰ろうかな……。
もし玖珂が食べなければ、自分が明日も食べれば終わるようなサイズなら問題ないだろう。渋谷がケーキ屋のドアに手を掛けた瞬間、ポケットで携帯が振動した。
一度手を止め、少し道の脇へ寄って携帯を取り出す。画面を見ると玖珂からメッセージが届いていた。先程最寄り駅についてすぐ、『今から帰ります』と打ったので、それへの返信かもしれない。
クリスマスの土曜日でもある今日、本当は休日の自分がどうして仕事帰りなのか。
それには理由があった。
取引先の都合で、どうしても今日の午前中に現地を視察しなくてはいけなくなったからだ。急遽その為だけに朝から出社。昼に現地を視察してから一度社へ戻り、企画の書類を書き直してから退社した頃にはすっかり夕方近くなっていた。
本当は昼過ぎに出掛け、その後、予約している店のディナーに向かいがてら、玖珂と二人でイルミネーションを見に行く予定だったのだ。
仕事だから仕方がないとはいえ、急な予定変更に一番ガッカリしているのは多分自分で……。渋谷は、昨夜の事を思いだして軽く溜め息をついた。
明け方近くなって帰宅した玖珂は、一通り寝る準備をした後いつものように渋谷を起こさぬようにベッドへそっと入ってきて腕を回す。幾度か渋谷の身体を確認するように撫でて、そのまま眠りにつく。昨夜もそうだった。
渋谷は、うとうとしながらもベッドが軋む音で目を覚まし、今日の予定変更を伝えようと振り向いた。起きていたことに驚いた様子の玖珂は、一度手を止め、すまなそうに渋谷と視線を合わせた。
「起きていたのか? それとも、起こしてしまったかな」
「いえ、伝えたい事があって……。起きてようと思ったんですけど、ちょっとうとうとしちゃってました。おかえりなさい」
「ああ、ただいま。伝えたい事って? なにかあったのか?」
玖珂は優しい笑みを浮かべて渋谷の額へと軽く口付ける。それがくすぐったくて、渋谷は恥ずかしそうに肩を竦めた。玖珂の方へ身体を向け残念そうに口を開く。
「明日……あ、いやもう今日ですね……。俺仕事が入っちゃって……。夕方には帰れるので夕食は間に合うと思うんですけど……」
「そうなのか、大変だな。わかったよ。じゃぁ、大人しく待ってるとしよう」
「休みだって言ってたのに、すみません。なるべく早く帰ります」
そう言いながら申し訳なさに視線を落とすと、玖珂は囁くように「気にしなくていい。気をつけて行っておいで」と渋谷の頭を撫でた。
「はい」
「それじゃぁ、早く寝ないといけないね」
「そうですね……」
一緒に暮らし始めて数ヶ月、別々に暮らしていた頃より格段に玖珂といる時間が増えた。しかし、互いの生活リズムが変わったわけではない。
夕方に出て行き明け方近く、どんなに早くても日付が変わった後に帰宅する玖珂と、普通の会社員である自分との時間は中々合わず、互いに数日寝顔しか見ていないなんて日もざらだった。
それでもこうして、話したい時に側にいてくれるというだけで、一緒に暮らしていて良かったと思う。
「玖珂さん」
「んー? どうした?」
「まだ少し、髪が濡れてる……」
渋谷はベッドからごそごそと手を出すと、向かい合う玖珂の額へ落ちる毛先を指でつまんで笑みを浮かべた。
「そう? ちゃんと乾かしたつもりだったんだけどね」
「風邪、引かないで下さいね」
「大丈夫だよ」
もう少しだけ玖珂の声が聞いていたくて、寝起きの回らない頭で他愛もない言葉を探してしまう。あと数時間で自分は起きなければいけないのに。
「あの……、クリスマスプレゼントの件……本当に今年はいいんですか?」
「ああ、そう約束しただろう? 祐一朗と一緒にいられるだけで十分だよ」
「そうですか……。わかりました」
「ほら。もう寝た方がいいんじゃないか? 後少しで、起きる時間だろう」
「……はい」
渋谷を気遣って話を切ると、玖珂は「おいで」と言って自分の胸に渋谷をそっと引き寄せると静かに目を閉じた。少しして聞こえてくる玖珂の寝息に誘われ、安心したように渋谷も眠りに落ちた。
その二時間後に起床すると、玖珂は当然眠っていて、起こさぬようそっとベッドから出て支度をした。
渋谷は自宅にいるはずの玖珂からのメッセージ画面を開く。帰るときに何か買ってきて欲しいというメッセージなのだろうか。
画面には一言だけ書かれている。
『お疲れ様。帰宅する時、ポストを見てきてくれるかな』
すぐに『わかりました』と返信したが、それは既読になった物の返信がくることは無かった。少し不思議に思いつつも携帯をしまうと、渋谷はケーキ屋のドアを開いた。
入り口に付けられている鈴が軽い音を鳴らし、店員がいらっしゃいませと笑顔を向けてくる。
「私、このトナカイさんが乗ってるのがいい!」
「ええ? こんなに大きいの食べきれるの?」
「いいじゃないかママ、クリスマスなんだし、これがいいって言っているんだから」
耳に飛び込んでくる三人家族の会話。
先に店内にいた家族連れは、暫く話し合った結果、はしゃいでいる娘が欲しがった大きなホールのケーキを選んだようだ。会計を済ませる間、渋谷は腰を屈めて少し後ろから色とりどりのケーキを見つつどれにしようか迷っていた。
ケーキ屋の奥から漂ってくるのは焼き菓子の焼ける甘い香り。それだけで、幸せな気持ちになる。そんな自分も、目の前の子供と同じく随分とはしゃいでいるように感じて、渋谷は一人恥ずかしくなって頬を掻いた。
家族連れが店を後にし店員と渋谷だけになると、店内にかかっているクリスマスソングがやけに大きく聞こえた。
「お待たせしました。お決まりでしょうか?」
「ああ。……ええと、この中で甘さが控えめの物はどれになりますか?」
「うーん。そうですね……。こちらの二点は、ビターチョコレートを使用しているので他の物よりは甘さが控えめになっています。中のラズベリークリームに少しアルコールが入っていますが、大丈夫なようでしたらお勧めです。男性の方にも人気ですよ」
「なるほど」
店員がさした二点のうち一点はブッシュ・ド・ノエルで、もう一点はシンプルな見た目の大人っぽいホールケーキだった。サンタが乗っているような可愛いクリスマスケーキではないが、小さな柊とMerry Christmasのプレートが飾り付けてある。丁度大きさもそんなに大きくはないようだ。
「じゃぁ、このホールのケーキをいただけますか」
「かしこまりました。蝋燭もお付けできますがどうされますか?」
渋谷は一瞬迷った後「蝋燭は……、結構です」と断った。誕生日でもないし、何だか蝋燭をお願いするのが気恥ずかしかったからだ。
一度奥へとケーキを持っていき、綺麗な箱に入れて戻ってきた店員は、器用な手つきで真っ赤なリボンを包装紙の上へと飾り、レジ向こうから渋谷へと手渡した。
ケーキをいれる紙袋もクリスマス仕様で、サンタの格好をした雪だるまが描かれている。思わず「可愛いですね」と率直な感想を呟くと、店員は「今日までの特別仕様です」と言って笑っていた。
「有難うございました。またのご来店をお待ちしております」
軽く会釈をし、受け取ったケーキを手に帰路へ着く。
アルコールが入っているビターなケーキなら玖珂も食べるかもしれない。
一人暮らしだった頃はホールのケーキなど買った事も無かったが、こうしてホールのケーキを買うというのは思いのほか楽しい物だなと感じていた。
ずっしりとした重さ、それを手に持って自宅へ帰るというのは、待ってくれている人がいるからこそ出来る事なのだ。
「……あれ? ……雨?」
渋谷の着ているベージュのトレンチコートに数カ所雨粒がおちて色を変えている。空を見上げてみると、それは雨粒ではなく降り出した小雪だった。地上におりてアスファルトに辿り着く頃にはもう水滴になっているような霙まじりの雪だ。
傘を持っていないので、ケーキが濡れぬよう少しだけ足を速める。
自宅マンションへ着くと、肩の辺りはあんな小雪でもかなり濡れてしまっていた。軽く払ってからエントランスのポストへ向かう。
基本的に郵便物は玖珂がとってくるので、渋谷がポストを見る事は滅多に無いのだ。ダイヤルを回してロックを解除すると、中にはメモのような紙が一枚だけ入っていた。
――何だろう……。
半分開いている状態なので、中の文字が見える。
渋谷はエレベーター前で足を止めてメモを片手で開いた。
『家に入ったら、浴室のシャワーを見ること』
――???
字は玖珂の字である。全く意味がわからないが、とりあえずそのメモをポケットへいれてエレベーターへ乗り込んだ。直通で最上階へ上がるそのエレベーターは専用なだけあり、人と鉢合わせることはまずない。未だにそんな高級マンションが自宅だなんて信じられない思いである。
一人暮らしをしていた一般的なマンションとは何もかもが違う。
すぐに辿り着いた玄関の鍵を開けて中に入り、後ろ手で鍵を施錠する。日も落ちているので真っ直ぐ伸びる廊下は真っ暗だった。反応して点灯するセンサーを足に纏って進む。
「ただいま、遅くなりました」
どこかにいるだろう玖珂へと声をかけ、コートを脱いで手に持つとひとまず居間へと向かう。硝子のドアをそっとあけてみると居間は暗くて、渋谷が入ってきたことでやっと照明がパッとついた。
「玖珂さん……?」
声をかけてキッチンの方も覗いてみたが、玖珂の姿はない。少し遅くなってしまったから、買い物にでも行ってしまったのか。一瞬そう思ったが、何も連絡なしにそんな事をするのは考えられない。
そこまで考えて、渋谷はポケットに入れたままのメモを思いだした。そういえば、浴室のシャワーを見るようにとメモを受け取っていたのだ。
濡れたコートをダイニングの椅子へとかけて、すぐに浴室へ行ってみる。扉を開いて、乾いたタイルに足を乗せる。昨夜使用した後の残り香なのか、浴室はとてもいい匂いがした。
大きなジャグジーは疲れた身体を揉みほぐすのには最適で、この家で気に入っている場所の一つである。
一緒に玖珂と風呂へ入る日も週に数回はあるが、そんな日は決まって長風呂になってしまう。別にあがってから話せばいいのに、何だか風呂場だといつもより色々話したくなってしまうのだ。
メモの通りシャワーのノズルにまた何かのメモが貼ってある。
先程のメモと同じ玖珂の字で、そのメモには……。
『おかえり、祐一朗。次は、俺の自室の机の上を見て欲しい』
と書かれていた。何かのゲームのつもりなのかもしれない。
渋谷はまるで子供の頃にした宝探しゲームをしている気分で、思わず苦笑した。玖珂は十分大人の男だが、こういう遊び心も持ち合わせている。渋谷自身が考えた事も無いような事をたまにしてきて、驚かされたのは一度や二度ではない。
一度居間へ戻り、買ってきたケーキを冷蔵庫へしまってから玖珂の自室へと向かう。
普段あまり入らない場所ではあるが、指定されている場所がそこなのだから仕方がない。小さく「お邪魔します」と呟いて玖珂の自室へ入る。
綺麗に片付けられた部屋は主がいなくても、微かに玖珂のいつもつけている香水の香りがする。仕事で使うパソコンが設置されているデスクの下では機器が不規則に点滅していた。
壁に備え付けられた天井まであるオーダーメイドのコレクションラックに並べてあるのは年代物の酒だった。端の方には学生時代のトロフィーなども飾られている。あまりじろじろ見るのも失礼なので、渋谷は棚から視線を外すと玖珂の指定するデスクの前へ行った。
机の上には、前に見せて貰った事のある玖珂の家族の写真。
その横に、また同じメモが置いてあった。
『覚えているかな? 君からの最初のプレゼントはこの名刺だったね。今年のクリスマスも祐一朗と過ごせて嬉しいよ。さて、最後の場所はここには書かない。祐一朗自身で探してくれ。ヒント:ある約束をした場所』
メモと一緒に置かれていたのは、出会った日に玖珂に渡した自分の名刺だった。何年も経っているので、角が少し潰れている。そういえば、名刺を玖珂に渡したのはこの一回きりだ。大切に持っていてくれたことに嬉しくなる。
渋谷はそれを手に取って、当時を思い出していた。
夏の暑い日、まだ名前すら知らなかった玖珂に助けられてこのマンションへ初めて来たのだ。その原因は苦い想い出でしかないけれど、あの日玖珂と出会わなければ今の自分はいない。
どこかで誰かに心を開くわけでもなく、仕事も辞めていただろうし、新しい職場でひたすら職務だけをこなす何の楽しみもない人生を送っていただろうと想像できる。あの頃から、玖珂はずっと変わらず自分の憧れで、大切な人で……。
あの日は、まさか将来この家に玖珂と住むなんて思ってもいなかった。
「玖珂さん……」
冬の日が落ちるのは早い。
先程まではかろうじて夕暮れといった感じだったが、もう外は真っ暗だった。
渋谷はメモだけを持つと、居間へ戻り窓際へと歩み寄った。
小雪はいつのまにかしっかりとした雪になっており、地面は濡れているだけだが人が立ち入らないビルの屋上などはうっすらと白くなりはじめている。外灯の灯りの下だけ真っ白な雪が舞っているのが見える。外は相当冷え込んでいそうだ。
冷たいガラスに手を突いて、渋谷は遠くを見渡した。
徐々に雪景色へと変貌するその景色を見ていると、急に玖珂が今傍にいないことが寂しく感じた。
一体どこへ行ってしまったのだろう。
携帯を取りだして一度玖珂へと連絡してみたが電源をいれていないようだ。
――最後の場所……。
この自宅の中でという意味だろう。渋谷はスーツを脱ぐのも忘れたままキッチンを見渡し、その後エプロンの入っているクローゼットをあけ、居間のオーディオが置かれている棚を探す。だけど、メモは見つからなかった。
――どうしよう……。約束をした場所って書いてあったな……。
立ち尽くしたまま考えを巡らせていると、自分がここへ越してきた日に玖珂とした会話がふっと浮かんだ。
「祐一朗。お互い時間が合わないことが多いと思うが、一つだけ約束するよ」
「約束……、ですか?」
「ああ。どんなに遅くなっても、必ず祐一朗が目が覚めた朝。俺は君の隣にいる」
「……玖珂さん」
前に自分が「目覚めた時、玖珂さんが傍にいると凄く嬉しいんです」と言ったのを覚えていてくれたのだ。一緒に暮らし初めて一年も経っていないけれど、玖珂は、言葉通り渋谷が目を覚ます朝には必ず隣にいてくれた。仕事が忙しくて持ち帰ってきていたとしても、朝には約束を守ってくれていた。
――会いたい……。
今すぐ玖珂に会いたくて堪らなくなる。
渋谷は寝室へと足を向けた。玖珂が約束してくれた幸せの形。どんなに疲れていても、温かい玖珂の隣で目を閉じれば幸せで胸が一杯になる。
世界で一番安心出来る、その場所へ……。
寝室のドアはきっちり閉まっている。
ドアを開くと、正解を表すように寝室には最初から灯りが点いていた。閉められていないカーテンの向こうには眩い程の夜景。
そして、綺麗にベッドメイキングされたクイーンサイズのベッドの上には、最後のメモ。
渋谷は急いでベッドの側へ寄った。
『メリークリスマス。祐一朗、愛しているよ』
メモと一緒に置かれている小さな小箱、互いにクリスマスプレゼントを用意するのはやめようと決めたのに、どうやら用意していたらしい。
真に受けて何も用意しなかった事に少し慌てていると、再び胸元の携帯が着信した。相手は勿論玖珂である。渋谷は、玖珂が話し出す前に口を開いた。
「玖珂さん? 今、どこにいるんですか?」
『家の近くだよ。もうプレゼントは見つけてくれたかな?』
「それは……。はい……。でも、プレゼントはなしって約束したじゃないですか」
『俺も祐一朗から貰ったからね。それのお返しだよ』
「……え?」
『さてと……。それじゃ、俺も帰るかな。駅前の喫茶店にいたんだが、そろそろ君が恋しくなってきた所だ』
玖珂はそういって笑うと、「話の続きは帰ってから」と言い残して電話を切った。駅前にいるのなら、そうかからずに戻ってくるだろう。渋谷はプレゼントの箱をそっと開けてみる。中には腕時計が入っていた。この前料理をしている時に水の中に落としてしまい壊れたままなのだ。
修理に出すほどの高価な物でも無かったので、そのうち買い換えようと思いつつ今になってしまっている。
「……!?」
取り出してよく見て見ると、プレゼントの時計は玖珂の愛用している物と同じブレゲのものだった。ブレゲの時計は流行に流されないシンプルな物だが、シークレットサインとして刻まれた繊細な装飾や、風格のあるどっしりとした重厚感が玖珂にとてもよく似合っていた。自分には不似合いなほど高級な物だ。
腕にはめてみると、しっかりと馴染み、玖珂が選んだ物を身につけているという実感がわいてくる。嬉しいけれど、こんなに高級な物を貰うのはさすがに気が引ける。何せ、自分は本当に何も用意していないのだから。
暫く自分の腕をマジマジと見ていると、玄関が開く音が聞こえた。
――玖珂さん!
渋谷は立ち上がると勢いよく寝室のドアをあけた。
「おかえりなさい」
「ただいま。外をもう見たか? すっかり雪景色だな」
「さっき、ちらっと見ましたよ。かなり積もるかもしれないですね」
「そうだね。ホワイトクリスマスとは、神様も洒落た演出をしてくれるね」
玖珂はそう言って笑うと、自分が贈ったプレゼントを渋谷が腕に付けていることに気付き嬉しそうに目を細めた。
「早速してくれたのか? よく似合っているよ。気に入ってくれたかい?」
「それは、勿論ですけど。俺には不相応な気がして。……こんな高級な時計、貰うわけには……」
「何を言っているんだ。俺はそれ以上の物を先に貰っているんだから、気にすることはないよ」
「あの……俺、何も用意していないんです……。玖珂さんはさっきも俺に貰ったって言ってたけど、なんのことですか? 俺も何か用意すれば良かった……」
「祐一朗に送った物と同じ物を俺も貰ったぞ?」
「え?」
玖珂はそういってコートを脱ぐと、「ああ、寒かった」といって悪戯な笑みをこぼした。
「まずは一服してもいいかな? 喫茶店が全席禁煙だったんだ。喫煙者は本当に肩身が狭いな」
参ったとでもいうように眉を寄せる玖珂がおかしくて、渋谷も釣られて笑う。居間のソファに並んで腰を下ろす。玖珂の言うとおり、外はいつのまにか地面まで真っ白になっていた。
つい先程はそこまででもなかったのに。並べておいてある自分の煙草を取り出して、渋谷も隣で一緒に紫煙をくゆらせた。
「ちゃんと説明してくれないと受け取れないですよ。この時計、玖珂さんのしている物と同じものですよね」
困った表情を浮かべる渋谷を宥めるように、玖珂は煙草を指で挟んで渋谷の眉間に寄った皺に人差し指をあてた。
「わかったわかった。ちゃんと今説明するから、返すなんて言わないでくれよ?」
玖珂が笑って煙草を再び咥える。ゆっくりと肺の奥深くにいれた煙を味わってから雪で濡れた髪を手で整え、渋谷の方へ振り向いた。
「俺が残したメモのゲーム。結構大変だったんじゃないか?」
「いえ……。少し最後は迷いましたが。……楽しかったですよ。玖珂さんの残したメモを辿ってる間、色々な事を思い出して、ずっと玖珂さんの事を考えていました」
「そうか、それは嬉しいね」
「浴室で最初にジャグジーに驚いた事とか、出会った日に渡した名刺とか、あの日から今まで貴方と過ごした時間を思うと懐かしくて……。一緒に住むことになって……玖珂さんがしてくれた約束を思いだして、やっと最後の場所がわかったんです」
「なるほど、流石に勘がいいね」
玖珂は吸い終わった煙草を灰皿でもみ消すと、自身の顔の前で長い指を組んだ。
「Gifts of time and love are surely the basic ingredients of a truly merry Christmas.」
突然流暢な英語で話され、訳すのに頭が回らない。何とか意味を汲み取ると渋谷は確認するように呟いた。
「時と愛のプレゼントは、クリスマスの真の材料……って事ですか?」
「正解だ。アメリカの作家ペグ・ブラッケンの言葉だよ。時間と愛の贈り物は、楽しいクリスマスの基本、って意味だ」
「そうなんですね。初めて知りました」
「祐一朗は、メモを辿って探している間、ずっと俺の事を考えてくれていたって、言っただろう?」
「……はい」
「その時間と気持ちが、祐一朗からのプレゼントだよ」
「……それは」
「俺が贈ったのはただの『物』でしかない。だけど、祐一朗がくれたのは、君の人生の数時間だ。形は無いけど、俺にとってはどんな物より価値がある」
「…………玖珂さん」
「それに、俺は欲張りだからね。その時計を贈った意味はもうひとつある。身につけている間、時計を見れば俺を思い出すだろう? その時間も、俺が独り占めって訳だ」
玖珂が柔らかに目を細めて自分を見つめているのに気づき、渋谷は何度か瞬きをするとはめたままの腕時計に視線を落とした。細い秒針が、二人の間を流れる時間を細かく刻み続ける。
形のない贈り物を貰ったと、玖珂は言うけれど……。
「……俺の時間なんて」
「ん?」
「俺の時間でいいなら、何年分でも、玖珂さんにあげます。仕事以外では、俺、貴方のことばかり考えているから……。全部、独占して下さい」
「参ったな。……時計を贈ったのは、間違いだったかもしれないな」
玖珂が困ったように眉を寄せ苦笑する。
「……え?」
「だってそうだろう? そんな可愛い事を言ってくれる君の傍に、俺がいない間もいられるんだからね。時計に嫉妬するのは、多分人生で初めてだよ」
いつものように冗談交じりで返されたのは、この上なく甘い言葉で。ケーキ屋で感じた幸福感にも似ている。心がふんわりと包まれたような、優しい一時。それを噛みしめて、渋谷は笑みを浮かべた。
「……一生大切に使います。有難うございます」
「時計だけじゃなく、俺の事も、一生大切にしてくれるかな?」
「当たり前じゃないですか」
「安心したよ」
玖珂と顔を見合わせて笑う。
渋谷は時計の上に、大切そうに逆の掌を重ね目を閉じる。まるで婚約記念の贈り物を貰ったような気分である。時計は勿論、玖珂と一生共に過ごせるなんて、クリスマスだけの夢でも見ているようだ。
それが現実である事は、その熱でわかる。
目を閉じた渋谷の顎を軽く指先で持ち上げると、重なってくる玖珂の唇。角度を変えながら続く濃厚な口付けにあっという間に翻弄される。
「……んっ、珂さ、」
身体を触られているわけでもないのに、全身の力が抜けていく。質のいいソファの背もたれに身をもたれ掛からせれば、玖珂は口付けたまま渋谷の手に指を絡めて優しく握った。
口付けが解かれても、すぐには動けないほどの脱力感。
暫くして目を開けると、玖珂が間近で自分を見つめていた。色気を滲ませた玖珂の瞳に映り込んでいるのは自分自身。
「今年のクリスマスも君と過ごせるなんて、俺は幸せ者だな」
「……俺もですよ。俺も……、世界一の幸せ者です」
「おっと、大きく出たね」
優しい玖珂の隣にいると、今まで感じられなかった些細な事まで幸せを感じるようになる。そして、自分だけではなく、玖珂にもそう感じて欲しいと願ってしまう。恋をするという本当の意味は、そういう事なのかもしれない。
「そうだ……。俺、ケーキ買ってきたんですよ。なるべく甘くなさそうな物を選んだので玖珂さんも食べられるかも」
「そうなのか? どんなケーキかな。ちょっと見てみようか」
「ええ。冷蔵庫にいれてあるので」
二人でキッチンへ向かい包装したままの大きな箱を取り出して置く。真っ赤なリボンをといて箱から出すと、丁寧に持ち帰ったはずなのに、少しだけ柊が傾いていた。
玖珂が指先を伸ばしてそれをそっと立て直す。
「美味しそうだね。じゃぁ、帰ってきてから一緒に食べようか」
「良かったです。玖珂さんが食べられそうで」
「祐一朗が選んでくれたケーキなら、どんなに甘くてもちゃんと食べるぞ?」
渋谷がケーキを箱にしまう際触れた指先にビターチョコのクリームがつく。玖珂は渋谷の指を手に取るとクリームごと口に含んだ。
「玖珂さん!?」
指先にあたる玖珂の舌先。
「本当だ。そんなに甘くないね」
「き、急にこういう事をされると困ります……」
「どうして?」
「どうしてでも、です」
あまりからかうと祐一朗が怒るから、今日はこれ以上はやめておくよと玖珂は笑っていた。
今夜の夕食はフレンチのレストランを予約している。時計を見ると、そろそろ準備をして出掛けた方がいい時間になっていた。まだクリスマスの夜は始まったばかりだというのに、色々な事がありすぎて帰宅したスーツのままだった事に気付く。
「そろそろ出ますか? 俺、着替えてこなくちゃ」
「もうそんな時間か。そうだね、俺も準備するとしようか」
再びケーキを冷蔵庫に戻し、出掛ける準備をするために互いの自室へ戻る。有名なレストランなので予約が取れただけでも凄いのに、取った席はどうやら個室らしい。渋谷はクローゼットから一番仕立てのいいスーツを取りだして着替える。玖珂の行きつけのテイラーに一緒に行き仕立てたものなので、さっきまで着ていた吊るしのスーツと比べると身体に沿うようにフィットしていて着心地が違う。
腕時計にも、これなら合いそうな気がする。
大して変化しないが一応髪も整えておく。全ての準備を終えて自室を出ると、玖珂はもう着替え終えて廊下で待っていた。先程までと雰囲気が全然違う。ラフな格好の玖珂もいいが、やはりスーツ姿は玖珂の魅力を一番引き出すと思う。長めの黒いコートの袖から覗く、ブラックレザーの手袋。
タイトに固めたサイドの髪のせいで端正な横顔がより際立っており、渋谷はその横顔に見惚れていた。
「お待たせしました。……、あの」
「ん? どうかしたか?」
「いえ……、その、……。凄く、かっこいいです」
「そう? 有難う。祐一朗もそのスーツがよく似合っているよ」
「そ、そうかな。だといいんですけど……」
渋谷は照れくさそうに視線を逸らしコートを羽織る。寒そうなので持ってきたマフラーをその上から巻こうとすると、玖珂が腕を伸ばして代わりに巻いてくれた。
「それじゃ、行こうか」
「はい」
傘を持ち玄関を開けて外に出ると、見事に真っ白な雪景色が眼下に広がっていた。マンションを出るまでの束の間、玖珂と手を繋ぐ。
レストランのある新宿は本来なら電車で一駅離れているが、歩いてもそうかからない。ゆっくりと雪を踏みしめながら二人で歩く。
「東京でこんなに雪が降ることって少ないから、明日はきっとあちこちに雪だるまがありそうですよね」
「子供達が作るって意味かな?」
「ええ、そうです。玖珂さんも、子供の頃作った事ありますよね?」
玖珂が歩きながら側にあったガードレールの雪を手で掬う。
「勿論あるよ、弟と一緒にね。溶けるのが嫌だって澪が泣くから、小さな雪だるまを作ってやって冷凍室に沢山入れていたら、母親に怒られてね」
渋谷がそれを聞いて笑う。
「それは怒られますよ。冷凍庫はいいアイデアだと思いますけど、俺はやったことがないですね」
「祐一朗も、妹さんに作ってあげてたのか?」
「そうですね、小さい頃は。うちの妹は大きい雪だるまが好きで、妹と同じぐらいの大きさを作るのって大変だったんですよ。相当時間がかかっちゃって……。次の日風邪を引いて寝込んだことならあります」
「それはまた……。お互い苦労してるね」
「ホントに」
互いに離れた場所にいる兄弟を思いだし苦笑する。
玖珂が自分の傘を外側に傾けて渋谷との距離を詰める。片手の手袋を外して渋谷の手を握ると、前を向いたまま口を開く。
「傘も差しているし、誰も気付かないよ」
「…………そうですね」
すっかり冷たくなっている渋谷の手に、玖珂の温かさが伝わってくる。その大きな手を、渋谷もぎゅっと握り返し、照れくささに俯く。
マフラーに埋もれた口から吐く息が、眼鏡を時々曇らせて視界を白く染めた。美味しいディナーも楽しみだけれど、その帰りに、また手を繋ぐ事に期待している自分がいる。
――帰りは、自分から繋いでみよう。
そうしたら、玖珂は喜んでくれるだろうか。渋谷は横に並ぶ玖珂の横顔を見て、幸せそうに笑みを浮かべた。クリスマスの夜は、ほんの少しだけ魔法がかかるのかもしれない。
街ゆく人々にも、そして、勿論
自分にも……。
Merry Christmas to you.