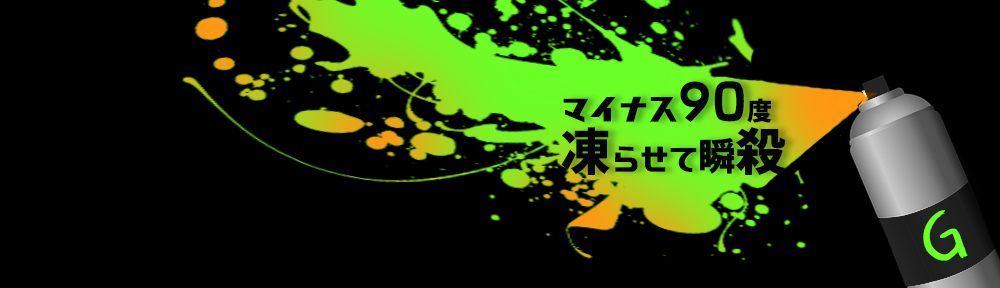
時々男として謎の見栄を張ることがある。
それは、恋人に男らしいところを見せて惚れ直して欲しいというささやかな期待を含んでいることが多い。
そんな男らしさを簡単に発揮出来るのが虫退治である。頼れる男の演出には欠かせない。しかし、虫と言っても何でもよい訳ではないのだ。
蚊を殺せるのは当たり前、セミやバッタはそもそも殺す方が酷い男だと認識されてしまうので手を出さない方が良い。ムカデは都会では滅多にお目にかかれないので除外。蜘蛛やらカメムシやら色々いるけれど、ここは一番の嫌われ者ゴキブリが一番簡単かつ遭遇率も高めで効果が高いと思われた。
雑居ビルのひしめく歌舞伎町、飲食店の数と比例してゴキブリ王国も多い。へたをすると歌舞伎町の酔っ払いより数が多く、もう共同生活をしていると言っても過言ではないだろう。
LISKDRUGの入っているビルも例外では無かった。
たかがゴキブリ、されどゴキブリ。
店を閉めた後のLISKDRUG待機室では、そんな男達の思いが渦巻いていた。
* * *
何本か酒を開けた後のほろ酔い気分で仕事も終わり、皆どことなく緩んだ雰囲気である。
「さっきのめちゃくちゃでかかったっすよね! 久し振りにあんなでっかいの見たかも。茶羽のやつは結構みますけど」
ゴキブリもでかかったのだろうが、信二の声も相当でかい。
信二は続けた。
「でも、最近のゴキブリ退治スプレーって凄いっすね~。昔って新聞紙丸めて叩いたりしたじゃないっすか?」
信二が灰皿の横に置かれたゴキブリ退治用のスプレーを手にして、さも開発したのが自分であるかのように興奮気味に話す。
缶の表面には『マイナス90度! 凍らせて瞬殺!』と物騒なことが書かれている。
ゴキブリもたまったもんじゃないなと思いつつ、晶はソファから身を乗り出した。
「新聞紙って、お前いつの時代の人間だよ。昔もあったろ、シューってやって殺すやつ」
苦笑しながら煙草に火を点けた晶の口から煙が輪っかになって吐き出されて宙に消える。
「ああ……。ありましたね。僕も何度か使ったことがあります。でも、昔の物は薬剤が弱かったのか殺す力が弱くて、相当吹きかけないと死ななかった気がしますが……」
楠原が、当時を思い浮かべるようにそう言って「ゴキブリって生命力が強いですからね……確実にとどめを刺さないと。生き返らないように二度息の根を止めるように気をつけています」と付け加える。
ゴキブリという単語がなければ、ただの暗殺者も同然の発言だ。
「そうそう、めっちゃ吹きかけねぇと死なねぇんだよな。吹きかけすぎて奴の周りが水たまりみたいになってさ。そうなると今度は片付けんのが大変なんだよな~」
「わかります! 俺もそうなってた。やっぱそう考えるとコレって凄いっすよ。一瞬で凍らせられるんっすよ!? 画期的すぎて、俺が偉い人だったら、これ作った人にノーベル賞あげたいくらいっす」
「いや、それは言い過ぎっしょ。どんだけそのスプレーに感動してんだよ。随分やっすいノーベル賞だな」
「ノーベル賞はともかく、世界的に価値のある賞を取るには、殺した後、一切手を触れずに消せるぐらいの何かを発明しないと無理でしょうね」
「蒼先輩、それもう魔法っすよ」
皆一度は経験があるのだろう。三人の脳内には、薬剤の水たまりで息絶えるゴキブリの姿が鮮明に映し出されていた。
実は店が終わってすぐに、待機室でゴキブリが出たのだ。
店は改装して新しいが、ビル自体が古いのでそう珍しいことでもない。
後輩ホストがまっ先に発見し、叫びながら廊下に逃げてきた事で店は大騒ぎになった。
何事かと皆が待機室に駆けつけてみると、そこには近年まれに見る巨大なゴキブリがいたのだ。よくも退治されずにここまで大きくなれたものだと感心するほどに。
常備してあった退治スプレーで楠原が一瞬にして葬り、信二が手近にあった雑誌のページを千切ってそれで掴みゴミ箱へと捨て、無事ゴキブリ騒動は落ち着いた。
「それにしても、今の若い奴らってゴキブリ殺せないって雑誌で見たことあるけど、あれマジな話だったんだな」
「そうっすね。まぁ、あいつらがたまたまって可能性もありますけど……」
「でも、三人とも揃って無理な様子でしたよ? 男だからゴキブリぐらい殺せるだろうって考えが、もう古いのかも知れませんね。苦手な物は誰しもありますから」
「だな。まっ、でも女の子と一緒の時にそういう場面に出くわして、真っ先に悲鳴上げて逃げたら、女の子可哀想じゃね? 退治できる女の子だったらいいけどさ」
「そういう時は、本当は嫌でも無理して頑張るんじゃないですか? 男としては頼られたいですし、女性の手を汚させるのも忍びないですから」
「そうっすよね。え、だって、どうするんっすかね? 二人とも無理とか言ってたら逃げられますよね」
「どうしても無理な場合は、あえて逃げるのを待つしかねーんじゃねぇの? 見なかったことにするとかさ」
「逃げても同じ部屋だと、またいつか出てくるのに?」
「だって、それ以外ないっしょ」
「やはり、どちらかが退治できる方が安心ですね……」
「そうそ。ゴキブリぐらい殺せねーと、かっこつかねぇよな」
晶がそういって笑い、吸い終わった後の煙草を灰皿へ押しつける。その笑顔が若干引き攣っている事には誰も気付いていなかった。
先程の様子と今の会話を聞いていて、信二が全くゴキブリを意に介さない男だというのはわかった。ひょっとしたら苦手な可能性を考えていた楠原も、信二と同じく問題ないようだ。そうなると……。
――もしかして、自分だけなのか……。
晶は内心の焦りをごまかすように、二本目の煙草を手に取った。
殺せないわけではない、見るのも平気だ。
しかし、その後の死体を始末するのが正直苦手だった。雑誌越しでも触るなんてとんでもないし出来れば近寄りたくないのだ。
何故かというと、昔、完全に息の根を止めたはずの奴が、ゴミ箱へ運ぶ前に生き返ったからだ。いや、生き返ったわけでもなく、ただたんにまだ死んでいなかったのだろう。
ティッシュを何十にも重ねて軽く握っていた晶の手の中で、奴は暴れて晶の顔をめがけて飛んできた。めちゃくちゃ驚いた拍子に腰を抜かし、背後にあった壁に頭をしたたかに打ち付けた。
あの時の衝撃が今でもトラウマである。スプレーから吹き出る薬剤は真っ白だったせいで、それを被ったゴキブリもやっぱり真っ白で、それが顔にくっつきそうになったのだ。ああ……思い出しただけで鳥肌が立ちそうだ。
晶は無意識にスーツの上から腕をさすった。
「よーし、んじゃそろそろ俺は帰るかな。おまえら最後ちゃんと戸締まりして帰れよ」
「了解っす」
「お疲れ様です」
晶は一度オーナー室へ戻り、帰り支度を終えると店を後にした。
足取りがやけに軽いのには理由がある。
流行の歌を適当に鼻歌で歌いながら、通りに出てタクシーを拾った。
* * *
「ただいま~」
いつもなら、返事のない真っ暗な部屋から、今日は反応が返ってくる。
「案外早かったな」
灯りの点いた部屋から佐伯の声がする。
晶はそれだけで気分が上がった。
「そう? まぁ、寄り道しなかったからじゃね。要がいると思って、仕方ねぇから急いで帰ってきてやったんだよ」
「ほう、それは有難い話だな」
今夜は、というか昨夜から出張にきている佐伯が晶の自宅へ泊まっているのだ。
店の休みと一日も重なっていなかったので、店を終えてから佐伯のマンションへ通うには時間がほとんどない。なので、今回は佐伯に無理を言って、ここ晶の家を出張の間使ってもらっているのである。
開いていたノートパソコンの電源を落とした佐伯が、少し疲れたように頬杖をつく。当然だ。現在午前4時前。夜勤の日でもなければ佐伯は寝ている時間だろう。
「つか、先に寝てて良かったのに。こんな時間まで起きてて、暇して疲れたんじゃね」
「問題ない。やることは山ほどあるからな」
佐伯は言わない。お前が帰ってくるのを待っていた、とは。でも、こうして自分の帰りを待っていてくれたのは、言葉よりもグッとくるものがあった。
仕事を終えて疲れて帰宅した時、誰かが家にいて待っていてくれるというのは、思っていたよりずっと嬉しいことだった。
クローゼットで着替えながら、晶は佐伯を見ずに口を開く。
「ありがとな。どんな理由でもいいけどさ、やっぱ、帰った時に待っててくれる奴がいるっていいもんだよな」
佐伯は返事をしないまま、小さく笑った。
それが同意なのか。相変わらず淋しがり屋を隠さない自分へむけての物なのかは分からない。
「あー腹減ったな。カップ麺でも食おうかな」
着替え終わった晶がキッチンへきて棚を開けて物色する。棚には所狭しとレトルトやインスタント食品が押し込められていた。
「こんな時間に、そんな物ばかり食っていたら体を壊すぞ。俺が作ったのを残してあるから、それを食え」
「え! なに、飯作ってくれてたんだ? ラッキー。んじゃそれ貰うわ」
冷蔵庫を開けてみると、八宝菜らしきものがラップを掛けてしまってあった。冷凍してあるご飯パック(これも佐伯が作っておいてくれたらしい)と共にレンジで温める。
「使った材料がまだ野菜室に残っているから、腐らないうちに食えよ」
「俺、作れねぇよ。生で食える野菜じゃねぇの?」
「炒めればいいだろう。小学生でもそれぐらいは出来るぞ。切って炒めて、醤油でも掛ければ一品になる」
晶はそっと野菜室を開けて中を確認し、見た事がある野菜ばかりな事に安心して頷いた。切って炒めるだけなら出来そうだし、なんなら切らなくても大きいままで使えそうな物もある。
しかし、それを言うと佐伯に「横着をするな」と言われそうなのでそこは黙っておいた。
電子レンジが温め終わりの音を鳴らし、晶は熱々のそれをご飯の上に掛けて食卓へと腰掛けた。
「うまそうじゃん。いただきま、……ん?」
宙に浮いたままの晶のスプーンが停止している。
――今、何か動いた??
「どうかしたのか?」
飲み物を取りに来た佐伯が晶の視線の先を見る。
「いや、今なんかいた気がすんだけど」
「……どこにだ?」
佐伯も手を止めて暫く見ていると、二人の目の前の壁にゴキブリがひょっこりと歩いて顔を出した。白い壁に黒いゴキブリは非常に目立つ。
「そ、そこ!ゴキブリがいた!」
晶が急いで椅子から立ち上がり、玄関に置いてある殺虫スプレーを取りに走る。今日は二度目だ。
一日に二度もゴキブリと顔を合わせる羽目になるとは、思ってもいなかった。
下駄箱の中にあるはずのスプレーはいつ使ったかも忘れているぐらい昔の物なので、どこにやったのか中々見つからない。早くしないと逃げて見失ってしまう。
晶は靴を引っ張り出し、漸く奥の方にスプレーを発見した。
マイナス90度系では無いけれど、殺すことは出来るはずだ。
「あった!!」
手にしたスプレーを急いで部屋へ持ち帰ると、佐伯が壁際でまるでフェンシングをしているかのような「突き」の体勢で腕を伸ばしていた。
「……要?」
手を伸ばしたまま、佐伯は晶の方を振り向いた。
「もう殺した。ビニール袋と台所の洗剤をとってくれ」
「え? 殺したって、どうやって?」
勿論スプレーはまだ手渡していないし、佐伯は手に雑誌なども持っていない。まさか素手で!?
晶が恐る恐る近づいてみると、佐伯は手にした爪楊枝でゴキブリを串刺しにしていた。キッチンの近くに置いてあったものだ。しかもゴキブリはまだ死んでおらず爪楊枝の先でもがいている。
もうどこからツッコミを入れて良いのかわからない光景である。
「ちょっ、凄くね!? なにその殺し方。めちゃくちゃこえーんだけど!?」
「押し潰したら壁が汚れるだろう。丁度近くに爪楊枝があったからな。刺して動きを封じ、洗剤をかけるのが一番簡単で何も汚れない」
それはそう。佐伯の言うとおりなのだが、まず第一にゴキブリは素早いので、あんな細い爪楊枝の先で確実に胴体を仕留めるのは非常に難易度が高い。
そして次に、爪楊枝は短いので、もがいているゴキブリがへたをすると指に触れる可能性がある。怖すぎるし、嫌すぎる。考えただけでゾワゾワする。
晶が言われたとおり洗剤とビニール袋を持っていくと、佐伯はゴキブリを刺したまま手に持って奴の裏と表に洗剤をたっぷり垂らし、そのまま爪楊枝ごとビニール袋へ捨てて口を縛った。しぶとく生きているゴキブリがビニールの中でごそごそと音を立てる。
「……それ……、大丈夫? まだ死んでなくね? スプレーを中にシューってやった方がいいんじゃねぇの? 洗剤なんかで死ぬのかよ」
「やつらは腹と胸の表皮で呼吸をしているからな。粘度の高い洗剤をかければ1分もしないうちに窒息死だ。問題ない」
「あっそう……へ、へえ……」
佐伯の言った通り、少しするとゴミ箱に捨てられたビニールの中からは全く音がしなくなった。どうやらご臨終らしい。
念入りに手を洗い終えた佐伯が、何事もなかったかのように煙草を取り出して換気扇をつける。
温めてから食べるまでに時間が経ってしまったので、晶が再び飯を食べ始める頃にはすっかり冷めていた。やれやれ、とんだゴキブリ騒ぎである。
まぁ、それでも冷めていても佐伯が作ってくれた夕飯は充分おいしかったのだけれど。
「要ってさ……なんか、色々やっぱすげぇよな」
「ん?」
「いや、だってさ、俺、人生で初めて見たし。あんな殺し方すんの。必殺仕事人かよ」
「たまたまだ。手近にある物で素早く殺した方が逃げられずに済むからな。お前がスプレーを持ってくるのを待ってたら、見失ってたぞ」
「そりゃそうかもだけど」
晶は最後のご飯を掬い上げて口に入れると、思い出して一人笑った。
店で皆と話していた時、恋人同士の片方が退治出来れば安心だという話をしたばかりだ。
その時は、ありえないが、佐伯がもし苦手でもスプレーさえあれば自分が代わりに退治できる。頑張ればそのあとの死体の処理もなんとかやれるだろう。そう考えていた。
しかし、佐伯といる限り、その必要は全く無いようだ。
ゴキブリ関係は、佐伯に任せる事にしようと思う。
「要って無人島とかのサバイバル生活でも余裕で生きていけそうだよな」
「……?? 突然何の話だ」
「だって、変な虫とか、あと何かが襲ってきても瞬殺できそうじゃん」
「無人島に行く予定はないが、お前がどうしても守って欲しいって言うなら、協力してやらんこともないが」
「なっ!別に守って欲しいとか言ってねーだろ。俺だって、いざとなれば色々出来んだぜ? 泳げるし、食料だって調達できるし」
「ほう?野生の動物でも捌いてくれるのか?それとも魚でも釣ってくるのか?」
「いや……。動物捌くとか無理。釣りもした事ねぇけど……」
「……じゃぁ、なにを調達してくるつもりだ」
「えぇと……木の実、とか?探して拾ってくるし。それ食えばよくね?」
「木の実か……。二人で飢え死に確定だな」
佐伯は、そう言って苦笑するとゆっくりと煙を吐き出した。無人島には行かないけれど、いざという時の為に、魚ぐらいは釣れるようにした方がいいのかもしれない。
晶は、この時、真剣に釣りを始めるかどうか迷っていた。
END