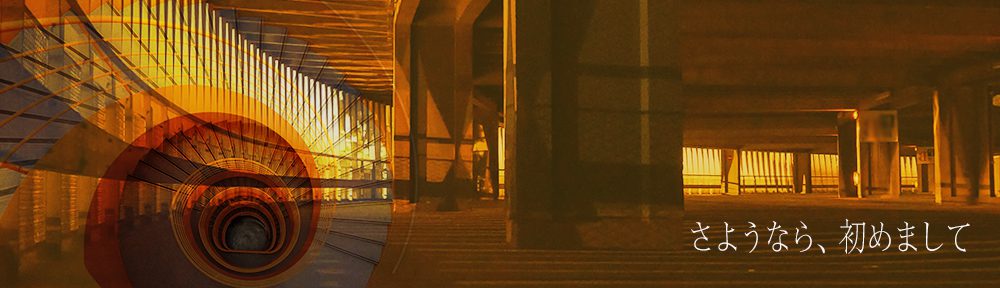──memory1──
「……死のう」
そう思った瞬間、まだ死んでいないのに凄く気持ちが軽くなった。
いつもと逆の電車に乗り、下調べをした駅で降車する。そう、朝からもう決めていた行動だ。
竜一は、締めていたネクタイを引き抜くと、端を持って屋上の柵からそれをひらひらとたなびかせた。このネクタイ、いつ買ったんだっけ? もうだいぶくたびれていて、剣先に続く両端の部分が擦り切れている。だけど、飛び込みの営業を掛けた時に褒められたこともある、一番気に入っているネクタイだ。
――本当にご苦労様……。今までありがとう。
ネクタイに敬意を払い、心からの礼を言う。
一際強い風が吹いた瞬間手から力を抜く。竜一に握られていたネクタイは、あっという間に飛んでいった。濃い灰色に、ぱっとみは水玉に見える柄入り。その水玉部分はよくみると小さなカメラの模様になっているのだ。その模様が視認出来たのも数秒、すぐに視界から消える。
闇に目を凝らし追っていくと、ビルの下、誰かが歩いているのが見えた。しかし、気付かれることもなくその背後にフワリと落ち、ネクタイは静かに地面に横たわった。
「……何も、なくなっちゃったな……、俺」
竜一は手摺りに腕を乗せ、一人呟いた。これでいい。
あと少ししたら自分も、このネクタイと同じように冷たいアスファルトに横たわっているのだろう。
人間は簡単に死ぬ。
それを初めて知ったのは子供の頃だった。自宅の鍵を忘れた時にいつも二軒隣の老夫婦の家で待たせて貰っていた。
一匹犬を飼っていて、そいつが可愛いので通っているうちに親しくなり、犬がすっかり懐く頃には飼い主であるその老夫婦とも親しくなっていた。
しかし、しばらくして、おばあちゃんの方が病気になり入院してすぐに亡くなった。その数ヶ月後には、後を追うようにおじいちゃんも他界したのだ。
変わらない日常を送っていた自分は、そのあっという間の出来事が中々受け入れられずにいた。「もう、おばあちゃんとは会えなくなったのよ」と言われ「どうして?」と訊ねる自分に母が告げた言葉。
――「遠い場所に行っちゃったから」
遠い場所。濁されたその言葉が『死』を意味する事は子供ながらになんとなくわかっていた。
飼い主の死後、可愛がっていた犬は親戚が引き取ったらしく、色々落ち着いた頃には姿が見えなくなっていた。
昔のことを思いだして、竜一は遠くの夜景を瞳の中にうつした。
今日の日中は少し暑さが残っていたが、今は吹く風が冷たく感じる程に寒い。十月下旬の夜空は、何も特徴の無い自分のような空だった。月も星も出ていない。
大都会の夜景をみていると、今の自分の惨めさが余計に身に染みた。
二年付き合っていた恋人との関係が不倫だった事が判明したのは今から少し前。何故急に知る羽目になったかと言うと、彼の携帯を偶然見てしまったからだ。恋人だとしても、普段は互いの携帯を見るような真似はしない。だけど、あの時は仕方がなかったのだ。
竜一の自宅へ泊まった次の日、彼が携帯を忘れていった。昼休みを利用して、何駅か離れている彼の会社へ届けた時のことだ。ポケットで何度も振動する彼の携帯に出るわけにもいかない。渡すまでの間サイレントに設定にしておこうと、サイドボタンを押すだけのつもりでポケットから取り出した。そこに表示されていたのは、彼と同じ名字の女性の名前。ご丁寧に(妻)と書かれている。
何かの冗談だと思った。
結婚指輪はしていなかったし、土日に会うこともあった。彼の自宅マンションへ行ったこともある。勿論、彼から既婚者だと聞かされたことも無い。そんな単純な思い込みで、一度も疑うことすらなかった。
現に前の日だって竜一の自宅で一緒に映画を見ながら酒を飲み、セックスをしていたのだから。
今となって思い返せば、付き合いが長くなり甘い雰囲気が無くなってきた時点で、違和感はあったのかもしれない。自分が鈍感で、一切気付いていなかったのか、それとも、何処かで気付いていて自分自身が気付かないフリをしていたのか、竜一自身にもわからない。
彼との未来をきちんと思い描いていたわけではないにせよ、漠然とこれからもずっと続くと信じていた。だから、余計に唐突に突き落とされた気がした。
彼はバイセクシャルで容姿端麗、頭も良くて誰もが羨むような男だった。
そんな男が寧ろ独身だという事の方がおかしいと、何故気付かなかったのだろう。三十歳にもなれば、そろそろ結婚し出す友人が出てきてもおかしくない。年に一度か二度会って飲みに行く程度の友人も何人か今年結婚し、それを機に疎遠になっていった。
竜一は、携帯を届けたその日からも、態度を変えぬように細心の注意を払っていた。気付いていないフリをし続ければ、このままで居られるとそう思った。だけど、そんな簡単な話じゃない。
いつも通りに出来なくなったのは、竜一の方だった。
自分が、彼の妻を苦しめているのではないかと罪悪感を抱くようになった。会う度にその感情は膨れあがり、今までのようにうまく会話を楽しむことも出来なくなっていった。気まずさから会う回数が徐々に減っていく。その変化に向こうが気付かないわけもなく、最終的には問い詰められる結果となった。
「竜一、何か俺に隠してる?」
――隠しているのは、お前の方だろ。
そう言いそうになるのを我慢し、冷静を装って結婚している事を知っていると告げた。彼はさほど驚かず「そうだったんだ」と気まずそうに視線を逸らしただけだった。
上滑りのみえみえの嘘でもいい、それでもお前が好きだと言って欲しかった。
だけど、それを望める立場じゃない事もわかっている。しかし、彼から出た言葉を聞いて、そんな考えをすることすら高望みなのだと知った。
「ごめん。相手が男だったら、浮気していても疑われないかなと思って……。都合が良かったんだ」
――なんだその理由。
何も言葉を返せなかった。
着信履歴に竜一の名前が残るのを気にしなかったのも、休日の電話に普通に出てくれたのも全部、男であれば、否、男の名前であれば誰でも良かったのだ。怒る気にもなれなかった。バイセクシャルである事を隠して職場の同僚とでも言っておけば、男と二人で酒を呑もうが出掛けようが確かに疑われることはないだろう。
二年掛けて大事に育んだつもりの愛情は、最初から今に至るまで一方通行だった。
自分は妻の居る男とただ寝ていただけ。真実はそれだけだ。
ぐっさりと刃先を押し込まれてやっと気付けた。肋骨をすり抜けた冷たいナイフが深い部分に刺さる。もう致命傷だ。長い夢から強引に殴って起こされた気分だった。
目を覚ました自分の傍にはもう誰もいない。
なんてあっけないのだろう。
ほんの小さな幸せが欲しかっただけなのに……。
胸には、痛みなんて言葉では表せないほどの傷が沢山ついていたけれど、治し方もわからない。痛くて悲しくて、自分の存在の全てが意味のない物に思えた。
自分の男を見る目の無さに呆れるばかりだ。彼と出会ったのはゲイバーだったけれど、出会ったその日から気があい、甘言を真に受けて、これは運命とまで思っていたのに。
とんだ笑い話だ。
この歳での失恋は、自分でも驚く程精神的に参るものがあって、今日に至るまでまともな睡眠も取れていない。
未だに何度も彼の夢を見る。
見た事もない彼の妻と彼が一緒に手を繋ぎ幸せそうに笑う夢を。その笑顔は、自分には一度も向けられたことの無い物だった。悔しいけれど、彼の居場所は自分の隣ではないのだとその度に思い知らされる。夜になるのも、一人でいるのも、何もかもが嫌になった。
職場は小さな印刷会社。最近の不景気のせいでいつ潰れてもおかしくない状態で、毎日毎日残業してもいっこうに軌道にのる事も無い自転車操業だ。営業成績のかんばしくない自分が肩たたきをされる日も、そう遠くないだろう。入社時にはあんなに感じていた仕事へのやる気も、いつのまにか色褪せてしまった。
恋人がいるだけまし。俺は大丈夫。
仕事があるだけまし。俺はまだ大丈夫。
雨風をしのげる家があるだけまし。餓死しないだけまし……。
『まし』の基準は一つ失う度にどんどん低くなり、マトリョーシカのように小さくなっていく。
もう残されたのは『生きていられるだけまし』それだけになった。
だったら、もう自分はここらでこの世からおさらばすればいいのではないか。
両親も恋人ももういないし、天涯孤独の自分が死んだところで悲しむ人間だっていやしないだろう。
こうして死に際に想いを馳せる相手が一人もいない人生に、価値があるとは思えない。
竜一にとって『死ぬこと』は苦しみから解放されるための手段でも、悲しみに打ちひしがれた絶望の結果でもない。そんなドラマチックな感情すらない。
ただ『もう、終わってもいい』と思った。酷く疲れていた。
この先、新しい恋をするのも怖いし。未来の自分を、別に知りたくない。
それ以外の理由なんてない。
竜一はスーツの内ポケットから煙草を取り出して咥えた。
煙草も今の自分には高級嗜好品なので、そうしょっちゅう買っているわけにもいかず、大切に大切に一箱を吸っている。今日は大盤振る舞いだ。箱には五本も残っているのだから。思う存分吸える。
ビルの屋上には誰もおらず、喫煙をしてもきっと誰にも咎められないだろう。こんな物騒な廃ビルなんて、普通の人間ならば近寄らない。
人生最後の煙草を肺の奥深くに吸い込んで感じた事は……。思っていたより普通の味だなということだ。
――……こんなもんか……。
正直がっかりした。
最後の煙草を咥えて「お前とも今日でお別れだな」なんて少し切なげな表情で口にする予定だったのに。それすら叶わないとは。
それでも、やはり何とも言えぬ感情が湧いている事は確かだ。
死ぬのが怖いわけでは無いけれど、先程から身体の震えが止まらない。
自殺なんて地獄行き決定だし、死んでからも自分は碌な人生を、いや死んでいるから『生』ではないけれど、送る事になるだろうなと。
竜一は短くなった煙草を思いっきり吸い込んで、眼下の夜景に吐きかけるように長く息を吐いた。一気にジリジリと火種がのぼってきた所で口から外し、コンクリートへと落とす。革靴の踵で吸い殻をもみ消した瞬間、竜一の視界の隅にありえない異物が写り込んだ。
「……?」
――……っ、なんで……。
目を細めて隣を見てみると、二メートルほど先に、なんと人が居たのだ。
自分が屋上へ上がってきた時、一通り周辺を確かめて誰も居ないのを何度も確認したはずだ。いったいどこから、いや、いつからそこにいたのか。
暗くてよく見えないが、見知らぬ男はラフな格好をしている。会社帰りの自分とは雰囲気が違う。歳はだいぶ上にも見えるが暗いので断定は出来ない。
いやいや、そんな事は今はどうだっていい。とにかく邪魔だし、飛び降りるところを見られたくない。辞世の句を詠むような情緒は持ち合わせていないが、最期は一人でひっそり逝くつもりだったのに。
かといって、ここは自分のビルというわけでもないので、どこかへ行けと言う事も出来ない。
――頼むよ、早く消えてくれないかな。
竜一は先程最後にするはずだった煙草をもう一本取り出して仕方なく口に咥えた。
二本目の煙草を吸い終わっても三本目の煙草を吸い終わっても、男は立ち去らなかった。
こうなってくると、これはもしかして相手も自分と同じ目的なのでは? という考えに辿り着く。この男も今から飛び降りようとしているのだ。向こうは向こうで竜一のことを「早くどこかへ行ってくれ」と思っているのかも知れない。このビルが自殺の名所だなんて聞いたことも無いけれど。
どんなバッドタイミングだよ……。
死ぬ間際までこんなに間が悪いとか自分の人生の運の無さにほとほと呆れる。
肩を落とし、なすすべもなく項垂れていると、ふいに男が話しかけてきた。
「あんた、死のうとしてる?」
ストレートな言葉に面食らった。他人にこんな不躾なことを聞く奴なんてお目にかかったことがない。
「……はい?」
咄嗟に返事をしたが、まさか話しかけられるとは思っていなかったので声が裏返った。
男は少しだけ近づいてきたものの、自分から声をかけたくせにその返事はどうでもいいような態度だ。ただの冷やかしか……。
一番困るのは、この後、自分が死のうとしているとわかってこの見知らぬ男に止められる事だ。
人生はまだ長い、諦めるな。とか熱く説得されるのだけは本当に勘弁して欲しい。何も知らない奴にそんなわかった口をきいて欲しくない。
どう答えるべきなのか逡巡していると、男は頭を掻いて大きな欠伸をし、こちらへ再度振り向いた。
COUNT0….|創作BL小説|メンズラブ|
シリーズ『俺の男に手を出すな』メインの長編連載小説サイトです。病弱、ホスト、バンドマン、医者、眼鏡、強気受け、リーマン。