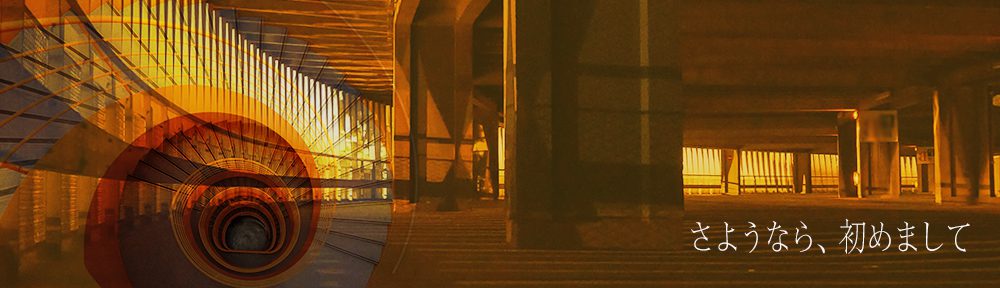──memory2──
元は良さそうなのに、身なりを構っていないせいで、ただのだらしない男に見える。髪はボサボサ、鼻までずり落ちている眼鏡に無精髭。足下をみると、履きつぶしたスニーカーを履いていた。
男を見る目に自信は無いが、面食いだと言われることが多いので、容姿の良し悪しの判断には自信があった。元が良かろうと、ここまで落ちぶれた風情の男に惹かれることは絶対無いけれど。
先手必勝、どう説得されても意志は固いという気持ちで振り向く。
「誰だか知らないけど、あなたに関係ないでしょ。用がないなら、どこか行ってくれませんか」
――言った。はっきり言ってやったぞ。
こう言われたら、特に理由も無く、やっかい事に関わりたくない普通の男なら立ち去ってくれるはずだ。しかし、何事も例外はある。目の前の男が『普通の男』ではない、そんな確率の低さを竜一は引き当ててしまったようだ。
「あー、わりぃ……。確かに関係ないよな。いや、もし死のうとしてるなら、俺に構わずどうぞって言おうと思ったんだけど。そういうわけじゃなかったんだな」
「…………え」
自殺するとわかっていて止めるつもりがないなんて、頭がおかしいのか。竜一は一歩後ずさった。止められるのも困るけれど、こうもあっさり「どうぞ」と言われても困る。
死のうとしている自分の事を棚に上げて、竜一は理解できないというように眉を寄せた。男が目を眇め、長く息を吐く。
「で……死ぬの? 死なないの?」
結局確認してくるじゃないか。そう思いながら、溜め息をつく。返事を待たずにかけてきた次の言葉に竜一は耳を疑った。
「あんたがしないんなら、俺先でもいいか?」
――……この男……。
本当に少し頭のネジが緩い奴なのかも知れない。
「先? ……あなた、何言って……」
「あー、だから。先に俺が死んでもいいか? って事」
「…………」
まるで、ひとつしか空いていないトイレを譲り合うレベルの軽さでそんな事を言う男に驚きすぎて返す言葉もない。ぽかんとしていると、隣の男はフラフラしながら柵に足をかけ始めた。人の返事を待たない上に、どうやら相当酔ってもいるらしい。
廃ビルと言っても、柵が腐り落ちるほどの古さはないので、そう易々と乗り越えられる物ではない。
一度引っかけた足はズルッと滑り落ち、男は中々柵に登ることも出来ないようだ。
これじゃ、飛び降りる前に横転してコンクリートに頭を打ち付けて気絶なんてこともありえる。見ているだけでヒヤヒヤした。
「あっ、ちょっと! 危ないな……、落ちますよ」
いや、自ら落ちようとしている人間に「落ちますよ」は意味がわからないだろうと思うけれど、他に言いようがない。
このままこの男は放っておいて、もう今日は諦めて帰ろうかと思ったが、気付いたら声をかけてしまっている自分がいた。死ぬ間際まで発揮してしまう男運の悪さ。
自分がどうしてこんな目に……。頭が痛くなってきたが、その前に、やはり自分の目の前で人が死ぬなんて、寝覚めが悪すぎるのでどうにかしてやめさせたかった。
「聞いてます? 危ないって言ってるのに」
「……ごちゃごちゃ煩いよ、あんた」
「あのなっ!! そっちが先に言って、」
柵に掛けた足はそのままに、男は不機嫌そうにこちらを見た。心底不愉快そうだ。冗談じゃない。不愉快極まりないのはこちらだというのに。思わず、明らかに年上っぽい相手に対しての口調も忘れ、タメ口になってしまった。
「何してんだよ。俺の前で死ぬとかやめて欲しいんだけど。見たくないんだよ」
「さっき、関係ないってあんた言わなかったっけ? それに、別に見なければいい。頼んでないだろ。俺は勝手に飛び降りる。あんたはこのまま帰る、なにか問題があるか?」
「あるよ。とにかく死ぬとか、やめてくれ」
「それは聞けない相談、――」
言葉の終わらないうちに男が目を見開く。
あ、と思った瞬間、男はバランスを崩して屋上側に盛大に尻餅をついた。やっぱり……。嬉しくもない予想的中に溜め息しか出ない。男は「痛ってぇ」といいながら腰をさすって眉を顰めていた。柵を越えられないほど酔っているなら、自殺なんかやめておけばいいのに。しかも……。
「……う、……グッ……オェエ」
「ちょっ、えっ!?」
尻餅をついた衝撃なのか、男はフラフラと腰を上げるとそのまま地面にゲロを吐いた。吐瀉物独特の匂いと、強いアルコール臭に思わずもらいそうになり、竜一は鼻と口を覆った。
本当に最悪である。
先程までの感傷的な気持ちはすっかり失せて、今の惨状にどっと疲れが増す。
竜一は風の吹いてこない方向へ回り込むと、ゲェゲェと吐いている男の側に行った。
「ええと……、大丈夫?」
どうしても放っておけなくて、背中を摩ってやろうかと竜一は腕を伸ばした。
――……っ。
しかし、指先が背中に触れる直前で一時停止を押されたかのように動けなくなった。触れたらきっと男の体温が指先に伝わる……。思い出したくない、人の体温に触れるその感触を。
急に震えだした右手を必死で隠し、後ろでギュッと握りしめる。じっとりと掌が汗ばんでいるのがわかった。
一体自分は何故見知らぬ男がゲロを吐くのを見ているのだと考えている内に、漸く我に返った。動揺を気取られぬよう、出来るだけ呆れた声を滲ませて口を開く。
「……。な、なにしてんの。もう……あなた、ただの酔っ払いでしょ。死ぬつもりなんてなかったんじゃないの?」
「オェっ……、あー、……くそっ、」
大量に吐き出したゲロを避けるようにして、男は汚れた口元を拭い。少し離れた柵におぼつかない足取りで進んでいって寄りかかった。何気なく男が吐いた物を見てある事に気付く。ほとんどがアルコールなのか水分ばかりの吐瀉物の中には白い錠剤が大量に混ざっていた。いくつかはもう溶けかかっている。
――……コレは。
瞬時に察する。この男も本当に自殺しようとしていたのだろうと。オーバードースをしても死ねなくてここまで来たのかも知れない。こんなに酔っているのだって、死ぬのが怖くて正気でいられなかったからなのだとしたら……。
どこかで自分と重ねてしまい同情している自分がいた。
この男にだって事情があって、色々考えた末の結論がこれなのだ。
だって、どう考えてもこの時間に、こんな場所に一人で来るなんて普通の男ではない。
男は苦々しい顔で何度か咳き込むと、苦しげに息を吐き出した。
「なぁ、あんた。さっき、煙草吸ってただろ。一本くれない? ゲロ吐いて口が気持ち悪いんだよ」
「……いいけど」
竜一は仕方なく煙草を取り出すと、一本を男の方へ渡してやった。貴重な煙草だが、断ったり説明をするのも面倒くさい。受け取って咥えた男は「火も貸してほしいんだけど」と図々しい事を言ってくる。
どうせ今夜はもうここで死ぬ事なんて出来ない。竜一は諦めて男の煙草に火を点けてやり、隣に立ったまま柵に寄りかかって自分も煙草を取り出した。
残っていた最後の一本を一緒に吸う。
煙草の箱はもう空っぽだ。
リングロープに縋る負けボクサーのように柵に腕を掛けたまま、見知らぬ泥酔男と一緒に夜景を見ながらの一服。試合が始まる前に終わってしまったような気分だ。
なのに、何故か先程一人で吸った煙草より美味しいのが納得いかない。
「まいったな……。まだ胃の辺りがムカムカしやがる」
男が眉を顰めて煙を吐き出し、胃の辺りをさする。
「参ったのは俺の方だよ。あなたさえいなければ、とっくに俺は、ビルの下で死体になってたはずなのに」
空を見上げて不満げに呟くと、癇に障るほど脳天気な声が返ってきた。
「へぇ。そりゃ、よかった」
「何が良かったんだよ! あなたのせいで計画が台無しだ」
あまりの言い種に、つい男を睨み付け声を荒らげてしまった。見ず知らずの他人にこんなに声を荒らげたことはない。
「悪かったって、でも、本当に良かったって思ったんだからいいだろ。結果的に、あんたはまだ生きてる」
「それがなにか?? 俺が死ななかった事で、何かメリットがあるとでも?」
「おう、数え切れないほどな」
男が自分を見て、初めて笑みを浮かべた。男が何を考えているのかサッパリわからなかった。
何かを返そうと口を開こうとした瞬間、雫が男の頬に落ちるのが見えた。ポツリ、暗い夜の空から一滴。竜一が男から視線を外して空を見上げると、丁度降り出した雨が暗い灰色の空から次々に降りかかってきた。
「……雨?」
「みたいだな」
屋上のコンクリートが雨に濡れてまだらに色を変える。こんな時に、雨まで降ってくるなんて……。ついていない。
竜一が、徐々に濡れていくスーツのジャケットの水滴を払っていると、男がぽつりと呟いた。
「雨、冷てぇよな。今の時期は、特にそんなに厚着でもないし」
「……?」
「さっき死んでたら、もう、雨の冷たさとかわからないんだぜ?」
「……だから、有り難がれって?」
「そうは言ってねぇだろ。そんなに噛みつくなよ」
すぐそこにはゲロがあって、全くロマンチックでも何でも無いのに、そういいながら笑顔を浮かべる男を見て酷くホッとしている自分がいた。まだ生きている、男の言葉が全身を駆け巡る。冷え切っていた指先がじんわりと温かくなる。
煙草を吸い終わると、男は一度大きく伸びをして柵から離れた。近くで並ばれると全然自分と身長が違う事に気付いた。かなり長身の男である。しかも足が長い。竜一は自分との腰の位置の違いに不満げな気持ちを抱いた。
「んじゃ、雨も降ってきたことだし、退散するとすっかな……」
「……あなたも今夜は、……やめるってこと? その……死ぬの……」
「まぁ、そういうこった」
いつまでもここにいても仕方がないし、このまま雨に濡れていたら風邪を引くかも知れない。つい先程まで死のうとしていた人間が、風邪を引く心配をするなんておかしな話だ。
溜め息をついたあと、竜一も仕方なく男の後についてビルの階段を下りた。雨の匂いと、ビル内の埃の匂いが鬱々とした気持ちを増長させる。男と自分の足音だけが、薄暗いビルの中でコツコツと響いている。
とんでもない事になってしまった。
だけど、家に帰りたくない気分だった。自殺を失敗した日の事なんて考えてもいなかったので、どういう心境で一人で自宅で過ごせば良いのかわからない。かといってホテルへ泊まるような金もない。
どうせ、死ぬつもりだったんだから、どうなってもいいと思い、竜一は男の後ろで勇気を振り絞って呟いた。
「あなた、ここの近くの人?」
「んー? ああ、そうだけど。寄ってくか?」
「うん……」
あっさりと「うん」と言った事が意外だったのか、男は一度足を止めて竜一の方へ振り向いた。
「マジで言ってんのか?」
「うん、そうだよ。一晩泊めて欲しい……。さっき、煙草あげただろ」
「いいけど、煙草代が宿代と同じとか、割に合わねぇな」
口ではそういいながらも、男はどこか楽しそうだった。ちょっと元がいい男だからって、こんなだらしない男の家に自ら行こうとしているなんて、今までの自分だったら絶対しない行動だ。もし自分と同じゲイだった場合は犯される可能性まである。
頭の中ではそれがわかっているのに、自棄になっている今は、そうなってもいいとすら思っていた。この男にどう思われたって関係ない。そういう意味では、全く素性の知れない男というのは、今晩一緒に過ごすのに最適な選択肢に思えた。
並んで歩いている間会話は無かったけれど。何度かクシャミをしていると、竜一の頭にバサリと男の羽織っていた上着が被せられた。
「着くまで被っとけ、傘代わりになんだろ」
要らないと突き返そうと思ったけれど、男の羽織っていた上着が温かくて、意思に反してギュッと握ったまま離せなかった。
男の言っていることは本当で、ビルから通りに出て十分もしないうちに目的地へ辿り着いた。
「え……ここ?」
路地の奥まった場所にある、お世辞にも綺麗とは言い難い一軒家だ。
「そうだけど。下は店やってるから住んでるのは二階な」
言いながら外階段を上る男について行くと、丁度下から三段目の階段に足を乗せた瞬間ギギッと音がし、階段の端っこが少し崩れた。
「ああ、階段の三段目は飛ばせよ。そこ痛んでるから、下手すると崩れて落ちるぞ」
竜一は慌てて四段目に移動した。
「もっと早く言ってよ。危なかった」
男は、そんな竜一をチラッと見て可笑しそうに笑った。最初に教えなかったのは絶対わざとだ。こんな子供みたいな悪戯をしてくるなんて、本当に変な男である。
階段を上りながら店だという一階に視線を向ける。シャッターが閉まっていて看板も出ていないので、何をしている店なのかわからなかったけれど、気付くともう玄関の先へ男が消えていたので慌てて追いかけた。
COUNT0….|創作BL小説|メンズラブ|
シリーズ『俺の男に手を出すな』メインの長編連載小説サイトです。病弱、ホスト、バンドマン、医者、眼鏡、強気受け、リーマン。