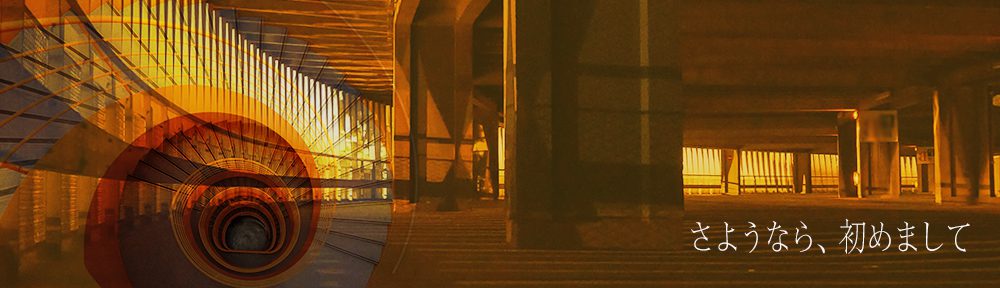──memory3──
引き戸の玄関をあけて入ると、タオルが飛んでくる。竜一は慌ててそれをキャッチした。
「泊まっていいとは言ったけど、もてなすような物はないぞ。適当に好きにしてろ」
被っていた上着を脱いで、投げられたタオルを頭から被り髪を拭いた。だらしない男にみえるが、洗濯はしているようでタオルは柔軟剤の良い匂いがした。
「上着、有難う……。おかげであまり濡れなくて済んだよ。これ、どうすればいい?」
「ああ、そこら辺に置いておいてくれ」
「わかった」
部屋に上がって上着を近くの椅子に掛け、奥へと足を踏み入れる。
「どこに座れば……」
見渡す限り荒れ放題で物の多い部屋は、男が先に腰掛けたPC前の椅子以外に座れそうな場所もない。
「どこって、どこでも好きに座れば良いだろ」
「座る場所がないから聞いてるんだけど」
何に使うのか、大量の工具やら基板、木材の端材、様々なサイズのネジなどがそこらじゅうに放置してあって、ここなら自分のアパートの方がまだ片付いていると思った。
「……やべ、まだ気持ち悪ぃな……」
男は竜一の言葉に耳も貸さず、独り言のように呟くと、玄関脇のトイレに入っていった。
ドアが閉まると同時に、男が嘔吐する声が聞こえてくる。あんなに大量の薬を飲んだのだから、相当吐ききらないと吐き気はなくならないだろう。
あれだけの量を一気に飲んでも致死量には至らないって事なのか……。
――病院へ行って胃洗浄をして貰わないとヤバイんじゃないのか。
どうでもよかったはずが、男が楽になる方法を無意識に考えている自分がおかしいという事に、竜一は気付いていなかった。
トイレのドアには、ブリキで出来たオルゴールの写真がセロハンテープで貼ってある。どこか懐かしさを感じさせるセピア色の写真。貼ってあると言うことは、この男が撮影したのだろうか。心の籠もったいい写真で、暫く見惚れてしまった。
竜一は、その後控えめに二度ドアをノックした。
「あの……、大丈夫? 病院に行った方がいいんじゃない?」
返事は無いけれど、代わりに獣じみた低い唸り声が戻ってくる。重い水音を耳にしつつ思いきって勝手にドアを開けると、部屋よりは片付いているトイレの中で男は便器に突っ伏していた。顔色はすぐれず苦しそうだ。
自分がいるのも構わず激しい嘔吐を繰り返すのを見ていると、その様子の危険さに怖くなった。
「ちょっと、本当に平気? まだ、気持ち悪いの? こんな所で死ぬなよ」
「死なねーよ。るせーな……。観察してる暇があるなら、背中でも摩ってくれ」
意識はしっかりしているようで、吐き捨てるようにすぐに言葉が返された。人が心配してやっているのにこの返事だ。つい、売り言葉に買い言葉を返してしまう。
「いや、あなた自殺しようとしてたんだろ? そのつもりで薬を大量に飲んでこうなってる。違うの? 自業自得なのに、俺に介抱を求めるのおかしいでしょ」
我ながら冷たい男だと思う。
だけど実際、本当の理由は別にあった。ビルの屋上で感じた感覚。男の体温に触れたくないのだ。少しでも楽になるなら背中を摩ってやりたいのに手が動かない。
まただ……。頭にズキリと痛みが突き抜ける。
突如現れる幻聴は、何度も何度も同じ言葉を繰り返す。停止ボタンのない壊れたプレイヤーのように。
――竜一は、ほんと俺に触れるの好きだよな。そうやってさ、いつもどっかに手を置いてくるじゃん?
――うん、安心するんだ。ちゃんと傍にいるのが感じられるからさ。嫌だった?
――別にいいけど。
ふとした会話が耳の奥、遠い場所で性懲りも無く響く。隣に居るだけでは満足出来ず触れてしまうのは、心の何処かで感じている不安感を拭い去りたかったからなのかも知れない。触れることでやっと実感できる現実が欲しかった。
あー、とか、うー、とか唸っていた男が水洗のレバーを引き、大量に吐き出された吐瀉物は一気に排水溝へと連れ去られた。気付くと幻聴は聞こえなくなっていた。
男の方を見ると、気が済むまで吐いたおかげで、顔色が少し良くなっている。竜一はホッと胸をなで下ろした。
「そういえば、さっきあんたが言ってた薬って何の事だ?」
口元をトイレットペーパーで拭った男が一息つき、座ったまま気怠そうに竜一を見上げた。
「だから、さっきからあなたが吐いてる物だよ。その錠剤、睡眠薬か何かじゃないの」
「ああ……。これか、薬じゃねぇから」
「はい?」
「ミントタブレット、っていうの? スッとする奴。あれ一缶一気に食っただけ。まさかこんなに気持ち悪くなるなんてな。逆効果もいいとこだ。とんだ目に遭ったぜ」
「…………」
ミントタブレットだと? それがわかった瞬間、ふつふつと怒りが湧いてきた。
自分と同じく何か悩んでいるのだとほんの少し同情したことが馬鹿馬鹿しくなってくる。
要は飲み過ぎて気持ち悪くなり、スッキリしたいためにミントタブレットを一缶全部一気に食べたら、逆に気持ち悪くなってしまった。それだけではないか。同情も心配もする必要の無い事だ。
怒りすぎると体調にも響くのか、頭が再び痛くなった。この男のせいだ。
「馬鹿なんじゃない。そんなに一気に食べる人とか、聞いた事ないし」
冷ややかな目で男を見下ろし、竜一は眉をひそめた。
「そうかもな……。俺、馬鹿だからさ。まぁでも、おかげさんでもう復活した」
そう素直に認められると先の言葉が出てこない。
竜一はトイレから出ると聞こえるような盛大な溜め息をつき、座る場所もないソファの上の物をどけようと持ち上げた。
――なんだこれ。
いい歳の男がこんなに沢山ぬいぐるみやらオモチャを持っているなんて、やはり相当な変人なのかもしれない。片耳が千切れそうになって綿がはみ出ているウサギのぬいぐるみは、とても大きくて綺麗な水色をしている。背中に電池が入る場所があるようだ。何か喋るか動く仕様なのかも知れない。抱き上げてマジマジと見ると、背部の部品が飛び出てきて慌てて手で元に戻した。
年季が入っているのか、表面は薄汚れている。近くの床へ軽い気持ちでどけようとした瞬間、トイレから出て来た男に注意された。
「おい、それ、乱暴に扱うんじゃねぇよ」
急な声に驚いて、竜一は身体をビクッとさせた。男の方を見ると、顔色がよくなった代わりに、眉間に深い皺が寄っている。真剣に怒っているらしい。
この男が、ぬいぐるみを大切にしていたとしたら怒って当然だ。竜一は素直に今とった行動を詫びた。
「……ごめん。別に乱暴に扱うつもりじゃ……これ、もしかしてお気に入り?」
「返してくれ」
竜一の手からオモチャを奪い取ると、状態を確かめた後、男は階段脇の棚へと大事そうにそれを並べた。
「まだ直して無くて、その……触ると余計壊れちまう」
「直す……?」
竜一は男が棚に置いたオモチャに視線を向けた。腕の取れたソフビの人形のほか、棚には他にも模型っぽい物やリカちゃん人形のような物、昔流行った携帯ゲーム機などがびっしりと並べられていた。悪く言ってしまえば、ガラクタにしか見えないようなモノばかりだ。
よくみると、結婚式の引き出物で昔みた事がある陶器製のオルゴールなんかもある。
竜一がそれらを見つめていると、男が頭を掻いて竜一の方へ振り向き、気まずそうに頭を下げた。
「急に大声出して、悪かったな」
「いや、いいよ……。誰にでも大切な物はあるし、俺が悪かったから……」
「……」
「……な、なに?」
「あんた、……馬鹿にしないんだな」
感心したようにそうにそう言って、男は口元を緩めた。
「普通、こんなおっさんがおもちゃを部屋一杯に並べてたら変な目で見るだろ?」
「まぁ……。最初はちょっとそう思ったけど。人の趣味にとやかく言うつもりはないよ……」
「そっか」
男はオモチャの棚から戻ると、竜一が座れるように、雑誌の山になっていた所を崩して隙間を空けてくれた。
「どうも……」
隙間に腰を下ろして、部屋を見渡す。一人暮らしなのか、他に人の気配はしない。こんなに物が多いのにどこか生活感が欠けているのは、つかみ所の無いこの男と似ている気がする。
「別に俺の趣味ってわけじゃない。さっき一階の店を見ただろ? 俺がやってる店」
「ああ、うん。でも何の店かは書いてなかったからわからなかったよ」
「わかりやすく言えば、おもちゃのお医者さんってやつだな。種類を問わず、何でも直す修理屋をやってる。さっきあんたが手にしたぬいぐるみも、客から預かっている物だ」
「ああ……、そうだったんだ。本当に、ごめん。だから、こんなに色々なオモチャがあるんだ」
「そういうこと。最近は、オンラインを通して一で人遊ぶようなものが多いけど、こういうふうに……」
男が別のぬいぐるみを抱き上げて優しい表情を浮かべる。
「手で触った時のあったかさとかさ、感触とかが伝わるオモチャもいいもんだぞ。子供の頃から常に一緒にいた人形やぬいぐるみは、過ごした年数分の想い出が詰まってる。他には、昔遊んでいたゲーム機が懐かしくて修理を依頼してくる客もいるし。関係の無い奴には、ただのゴミかも知れないが、どれも大切な物だ。オモチャを通して、客の思い出を修理する。そういう仕事をしてる」
「……、……」
饒舌に語る仕事内容は、ただのサラリーマンだった自分からすれば夢のある仕事で羨ましかった。それと同時に、想い出の修理屋をしているといった男の表情に釘付けになった。キラキラとした瞳、まるで夢を未だに追う少年のようだと思った。
自分も入社したての頃は、この男のように仕事にやり甲斐を感じていたはずなのに。今は、生活をする為に働いている、それだけの意味しか持たなくなってしまった。
趣味で写真を撮ってもいるが、それだって最近は時間も無くて遠ざかっていた。大金をはたいて買った一眼レフはすっかり埃を被っているだろう。
会話の流れとして、自分もどんな職に就いているか、さらっと教えた方がいいだろうかと考えたが、別に楽しくも面白くもない話である。結局竜一は、開きかけた口を閉じた。
「珈琲飲めるよな? 淹れるけど飲むか?」
「有難う……。じゃぁ、いただきます」
すぐそこにある簡易的なキッチンで何度かうがいをし、その後湯を沸かす背中を見ていると、不思議な感覚になった。
こんな見知らぬ男と二人きりでいるのに、気まずさや居心地の悪さがない。
付き合っていた彼といる時は、常に嫌われないように気にしながら行動をしていた。
この男は、本当にいい人なのだろう。犯されるかもしれないなど、失礼な考えを一瞬でもしてしまったことに心の中で謝罪した。
音の鳴る昔ながらの薬缶。ピーッとけたたましく鳴り響いた後、カップにお湯を注ぐと珈琲のいい香りが漂ってきた。
二つのマグカップを手にした男が、「インスタントだけど」と前置きしつつ一つは竜一の前に、自分の分は手に持ったまま柱へと寄りかかった。
「いただきます」
「どうぞ」
熱々のマグカップを両手で包んでフーフーと息を掛ける。竜一はやや猫舌なのだ。いつもなら砂糖とミルクを入れてのむのだが、たまにはブラックもいい。喉を通って行く熱い感触。
「……美味しい。……それに、あったかい……」
男に淹れて貰った珈琲が体内に浸食していく。こんな些細な事でも、人の優しさに飢えていた自分が満たされていくのがわかる。
寒気がしていた身体が次第に温まってくると、気持ちも落ち着いてきた。
「あんたさ」
呼びかけられ、視線を向ける。珈琲から立ち上る湯気の向こうで、少しだけ眉を下げて困った表情の男と視線が合った。
「今もまだ、死にてぇか?」
「……え」
男に問われて初めて、自分が死のうとしていた事を忘れているのに気付いた。
「あ、……いや……その、今は」
「今は?」
――忘れてた。
なんて言えない。口ごもっていると、男はゴクリと珈琲を飲み干し、流しへマグカップを置くと近くに来て、目の前の床へ腰を下ろした。ソファに腰掛けている竜一を見上げるように男の視線が向けられる。竜一は視線を外したまま呟いた。
「……あなただって飛び降りようとしてたくせに」
話の矛先を返すと、男はなにがおかしいのか「そういや、そうだったな」と言って笑った。
「あれは、俺の演技だ。ゲロ吐いたのはマジだけど。どうだ、迫真の演技力だったろ」
「演技!?」
「そ。俺は、死ぬつもりなんて最初からねぇよ」
「どういう……こと」
「あんたさ、俺があそこで『死ぬのをやめろ』って説教したら余計に意地になるタイプだ。違うか?」
「なに言って……。数時間前に初めて会ったばかりで、何がわかるって言うんだよ」
「初めてかどうかはともかく。俺は確かに、あんたの事は何もわからない。でも、あん時は直感でそう思ったんだ。いちかばちかで、賭けてみた」
「なんで、そこまでして……あなたには関係ない男なのに、どんだけお人好しなんだよ」
男はまるで恋人にでも向けるような穏やかな表情で竜一を見つめ、寂しそうに息を吐いた。
どうしてそんな目で見るのだろう。男の視線を見ていると、胸がギュッと締め付けられた。
話出す男の口元がゆっくりと開くのを見ていると、言葉の一つ一つが塊になって自分の中に詰まっていくような苦しさを感じた。
「帰り道にさ、ビルの下を丁度歩いてたら、ネクタイが降ってきた。最初は無視して通り過ぎたけど、なんだか気になってな……。ネクタイを拾いに戻ったんだ。見上げたら、あんたが屋上にいるのが見えた」
――……あの時だ。
竜一は時間を巻き戻すように記憶を辿る。屋上から見えた人影、気にもしなかったけれどそれがこの男だったのだろう。男の言葉は続く。
「その瞬間、ビルの階段めがけてもう走ってた。俺が止めなきゃって思ったんだ。俺は、間違ってたか?」
「……、……」
「あのビル、結構階数あるんだよな。相当飲んでたのに全力で走ったせいで気持ち悪くなっちまった」
「……。ほんと……とんだ迷惑だよ……」
「まぁ、そう言うなって。あ、そうだ。これは返しておく。大事なもんだろ」
男がポケットから、先程屋上から捨てたはずのネクタイを取り出し、僅かに付着しいていた砂を払うと丁寧に畳んで竜一へと差し出した。
拾って持っていてくれたのだろう。また手元に戻ってくるなんて思っていなかった。
擦り切れたネクタイ。捨てたはずのネクタイ。渡されたそれを見ていると、急に悲しくなった。
「……別にもう、……要らなかったのに。ボロボロなんだ、これ……」
竜一はネクタイを受け取ると、苦笑いで感情をごまかしてスーツのポケットへとグシャッとねじこんだ。
男がずれていた眼鏡を押し上げて、未だ雨で少し湿った髪をかき上げる。彫りの深い顔立ちは、こうして間近で見ると……、本当にいい男だった。もしかしたら外国の血が混ざっているのかも知れない。
「感謝とか、するつもりないよ……有難うも、……言わない」
「別に、それでいい」
「……あなた、本当に変わってる」
「まぁ、それは否定しないが。――なぁ……、あんたさ」
「……、……」
「ボロボロになってんのは、……ネクタイじゃなくて、あんたなんじゃないのか?」
「……、っ……なに、それ」
ふいに涙が滲んできて、竜一は堪えるように奥歯を噛みしめた。渇いた喉に唾を飲みこむとヒリヒリと痛んだ。精一杯強がっているのが自分でもわかる。こんな気持ちになっているのは、生きているからこそだ。
悔しい、悲しい、情けない、見られたくない、でも……、誰かに甘えたい。そんな全ての感情が生を証明し、どろどろに渦巻いて唇が震える。
我慢しきれない涙が、竜一の頬をツゥと伝った。
COUNT0….|創作BL小説|メンズラブ|
シリーズ『俺の男に手を出すな』メインの長編連載小説サイトです。病弱、ホスト、バンドマン、医者、眼鏡、強気受け、リーマン。