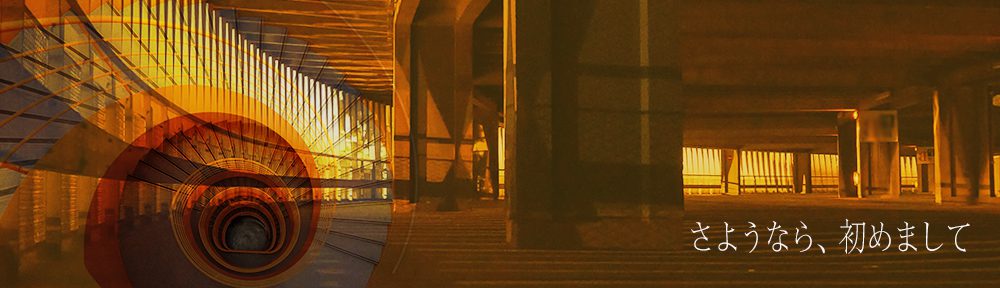──memory4──
男が何も言わないで自分を見つめているのがわかる。その表情を窺うのが怖くて顔を上げられなかった。
頬をなぞって落ちてくる雫は、先程の冷たい雨と全然違う。唇に伝えば、それは温かくて塩辛い。
「……いい歳して泣いたりして、俺って、本当に、ダサい……」
「んな事、思ってねぇよ」
「嘘だ、思ってるくせに。死ぬのも失敗して、ずっと付き合っていた彼にも捨てられたんだ。もう俺には、何も残ってない。何も……。全部、全部……俺には、」
言っている側から、いや、言えば言うほど、どんどん惨めになって、どうしたらいいのかわからなくなる。こんな事を言われたって困るとわかっているのに。でも、吐き出せなかった気持ちは堰を切ると止められなかった。
今顔を上げたらきっと、目の前にはうんざりした表情をした男の視線があるはずだ。竜一は恐る恐る濡れた睫をあげ、その瞬間息を呑んだ。
――……どうして……、そんな顔。
ずれた眼鏡の上から向けられる柔らかな視線。紡がれる言葉は男の口を出て竜一へと届いた。
「そうか、それは辛かったな。本当に、辛い事だ」
その言い方があまりにも優しげで、また涙が溢れる。
男が、優しく目を細め静かに竜一の涙を指で拭った後、そっと腰を上げる。一瞬「いいか?」とでも訊くように微笑んだ後、そっと身体を抱き寄せた。
「……!? っ、待っ」
――待って、俺に触らないで。そう言い終える間もなかった。
触れられた瞬間、案の定全身が強張ったけれど、あやすようにトントンと背中を叩かれているうちに次第にほぐれていった。その代わり、心音がもの凄い早さでうち出している。男は別にそれ以上のことをしてくる様子はなかった。
男の温かい腕を振り払うこともせずに受け入れている今の状況が、自分でも驚きである。
彼と別れてから、色々言い訳を自分の中で積み上げてきた。失恋の悲しさを想い出さないように。
だけど、こんなに優しくされたら思いだしてしまう。痛い。心の傷に、この男の優しさがしみ込んでいく。触れるのが怖かった他人の体温が、こんなにも心地よいなんて。
見知らぬ男の腕の中で涙を流す自分。こんなに素直に感情を表したのも、みっともない姿を晒すのも初めてかも知れない。
竜一の身体から腕を外し、男が顔を覗き込んだ。肩に置かれた大きな手から体温が伝わってくる。
「……、……」
「俺が、あんたを修理してやる。何でも直せるってのは誇大広告じゃないんだぜ? だから、死ぬな」
何度か鼻をすすって竜一は涙目のまま男の顔を見つめた。
「俺は、……オモチャじゃないよ」
「知ってる」
「修理なんて出来っこない……。替えの部品もないし、製造元だって不明だ」
「替えの部品は俺が作る。製造元なんか関係ねぇよ。なんなら、俺が製造元でどうだ」
「……ほんと、変な人。……俺にそんな優しくするなんて、何か理由がある、とか?」
「理由、か……」
竜一の言葉に、男は少し言葉を詰まらせ頬を掻く。側のテーブルに置いてあった煙草を咥える姿は、今までと違い少し余裕がないように見えた。
「吸うか?」と勧められ、竜一も一本貰う。自分が吸っているのとは別の銘柄だ。
沈黙はちょうど煙草一本分。涙が止まって少し落ち着いた竜一の様子を見て、ゆっくりと煙を吐き出した男が竜一のポケットを指す。
「そのネクタイ」
「……?」
「カメラの柄なんて珍しいからな。拾った瞬間、すぐに気付いた」
「気付いたって……何に?」
男は一度腰を上げると、PCデスク横の資料棚のような場所をごそごそと探しだした。「あったあった」と独り言を呟き、元の場所へと戻ってくる。手にしているのは日本でトップクラスの玩具メーカーのパンフレットだ。男はそれをバサッと竜一の目の前に広げた。見覚えがあるオモチャが表紙を飾っていた。
立ち上げ当時はプラモデル専門のメーカーだったと聞いた事がある。今は手広くやっていて、誰でも一度はここの玩具メーカーのオモチャを買った事があるぐらいには有名な会社だ。
営業としてやっと一人で新規開拓を任されるようになった頃行ったことがあるが、いいところまで話が進んだのに結局仕事は貰えなかった。竜一は、パラパラとページをめくった後、顔を上げた。
「これが、どうかしたの?」
「昔、ここの社員だった」
「え……、本当に!? 凄い……。大企業じゃないか」
「まぁ、そうなんだろうけどさ。だが、そこはどうでもいい話だ」
「……?」
男は一度眼鏡を押し上げると、思い出すように話出した。
「ある日、印刷会社の営業マンが職場に来た事があった。カタログをうちで作らせて欲しいってな。かなり一生懸命な様子で、すげーキラキラしててさ、可愛い奴だったよ。最初は話だけ聞くつもりが、その熱意に押されて、具体的な所まで話が進んだ」
竜一はハッとして唾を飲みこんだ。
男の言う印刷会社の営業というのは自分の事だ。
電子書籍が広まったせいで、今までの市場をほとんど奪われつつある。前までカタログやパンフレットなどを一手に引き受けていた取引先からも徐々に仕事が来なくなった。
印刷だけでは見向きもされないので竜一が入社した頃丁度、デザインも請け負う部署が出来たばかりだった。とにかく仕事が欲しくて、有名所からアパレル系、商店街の小さなお店のチラシに至るまで、手当たり次第営業をかけていた。その中で、この玩具メーカーへも行った事があったのだ。
本社である自社ビルは都内のオフィス街にあり、入り口からロボットが出迎えるという変わった受付で、いかにも玩具メーカーらしい遊び心が感じられた。
他にも大手と言われるメーカーに幾つか行ったけれど、どこも小さな印刷会社の営業なんて相手にして貰えなかったのに、ここだけは違った。
当時話を聞いてくれた担当者を思い浮かべる。日本人離れした体格で、一目見て圧倒された記憶がある。スーツの着こなしからして自分とは全然違い、酷く格好よく見えた。大企業に身を置く男との格差を思い知ったものだ。商談をするうちに少し親しくなったけれど、仕事の縁が切れると同じく、関係もそこで途切れてしまった。
心臓がドクッと大きく打ち、自分の耳へと響く。
「…………もしかして……」
「正解、あんたが商談した相手は、当時の俺だ」
「うそ……。あの時の……」
今目の前に居る男が、あの時の担当者だったなんて。確かによくよく思い出してみれば背格好は同じだし、今はだらしない格好だが髪を整えてちゃんとスーツを着ればあの頃の彼と同じだ。手応えを感じるまで話が進んだのに、最終的に上からの許可が下りず竜一の会社は使って貰えなかった。
それでも、毎回真剣に話を聞いてくれるその彼に心から感謝をしたし、時々挟まれる雑談もとても楽しかったのを覚えている。自分とは住む世界の違う相手として、こういう人と一緒に居ると楽しいんだろうなと、ほのかな憧れも持っていた。
「あんた、あの日もそのネクタイしてたよな。話す前にさ「素敵なネクタイだ。珍しい柄ですね」って俺が言ったら、「趣味で写真を撮ってるんで、カメラの柄が気に入っているんです」って、撮っている写真の話を聞かせてくれた。覚えてないか?」
「……覚え、てる」
話を聞くうちに当時の会話や光景が鮮明に脳裏に浮かび上がる。その頃はまだ新しかったこのネクタイを褒められて嬉しかった事も……。
竜一は戸惑う気持ちを抱きながら信じられないというように首を振った。
「まさか、こんな偶然があるなんて……」
「……ああ、俺も正直、屋上であんたを見るまでは半信半疑だった」
「あの頃は、俺、今と違って自分ならもっとやれるって根拠もなく自信があって、随分しつこくした記憶があるよ。一度目で断られたのに何度も押し掛けて、相当迷惑かけたと思う」
今となってはその情熱が空回りに感じて恥ずかしさがあった。その当時の自分を知る相手とこんな所で会うなんて……。
「迷惑? そんな風にはちっとも俺は思ってなかったぜ。寧ろ、逆だな。あんたが来るのを楽しみにしてた」
「……本当に? 社交辞令でも、そう言って貰えると安心する」
「社交辞令じゃねぇよ、本当の事だ。仕事が流れた後も、一度あんたに電話をかけようとした事もある」
「俺に電話を? なにか、話が……?」
「ああ、礼を言いたかったんだ。あんたには俺がどう写っていたかわからねぇけど、あの頃俺は、色々あって腐ってた時期でさ。何もかもにうんざりしてた」
「……、……」
「でも、あんたと何度か会って話すようになってから考え方が変わったんだ。一生懸命な姿が眩しくて、気付いたら感化されてた。あの後少しして、会社を辞めたんだ」
「そうだったんだ……」
「あんたが気付かせてくれたおかげで今の俺がいる……いい結果を返してやれなくて、あの時は……本当に悪かった。俺の意見だけで採用できるほどの立場じゃ無かったからな」
思いも寄らぬ事を言われて、竜一は視線を彷徨わせた。考えた事もなかったことだ。自分が他人に影響を与える事があるなんて。
「仕事で縁が貰えなかったのは残念だけど、それは仕方がないって。俺だってちゃんとわかってるよ。……にしても……」
竜一は男をマジマジ見つめ小さく笑った。
「まるで別人だな、言われるまで全く気付かなかったよ」
「そうか? まぁ、髪も伸びたし歳もくったしなぁ……。今じゃ滅多にスーツも着ないから」
「もったいないよ、折角かっこいいのに。俺、男としてちょっと憧れてたんだ。髪をこう、――」
竜一が男の髪を左右に流し、バラバラに散っている襟足の髪を後ろで纏める。ついでに眼鏡も人差し指でぐいと上に押し上げた。
「ほら、こうすればだいぶ変わる」
男は、側にあった電源の入っていない携帯を手にし、黒い画面に映り込む自分を見て苦笑した。
「……そうか? 変わんねーぞ」
「ううん、10%ぐらいは、かっこよくなってるって」
「たったの10%かよ。元が何%なんだって話だな」
男が笑う。そしてその笑みはスッと消えて、どこか切なげな色が代わりに浮かんだ。
「でも、そういうあんただって、俺には随分変わったようにみえるぜ」
「……いつまでも、新入社員じゃないんだから当然だよ。……俺だって同じだけ歳くってるんだし。今はもう……あの頃とは違うよ」
「もったいないのは、お互い様ってやつか」
「……そうなのかも」
「また見てぇなぁ……。元気いっぱいのあんたをさ」
「もう戻れないよ」
そう、お互いあの頃とは変わってしまったのかも知れない。だけど、この男の変化は前向きな物と捉えられるのだから自分とは真逆だ。いつから、こうなってしまったのだろう。
少なくとも、自分はもう昔の自分には戻れないと思った。
俯く視界に入る自分のくたびれたスーツ。
昨日も一昨日も同じ物を着ていた。
見知らぬ男が、知っている男に変わった瞬間、こうして正体を晒していることが急に恥ずかしくなった。それに先程から妙に身体が重くて、頭痛が少しずつ酷くなっている。
竜一はこめかみを押さえて一度目を閉じた。
どう思われてもいいと、半ばどうにでもなれという気持ちで家にまで着いてきてしまったけれど、知っている人間に醜態をさらしたとなれば話は別だ。今はもう、押し掛けて急に泊まらせて欲しい等と言ってしまった事を悔やみはじめていた。
こんな出会いなんて要らなかった。
「……。俺、やっぱり帰るよ。色々迷惑掛けて申し訳ない」
男は、急に立ち上がった竜一に驚いて腕を掴んだ。
「どうしたんだ、急に。なにかあんたの気に障ることでも言ったか?」
竜一は何度も首を振って出来る限りの笑みを浮かべた。
「いや、そういうんじゃない。感謝してるよ。でも、やっぱりおかしいと思って。その、さっきはちょっとどうかしてた。忘れて欲しい。……ごめん」
「謝るぐらいだったら、今晩は泊まっていけよ。雨も降ってるし、家どこだか知らねぇけど今から帰るのも大変だぞ。それとも、あれか……?」
「あれ、……って?」
「俺に、襲われるとでも思ってんのかなって」
「え!? いや、まさか。違うよ。それに、あなたノンケじゃないの? 襲うとか……そんな」
「あんたさ、よく鈍いって言われないか?」
男はまた煙草を咥えると、やれやれとでも言いたげに煙を口の端から勢いよく吐き出した。
「さっきから何回かあんたのこと口説いてるつもりだったんだけど。全スルーとか、流石に俺も傷つくぞ。それに、どうでもいい野郎を慰めたり抱き締めたりすると思うか?」
「……え」
「え、じゃねぇよ。下心があるから誘ったって言ってんだよ。弱ってるあんたにつけ込んで口説いた。狡いのは百も承知だが、のってきた時点で、あんたの負けだ」
俗悪的な言い方。男の言うとおりだ。どんな状況であったとしても、あの時点で見知らぬ男の家についていく事を決めたのだから、気持ちが変わったからって今更帰るなんて虫の良すぎる話だ。
ここは、男らしく覚悟を決めるべきだと思う。
こんな悪者ぶった言い方をする男の内心が、言葉とは裏腹に優しい物である事を知っているのだから怖い事なんてない。昔の自分を眩しいとまで思ってくれた相手に逃げるような真似をして、これ以上幻滅されたくないという気持ちもわき上がってきた。
竜一は大きく息を吸った。
先程自分を抱き締めてくれた腕の温かさに、下心なんて感じられなかった。これは、勘違いなんかじゃない。寧ろ、心の何処かで期待していたのは自分の方だったのではないか。
「泊まっていけよ……。帰るなんて言うな」
もう一度耳元で低く囁かれ、男の声が何度も鼓膜の上を滑る。
竜一は、着ていたジャケットをぎゅっと掴むと、男と真っ直ぐ視線を合わせた。自分の身体一つで礼になるとは思っていないけれど、下心を満たすぐらいの役目は果たせるかも知れない。触れられるのも触れるのも、今はまだ本当は怖い。だけど……誰かに必要とされている事が嬉しくて。
目の前に立って顔を覗き込む男の顔が、僅かに霞んで見える。心臓が口から飛び出るのではないかと思うほど緊張していた。
「わかった。俺でいいなら……いいなら……、好きに……、し」
――あ、れ……?
「おい、どうした? おいっ」
焦ったような男の声が遠くで聞こえる気がする。
先程から感じていた体の重さが極限に達していて、思うように動かない。流石にここ最近続く寝不足がたたったのか、そう考えながら次第に意識が朦朧としてくるのを感じた。
最後に感じたのは、温かい腕で支えられている感触だ。その腕が付き合っていた彼のものなのか、見知らぬ男の物なのか、わからなくなってくる。
人間はこんなにも眠くなることがあるのかと思うほどに眠い。引きずり込まれる夢の中にずぶずぶと沈んでいく、底に辿り着いたらどうなるのだろう……、そんな事をぼんやりと考えていた。
竜一は目を閉じ、その腕の温もりに身を任せた。
COUNT0….|創作BL小説|メンズラブ|
シリーズ『俺の男に手を出すな』メインの長編連載小説サイトです。病弱、ホスト、バンドマン、医者、眼鏡、強気受け、リーマン。