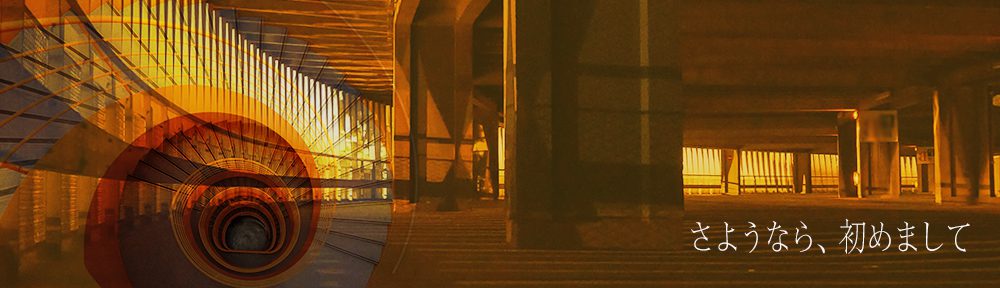──memory5──
携帯の目覚ましアラーム。いつもなら鳴る直前に目が覚めてしまうのでその音を聞くことも無いけれど、今朝は何度か鳴り響いている。竜一はベッドから手を伸ばしてモゾモゾと携帯を探した。だけど、いくら探しても見つからない。
仕方なく目を開けると、見知らぬ天井が視界に広がっていた。耳には未だ鳴り響くアラーム音。鳴っている携帯は探しても見つかるはずがなかった。なぜならば、寝ているのが自分のベッドではないのだから。
――???
ここはどこだ。三つ浮かんだ脳内の疑問符が順番に消え、最後の一つが消える瞬間、竜一はガバッと起き上がった。
「痛っ、……」
同時に頭に鋭い痛みが走った。まるで二日酔いの朝だ。ゆっくりと周囲を見渡して自分が置かれている状況を確認する。
そうだ、昨日……。
全てを思い出して頭を抱えたくなった。酒を呑んで記憶を無くしていた方がマシだったと思うぐらい、途中までは鮮明に覚えている。見知らぬ男について行って、しかも感情が高ぶって泣いたりしたことも思い出す。そのまま泊まってしまったのだ。
帰ろうとしたのを止められたところまでは覚えているが、いつベッドへ来て寝たのかは思い出せない。
ハッとして掛布の中の自分の身体を見てみると、下着姿だった。全裸ではないという事は、男と寝てはいない……はずだが、いつスーツを脱いでこの姿になったのかもわからない。右を向くと、スーツとワイシャツがハンガーに掛かっている。携帯のアラームはそのスーツの中から鳴っていた。
そして一番不思議な事に、このベッドの主である男の姿が見当たらなかった。
竜一は痛む頭をおさえながらベッドから足を降ろし、ようやくアラームを止めると、昨日男と話したリビングへ行ってみた。
昨夜は夜で気付かなかったが、天井が高く大きな窓から陽射しが沢山入り込む日当たりのいい部屋だ。
ほんの少しの機械油のような匂いと、煙草の匂い。
昨夜竜一が腰掛けていた部屋のソファの上で、大幅に足をはみ出させて男が寝ていた。
自分がベッドを占拠したせいで寝る場所が無かったのだろう。本当に申し訳ないことをした。
竜一は、男に近づくと、声をかけた。
「あの」
「……んん」
「ねぇ、起きて」
掛布の上から肩を軽く揺さぶると、漸く男はうっすらと目を開けた。頭の側に置いてあった眼鏡を手繰り寄せて掛け、竜一の姿を確認し、男は首に手を当て緩慢な動作で起き上がった。変な場所で寝ていたせいで首が痛むようで、しかめっ面をしてしきりに擦っている。
「いててて、クビ、寝違えたかな……」
ぐるりと首を回すと、ゴキっと音が響く。男は竜一を見上げて漸くはっきりと目を開けた。
「おはよう、……ございます」
「おう、おはよう。あんた、もう起きて平気なのか?」
「え?」
起きるのに平気も平気じゃないもない。
意味がわからず口をパクパクさせている竜一の前にのっそり立ち上がると、男はまっすぐ腕を伸ばし「どれどれ」と言って熱を測るように竜一の額に手を当てた。予想外の行動に竜一は固まっていた。
男らしい大きな掌は温かくて、ドキッとする。しかし、急にそんな事をされて驚いている竜一の様子は目に入っていないようだ。
「んー。まだ、ちょっと熱いかな」
「熱いって、俺?」
「他に誰がいるんだよ」
男は気合いを入れるように言葉とも言えないかけ声を口にし、全身をほぐすように腰に手を当てて軽く背筋を伸ばした。
「よーし、起きっか……」
完全に起きるまでにこうして時間が掛かるのはおじさんの証拠だぞと思うが、まさかそんな事は言えない。額を触られてから微動だにしない竜一の顔を覗き込むと、男は竜一の額を指で弾いた。
「いてっ、な、何」
「いや、ぼーっとしてんなーって思ってさ」
「……」
男が側に脱いであったスエットの上下を着ながら話しかけてくる。
「ゆうべは、急に倒れるから焦ったぜ、熱もあったし、話しかけてもはっきり返事しねぇし。起きたら病院へ行けって言おうと思ってた所だ」
「ごめん、俺覚えてなくて、またそんな迷惑掛けてたなんて。どうしよう……。それに、俺がベッドで寝たせいで場所無かったんだよね? 重ね重ね、ごめん……」
「俺はたまにソファで寝ることあるし、あんたがいたからってわけじゃねぇよ。気にすんな。それより、身体の具合はどうだ? 昨日の晩よりは、顔色も良くなったみてぇだけど」
「少し……頭が痛いけど別に問題ないよ」
「他は?」
「今はそれだけ」
「そうか。んじゃ、病院は行く必要ねぇか。だいぶ良くなって良かったな。あ、そうだ。夜に解熱剤飲ませたんだ。朝飯食ったらもう一回飲んどけよ。あと俺の部屋着かしてやるからとりあえず着とけ」
「え、ああ、……うん」
すぐに帰ると言おうと思ったけれど、男は当然まだいるという前提で話していた。それに案外世話やきなようだ。
とりあえず貸してもらった部屋着に着替えてみたはいいものの、サイズがあまりに違いすぎて洒落にならない状態だった。
スウェットのズボンは二段階ほど捲り上げてなんとかなったが、上に至っては肩は落ちているし、袖はとんでもなく長い。
着替え終わった竜一を見て、男は吹き出した。
「おいおい、酷ぇ状態だな。あんた、いつもはSサイズ着てんのか?」
「Sじゃない、Mサイズだよ。これ、何サイズ?」
本当は、メーカーによってはSサイズの時もあるけどそれは言わないでおいた。男としてのくだらないプライドだ。
「XL。まぁ、いいんじゃねぇの。大は小を兼ねるって言うだろ」
「……」
「歯ブラシとかもかしてやるから、こっちこい」
「……有難う」
一通りの朝の支度を済ませ食卓へ着く。男が機嫌良く鼻歌を歌っている。
自分を含めて不思議な光景だった。
男の匂いのする部屋着を着て、男の部屋で男が用意してくれた朝食を食べる。昨日の自分には想像できなかった状況だ。
焼いただけのパンとコーヒーのみの朝食。
あまり食欲がないのは、熱があるからなのだろう。しかも、食パンに塗る物は甘い物ばかり。マーマレードに木苺、ミルクバターにピーナッツバター。
「もしかして、甘党なの?」
目の前のジャムを見つめたまま聞くと、男は「別に? どうして?」と返してきた。どうしてって目の前の塗る物が全て甘い物だから。それ以外にあるだろうか。
「いや、沢山ジャム系があるけど全部甘い物だから」
「あー、あんた甘いの食えないのか?」
「ううん、そういうわけじゃないけど」
「俺も別に特別甘党ってわけじゃねぇよ。色々客から貰うから消費してるだけだ」
「そうなんだ、なるほど」
そう言う理由ならばわかる。どれにしようか迷ったが、なんとなくミルクバターを選んで食パンに塗ってみた。ちょっとだけカスタードのようないい香りがする。
暫くして半分ほど食べ終えたところで、向かい側に座っている男がじっと自分を見ているのに気付き、竜一はパンを飲みこむと「どうかした?」と男に顔を向けた。
「いや、ゆうべのあんたは、かなり色っぽかったなって、思い出してた所だ」
思わず飲みかけた珈琲を吹き出しそうになり、竜一は軽く噎せた。
もしかして、覚えていないけれどやはりこの男と寝たのだろうか、絶対無いとは言い切れない所がもどかしい。竜一は男の顔と食べかけのパンを交互に見て頬を赤く染め、思いきって本人に聞いてみることにした。
「その……昨日ってさ……」
「ベッドでの話か?」
「え、まぁ。ベッドって言うか、その時の話だけど……。着替えさせてくれたんだよね?」
「ああ、スーツのままってわけにもいかねぇからな。取りあえず脱がせてベッドに押し込んだ。まずかったか?」
「ううん……。それは助かったんだけど……。その後は?」
「後って言うと……ああ。……あんたがその唇で、もっと欲しいってねだってきて大変だった時か」
「う、うそだ」
「本当だって」
「俺が、自分でそう言ったの?」
「ああ、言った言った。「凄くかわいてるんだ。もっと欲しい……早く……」って」
声色まで変えて真似てみせる男を前に、恥ずかしくて顔から火を噴くかと思った。
「……あ、えーっと……、そ、それは」
血の気が引く音が聞こえてきそうになる。
どうしよう、とでもいう表情で頭を抱える竜一を見て、男はニヤニヤとからかうような笑みを浮かべ、俯く竜一の目の前を人差し指でトントンと叩いた。竜一は目を合わせないまま顔を上げた。
「喉が渇いてたんだろ? 熱あったしさ。解熱剤を、コップの水で飲ませた時の話だ」
――……え。
「解熱、剤……?」
「お、なんだ? 俺とヤっちまったとでも思ったのか?」
「なっ! ち、違う! でも……、覚えてなくて、その……。変な言い方するから」
「安心しろ。病人を襲うほど、飢えちゃいねぇよ」
竜一はホッとしたような表情を浮かべると、残りのパンを口に入れてコーヒーで飲みこんだ。先程からちょくちょくからかわれているのが納得いかないけれど、これはこの男の性格なのだろう。今まで自分の周囲にいなかったタイプなので、接し方に戸惑ってしまう。
「有難う……。昨日といい今日といい、俺、迷惑掛けっぱなしで……。その、何か御礼出来ないかな。俺で出来る事なら、なんでも言って欲しい。あ、金はあんまりないんだけど……」
「あー……」
男は暫く考えた後、椅子にもたれ掛かり天井を仰いだまま口を開いた。
「そうだなぁ……」
「……」
「じゃぁ、……一ヶ月。俺の恋人になってくれ」
「……ん? 恋人??」
予想もしていなかったお願いにビックリして、竜一は何度も瞬きをした。
「恋人って!? どの……恋人??」
「恋人は恋人だろ。『どの』も『あの』もねぇよ」
男が苦笑した後詳細を告げる。
「その一ヶ月で、俺の事が好きになれねぇなって思ったらハッキリ言ってくれ、その時は恋人関係を解消する。どうだ? お試し期間ってやつだ」
「そんな急に言われても。……あなたのことは、いい人だって今も思ってるけど……。俺、今はまだ、新しく恋愛をする気にはなれないんだ……。それに、あなただって急にそんな気になれないんじゃないの」
「だから一ヶ月あるんだろ? 別にあんただけの猶予じゃない。俺も同じ期間をかけて考えるんだ。一ヶ月は長いぞ~。720時間もある。そんだけあれば、考える時間は充分だろ? 一ヶ月後、どちらかが無理だって結論なら」
男は指で恋人同士を表すように交わらせ、言葉の最後で決裂を意味するように指を離した。
「どうして? そんな事……、俺がまた変な気を起こさないか心配だから、同情してくれて、」
「そうじゃない」
「じゃぁ、なんで」
「昨日言ったろ、俺があんたを治してやるって。その期間で何が出来るかわからねぇけど、やってみる価値はあると思ってる。あんたが俺を、受け入れてくれるならだが……。まぁ、本当にあんたにお願いしたいことは別にあるんだが……、それは一ヶ月後に話す」
「今じゃダメな話なの?」
「ああ、今はまだな……。ちょっとわけがあってさ。俺のお願いをあんたに話すかどうかは、保留にしておいてくれ」
まだ話せないお願いがなんなのかも気になるが、その前だ。
もう恋愛はしないつもりでいた。今だって自信が無いし、こんなイレギュラーな形で交際を始めるのも初めてでどうしていいかわからない。でも、男の言葉を信じるなら、どうしても無理そうなら一ヶ月後に打ち明ければちゃんと聞きいれてくれるはずだ。
散々迷惑を掛けてしまったのだから、一ヶ月後に話してくれるという本当のお願いを聞くまでの間、試すぐらい引き受けてもいいのではないかと思った。
「わかった。出来るだけ頑張ってみるよ」
「よし! じゃぁ今から俺たちは、恋人同士(仮)だ。いいな」
「うん、なんか、改まって開始宣言されると違和感しかないな……。しかも(仮)って、具体的に恋人になってなにをすればいいの?」
男が「ん?」と不思議そうな顔をして煙草を咥えた。
「なにって、あんた付き合ったことあるんだろ?」
「それはあるけど」
「何も特別難しいことをしようって言ってるわけじゃねぇぞ? 外でデートしたり、一緒に飯食ったりさ、そういうのでいいんだよ」
「あ、……そうだよね。うん、ごめんおかしな事聞いて」
「新鮮だな……」
「え? なにが?」
「あんたの反応。根っから真面目って言うか、見てるだけで面白い」
「失礼だな。珍獣扱い?」
思わず苦笑する竜一に、男は目を細めた。
「そうじゃねぇって。すげーいいなって、思ったんだよ。よし、んじゃ。俺も真面目に、自己紹介しとくか」
男がおかしそうに笑う。
「今更? でも、そうだね。じゃぁお先にどうぞ」
「俺の名前は、きりのたかゆきだ。字は桐野 恭征って書く。オモチャの修理屋をやってる」
そこら辺にあった紙に恭征という字を書いて、竜一の目の前に差し出す。随分達筆な文字で驚いた。と同時に当時貰った名刺を思い出した。
「あっ、思い出した。名刺を貰った時にも、芸能人みたいだって思ったんだ。これでたかゆきって読むの珍しいし」
「そうか? 俺もあんたの名前は何となく覚えてるけど、一応聞かせてくれ」
「うん。俺は、さくまりゅういち。佐久間 竜一って書く。仕事は印刷会社の営業をやってる。ってこれも知ってるよね。自己紹介って……他に何を話せばいいんだっけ?」
「んー。趣味とか? 特技とか」
「特技!? それは履歴書だよ」
「それもそうだな」
お互いの自己紹介なんて必要なかったのではないかと顔を見合わせて笑った。
「ところでさ……」
桐野が改まって真顔で腕を組む。なにか深刻な話? そう思って言葉を待っていると、何度か髪をかき上げた桐野がまっすぐ見つめてきた。
「俺って何歳に見える?」
竜一は思わず吹き出した。何を言われるかと思えば、本当にくだらない話題だ。
「そういうの、職場のおじさんが若い子にいう定番の台詞だよ」
「そうなのか?」
「うん。でも、そうだなぁ……。45ぐらい?」
「……45、ねぇ……」
桐野の顔が不満げに曇る。竜一は慌てて大幅に下げて言い直した。
「うそうそ。39ぐらい?」
「一気に6歳も下げて、それ、営業トークだろ」
「う、……いや……」
「まぁ、いいや。俺は41だ。そういうあんたは、いくつなんだ?」
「俺は30だよ、もうすぐ31だけど」
「へぇ……」
桐野がつまらなそうに「一回り近く下か」と呟く。45と最初に言われたのを気にしているのか、「やっぱり髪、切るか」と独り言のように呟く桐野が可愛く思えて、竜一は自然に笑みを浮かべていた。
「じゃぁ、俺からの質問もいい? 桐野さんは結婚とかしてない……よね?」
「恭征でいいのに。まぁ、そこは任せるけど。んで、いきなりプライベートにつっこんでくるんだな」
「だって、重要な事だろ。仮とは言え、その……こ、恋人の間は……」
「別に聞かれて困ることもないからいいけど。俺は見ての通り一人暮らしだ。戸籍上のバツもなし。でも、どうしていちいち聞くんだ? 結婚してないことぐらいは、見ててわかんだろ」
「深い意味はないよ。なんとなく……確認したかっただけ」
意味はある。自分はまだこの前の恋愛を引き摺っているからだ。見ていてわかるどころか、付き合っていてもわからなかったのだから。独身に見えていても、既婚者かも知れない。そんな疑心暗鬼に取り憑かれている。はっきりとこうして最初に聞いたのは安心したかったからだ。
「あんたが安心したんなら、それでいいけど」
見透かされたようにそう言われ、少しだけ恥ずかしかった。桐野は、失恋したばかりの竜一を気遣ってか、その手の質問は一切してこなかった。
朝食を摂った後、暫く他愛もない話が続く。
こうして誰かと一緒に食事をしてのんびり時間を過ごすのは久し振りだ。
PCのデスクトップに表示されているデジタル時計をチラッと見ると、もう十一時近くなっていた。
今日は休日だが明日は違う。
普通の日常へ逆戻りしてしまったからには、明日からまた仕事があるのだ。
以前はそれすらも考えるだけで憂鬱だったが、今はそこまで嫌じゃない。うまくいかない事が多いけれど、もう少しだけ頑張ってみてもいいかと思えたのは桐野と出会ったからに他ならない。
何せ一ヶ月先のお願いを聞くという理由も出来てしまったのだから。
こんな出会いなんて要らなかった。そう思っていたけれど……。
出会えた事に感謝、今は素直にそう言いたい気分だ。
そんな事を考えていると、聴き慣れない着信音が耳に飛び込んできた。桐野の携帯からだ。
「悪ぃ、仕事の電話だ。ちょっと出てくる」
桐野は側にあった携帯を持つと、少し離れた場所へと移動した。プライベートと仕事はきちんと分けるタイプのようで、電話で会話をしている桐野の口調は丁寧で先程までとは全然違う。その声を耳にしながら、竜一は当時、桐野と仕事で会っていた頃を思い出していた。
まるで別人のようだと思ったのは、あの時の桐野が仕事モードだったからというのもあるだろう。当時は、エリート然とした彼に憧れたものだが、自然体の彼もまた別の魅力があると思う。全く好みのタイプではなかったはずの桐野に対して、小さな好意が芽生えていると自覚してしまった瞬間だった。
電話を切った桐野が戻ってくると、竜一は顔を上げた。
「仕事、何か問題?」
「いや、大丈夫だ。部品を発注していた業者からだったんだが、複製のサンプルを見に来て欲しいんだと。夕方にでも行ってくる」
「俺も、昼には自宅へ戻るよ。いつまでもここに世話になっているわけにもいかないし」
「そうか……。もう、平気か?」
「……うん、大丈夫」
何が平気なのか、言葉で言われなくてもわかる。不安げな表情を浮かべる桐野が、心配するのも無理はない。出会ったきっかけがあんな状況だったのだから。
竜一は、笑みを浮かべて桐野をみつめた。
「明日から、俺もまた仕事行かなくちゃ」
明日のことを口にする竜一に安心したような桐野は「そうか」と短く返して、「頑張れよ、ほどほどにな」と付け加えた。
「うん。もう少し頑張ってみようと思う。――桐野さん、」
「ん?」
「ちゃんと言えてなかったけど。その……有難う。――俺に、明日をくれて」
意表を突かれたような桐野が照れたように頬を掻く。言葉は返ってこなかったけれど、静かに椅子から立ち上がった桐野が隣にきて食卓に手を突いたまま腰を屈めた。
「桐野、さん……?」
ゆっくり近づいてくる顔を見上げる竜一が、鼻先がくっつく直前で焦って口を開く。
「ま、待って。恋人(仮)は、いきなりキスもあり?」
「もちろん。ちなみに、キスの先もありだ」
「勝手に決めるなんて反則だ。聞いてない」
「じゃぁ、どこまでOKにするか話し合うか? キスした後でな」
笑いながら悪戯に唇を重ねてくる桐野に、竜一はギュッと目を瞑った。この歳でキスぐらいでどうこう思っているわけではないが、こんなにドキドキするのは久し振りだった。桐野からの口付けは、輪郭を見失うほど柔らかで、蕩けるように甘い。
ゆっくりと繰り返される口付けがとかれると、桐野は冗談っぽく「で、どうする? キスはOKにする?」と笑った。
一ヶ月の間で好きになれるかどうか決めるという約束のはずなのに、好きかどうかを決める前にこうしてキスをしてしまうなんて、順序が逆のような気がするが……。強引な桐野の口付けがちっとも嫌じゃ無い自分がいた。
竜一が、唇に指先をあてて下を向く。
「キスまでなら……」
「その先は?」
「それは……、まだわからない。その時考えさせて欲しい」
「了ー解。ああーあ、しくじったな。昨日、寝込んでるあんたを、襲っちまえば良かったか」
「酷い男だな」
「だな。自分で言っておいてなんだが、最低だ。こういう男には気をつけた方がいいぞ?」
「もう、遅いよ」
そう言って竜一は笑った。
冗談交じりの優しい言葉を紡ぐ、大人の男の余裕。
粗雑な見かけからは想像つかないほど桐野の言葉選びは洗練されていて、丁度いい場所にストンと落ちる。誰かと話すのがこんなに楽しいと思えるのは久々だった。
あと一ヶ月、(仮)ではあるけれど、真剣に向き合っていこうと思う。結果がどうなるかはわからないけれど、きっと何かが変わる。そんな予感がした。
COUNT0….|創作BL小説|メンズラブ|
シリーズ『俺の男に手を出すな』メインの長編連載小説サイトです。病弱、ホスト、バンドマン、医者、眼鏡、強気受け、リーマン。