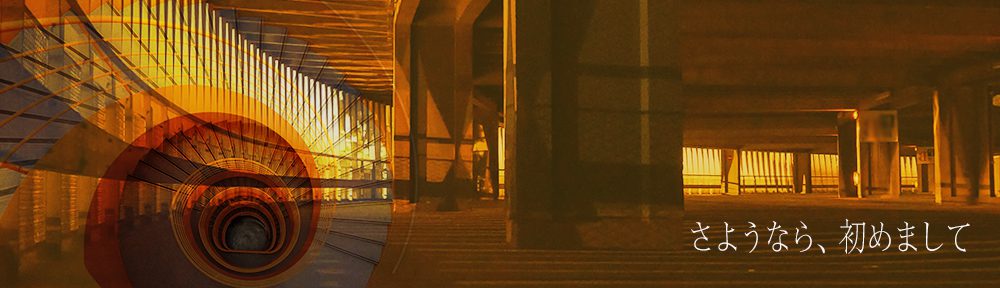──memory6──
仕事に区切りを付けた竜一は、帰り支度をしながら会社の窓から見える外を何気なく眺めた。まだ外灯が灯る時間にもなっていない夕方だ。定時をまわってすぐ、こんな早い時間に退社するのはここ一ヶ月で数えるほどしかない。
窓から視線を戻し、もう一度手帖を開く。
「大丈夫そうだな……。これと、これと……。ああ、ここは帰ってから自宅で赤入れよう……」
ブツブツと声に出しつつ確認する。問題がありそうな他の件は先に片付けたし、明後日までに初校を入れられればどうにか間に合う。
パタンと手帖を閉じて頷いていると、隣の席の同期に声をかけられた。
「佐久間、今日あがり?早いな」
「あー、うん。今日はちょっと用事があるんだ」
「なになに、もしかしてデート?佐久間も隅に置けないなぁ~」
「まさか、そんなんじゃないって。友人と会うだけ。そっちは?まだかかるの?」
「俺はまだまだかな。これもう三校目、ありえねーだろ」
「うわ、ご愁傷様」
もう、そう返すしかない。三校目というのは、平たく言えばクライアントから三回ダメ出しをされた状態である。次こそOKを貰えますように、祈るような気持ちで竜一は彼の肩を労うようにポンポンと叩いた。
「ああ、ところでさ、聞いておきたいことがあったんだけど、この件」
PC画面に向かって同期が指している場所を見る。
「それがどうかした?」
「いや、これ、お前の今回の大口だよな。……納期早すぎない?これ、絶っ対制作にどやされるって」
確かに他の件と比べて相当に急ぎの案件だ。しかし、それは竜一もわかっていてやっているのだ。
「仕方ないんだ。この納期で出来るって他の所では言われたらしくてさ。間に合わないならそっちで見積もり出し直して貰うって言われて」
「へー……他のって、また例のあそこ?もうそれ、脅しじゃん。言っちゃえよもう、『うちはうち!出来ないもんは出来ません!』って」
「お前それ、その大口案件で言える?」
竜一が眉を寄せて苦笑する。言葉を詰まらせた同期は、苦笑いをこぼしながら肩を落とした。
「言える!、と言いたいけど……言えないよな……。俺がお前でもこの納期で受けてくるわ」
「だろ。とにかく前倒しで頑張るよ」
比較的新しい印刷会社だが、納期がやけに早い競合他社が出現したせいでここ最近こういう事態は珍しくない。早いのを売りにしているだけでなく、デザインも専属の一流デザイナーを雇っているだけあって安心して任せられる。
そこと比べられると昔ながらの印刷会社で、デザイン部署も出来たばかりで研修をしたとは言え普通の社員がやっているうちとは明らかに差が出てしまう。せめて納期だけでも急ぎを任せられるという部分で差を出したくなかった。
だけど、自社の本来の強みは早さではなく、印刷物の綺麗さだ。客が希望する以上の正確な色で仕上げる。その為に色校から本紙校正まで、他の会社がする事を全て二度行い徹底した調整を行っている。だからなのか、色が命の服飾系や食品・化粧品会社の取引先が多い。
「うちはうちのやりかたでやるしかないんだから、出来る限りの事はしたいんだ。見積もりと同時に制作にも話はして、もう渡してある。まぁ……小一時間怒られたけどね」
「うっわ、悲惨。俺らに言わないで、直接客に言って欲しいよな~。「営業はクレーム処理班じゃねぇぞ」ってハッキリとさ。板挟みになるこっちの気持ちもわかれよって言いたくなる」
同感だ。全部その通りだという気持ちはあるが、文句を言ったところでその仕事が早く片付くわけでもない。竜一は短く息を吐いて袖を通したコートの襟をたてた。
「俺が怒られるだけで、引き受けてくれるんだから我慢するよ。大口だし。これで今月の売り上げがだいぶ違うから、そう考えたら多少の事は我慢出来る」
「まぁ、それしかないもんな。桁違いの部数発注してくれてあざーっすって気持ちで行くしかないか」
「そうそう。それにさ……」
「うん?」
「今回のコレ、クリスマスシーズンにデパートの化粧品売り場に大々的に置かれるんだ。自分が手がけたパンフレットがうまく出来て、日本中の人が手にとる。それを見たいなって。実際に見るとやっぱり嬉しいからさ」
「佐久間、お前ほんっと……。……いや。そういう所、俺も見習わなきゃだな。ああ、引き留めて悪かったな、デート楽しんでこいよ」
「デートじゃないっていってば。じゃぁお先。お疲れ様」
「お疲れ~」
鞄を持って廊下へ出る。
古いビルなのでエレベーターが一台しかなく、しかもいつも運悪く最上階で止まっていたりするので竜一は最初からエレベーターを素通りして階段へと向かった。
営業成績がここ最近ずっと低迷していた自分に舞い込んできた久し振りの大口。
それは、会社にとってかなりの利益になるだけではなく、竜一を重圧から解放するものでもある。
自分がそれを任されていると感じれば、その責任感でさえ心地よい。まだ先になるけれど、無事に終えた後の達成感は何物にも代えがたい。そんな忘れていた気持ちを、思い出させた。
印刷会社へ入社した動機は、小さい頃から写真集や色鮮やかな図鑑が好きで、人の目を楽しませる事が出来る印刷物が作りたかったからだ。自分の感性で惹かれた印刷物を昔からスクラップする癖があった。
ジャンルは問わない。惣菜屋のチラシから婦人服の広告までなんでも切り取ってスクラップしていた。今でも自宅のどこかに保管してあって中々捨てられない想い出の品だ。
実際、思っていたのと違い写真集を手がけることは未だないけれど、それでも魅力的な写真をそのままに印刷で再現して物を作り上げる。その過程に自分が携われることが嬉しかった。
竜一は今回の初校を脳内に引っ張りだし、完成予想図を思い描く。誰もが手に取りたくなるような鮮やかな発色、某化粧品ブランドの口紅をメインとした冬のカタログだ。
実物の商品やその写真素材から受けたイメージはまさにクリスマスを思わせる真紅。
豪華でちょっと日常から離れた贅沢な時間。完成したカタログがそのイメージと合致した瞬間、それはもう作品と呼んでもいいだろう。こんな事を考えるなんて、桐野と出会って影響されているのかも知れない。
ほんの少しだけ、昔の自分を取り戻せた気がして竜一は一人小さく笑い社屋に背を向けて歩き出した。足取りはいつもよりずっと軽やかだった。
歩いている途中で、外灯が灯りだした。
夜と夕方の境目、この瞬間、一日の僅かな時間を今日も自分はこうしてちゃんと生きている。そんな当たり前のことを考えながら、地下鉄の階段を下りる。
桐野と出会ってからもう一週間が経った。
恋人(仮)になったとはいえ、学生でもないので毎日会うわけじゃない。桐野に会うのは初日に泊まった日以来初めてだ。
待ち合わせの駅は普段使っている路線と同じ地下鉄の駅なのですぐに着くだろう。
何駅か電車に揺られ、降りた地下鉄の駅から地上へと出る。
待ち合わせ時間より早く着いてしまった竜一は、改札から出てくる人物の中から桐野を探してみたが、今の所まだ到着していないようだ。
一ヶ月は結構長いなと思っていたけれど、今日になるまでに電話で話したのが2回ほど。それも大した意味の無い雑談を楽しんだだけである。このペースでいたら後二回会うかどうかさえ怪しい。そうこうしているうちに桐野の言う約束の期限になってしまう。そう考えると、一ヶ月なんて本当は短いのかもしれない。
竜一は携帯を取りだして時刻を確認したあと、ポケットからミントタブレットの缶をカシャカシャと振って二粒を掌に出した。ころころと転がる真っ白な二つの錠剤は綺麗に別れて掌の上で左右に散った。
これをみるとどうしてもあの夜の事を思いだしてしまう。
桐野と今日会うのを楽しみにしているのは本当の気持ちだけれど、それと、新しい恋愛を始めることはまた別の話だ。そちらはやはりまだ答えは出せそうにない。
――この先、どうなるのかな……。
竜一が指先の方へ転がったタブレットを口に入れようとした瞬間、急に背後から背中を叩かれ、驚いた拍子にミントタブレットは地面に落下した。ああ……、二粒無駄にした。
「お兄さん、今時間ある?いい店に連れて行ってあげようか」
声の主は当然わかっているので、竜一は確かめもしないまま声の方へ振りむいた。当然そこには桐野がいて、悪戯な笑みを浮かべている。
「桐野さんがビックリさせるから、食べ損ねちゃったよ」
開口一番そう言うと、桐野は「ナンパに関してはスルーかよ」とツッコんできた。竜一は笑って一応桐野の言葉を拾う。
「それ、ナンパなの?胡散臭すぎてビックリ」
「どこが胡散臭いんだ?普通のナンパだろ」
「そうかな?いい店連れて行くとか、怖すぎるし。ついて行くのに身の危険を感じるよ」
「酷ぇな、それじゃまるで俺が人さらいみたいじゃねぇか。じゃぁ、あんたなら何て誘うんだ?そう言い切るからにはお手本とやらがあるんだろ?」
「えっ、お、俺は、ナンパとかしたことないから……。でもまぁ、「今時間あるなら、お茶しない?」とかなんじゃないのかな」
「そんな、ふっつーの誘いで乗ってくる奴、今時いるのかよ」
桐野は呆れたように首を振った。
「桐野さんの誘い方よりは、成功率高いと思うけど」
「言うねぇ。今日の所は、そういう事にしておいてやるか」
桐野はそう言って笑った。今日も相変わらずのラフな格好だったが、最初に会った時よりはずっと小綺麗な格好だ。竜一の手にしているミントタブレットの缶を見ると、桐野は嫌そうに大袈裟に眉を顰めた。
「おい……、そんなもん、食ってんのかよ」
まるでゲテモノを食べようとしているみたいな言い種だ。
「人と会う前のエチケットだよ。 桐野さんも、ひとつ食べる?」
「冗談言うな、俺は絶対いらねぇ」
『絶対』の部分をめちゃくちゃ強調したその言い方がおかしくて竜一はクスクスと笑った。
「だよね」
あの夜、ミントタブレットを一気食いして吐いた事がトラウマになっているらしく、桐野は「いいから、とっととしまえ」と手で払うような仕草をした。
落ちた物は諦めて、新しい物を口に入れると強力なミントのせいで口内の温度が一気に下がった。
「ふぅ、さーみぃ。今夜も冷えんなぁ……」
そう言って桐野は両方の手をポケットに入れ、長身の背を丸くする。
「もっと厚着してくればよかったのに。風邪引くよ?」
「着込むのが嫌いなんだよ。店に入ったら暑くて脱ぐんだし、脱いだり着たり巻いたり面倒だろうが」
「巻いたり?ああ、マフラーの事?」
「そう」
「そこまで面倒くさがりとか、珍しいね」
「その点夏はいいよなぁ。俺は自宅ではパンツのみで過ごしてる」
「へ、へぇ……。でも、人が来たらどうするの?」
「そりゃ、なんか着るだろ。別に露出狂じゃねぇんだし。って、それよりあんた、今日は残業しなくてよかったのか?まだこんな早い時間だけど」
並んで歩き出した桐野が、隣に並ぶ竜一を些か心配そうに見る。今日の待ち合わせ時刻を決めたのは竜一だ。
「うん、仕事はまだ残ってたけど、期限的には余裕がある物ばかりだったから大丈夫。たまにはこうして息抜きも必要だから。少しずつ意識を変えていかないと、何も変わらないなって。俺なりに考えてるんだ。結果がどうなるかは……、わからないんだけどさ……」
「結果は結果。その過程が重要なんだから、間違ってねぇよ。もし失敗だったーってなったら俺が慰めてやるから安心しろ」
「失敗する前提は困るな」
竜一は、眉を寄せて困った顔のまま苦笑した。
「あんた今、俺と会うのが息抜きになるって言ったか?」
「え?あ、うん」
「へぇ、サラッと嬉しい事言ってくれるな」
「えっ……。あ……う、うん。一人よりは、桐野さんと話してると楽しい……から」
「そりゃ、どーも。光栄な事だ」
何も考えずに言ってしまったが、今の言い方だと一人で浮かれているみたいで恥ずかしい。まだ出会ってそんなに経っていないのに、今日会う日まで、何度も桐野の事を考えてしまっていると知ったら、桐野はどんな顔をするだろうか。
恋愛感情と好奇心。今はまだ多分半々ぐらいだ。桐野の色々な事を自分は知らないけれど、もっと親しくなって友人としてでも関係が続けばいいなと思う。
竜一は隣をチラッと見た。
街で改めて見てみるとやはり桐野は目立っていた。
他の誰よりも背が高いし、それと、お洒落とは言い難い格好でも、どこか不思議と下品な部分がない。これは彼の最初から持つ雰囲気のような物が関係しているのだろう。
地味なスーツ姿の自分と並んで歩いているのを見て、周囲にはどう見えているのだろうか。友人?仕事関係の仲間?そんな事を気にしているのは自分だけっぽいが。
相変わらず少しずれた位置にかけている桐野の眼鏡を見て、竜一は前から聞こうと思っていたことを急に思いだした。
「ねぇ、桐野さん、どうしていつも眼鏡を上にあげないの?それじゃ視界が見づらくない?」
「ああ。これか」
「うん、何か理由が?」
「あるっちゃあるし、ないって言えばないかな」
「なにそれ」
竜一が笑うと、桐野は歩く速度を僅かに落として横断歩道の手前で止まった。ゆっくりと息を吐き、どこか切なげな表情を浮かべて少しだけ目を伏せる。
逆の信号が青になり一斉に動き出す人波の中には、早足のサラリーマン、腕を組んでいる恋人同士、ヘッドフォンをして音楽を聴き入っているような男子高校生、買い物途中の自転車にのる主婦。様々な人がいて、誰一人として同じ人間はいない。
信号待ちで足を止めている中、桐野は、竜一の方へ振り向いておかしな事を言った。
「今から30秒でいい。目の前の街を観察してみな」
「え?……う、うん」
竜一は桐野に言われたとおり、様々な物を目で追い、視線の先にある文字を読み、色を認識する。
同時に耳から入ってくる音を聞きながら、脳内では情報が忙しなく交差していた。
あの車、社用車と同じ車種だなとか、薬局から流れてくる曲が昔CMに使われていた物だなとか、特に意識しなくて流れ込んでくる。
色取りどりの電飾看板や、店全体が広告のようなクリーニング屋、その看板を見ればデザインより目を引く配色を優先したのだろうと想像がつく。見慣れたファーストフードの店構え、シャッターが閉まった何をしているかわからない店。
洪水のような情報が見える範囲だけでも溢れていた。
「はい、そこまで」
ドラマの撮影シーンを撮る監督のように、桐野がストップをかけ、竜一は我に返った。
「えっと……。今のは?」
桐野が顔を覗き込み、尋ねてくる。
「どうだった?」
「どうって……。いっぱい人が居るなとしか。後、これは職業柄かも知れないけど、店が結構多くて案外様々な色が使われてるんだなって事とか。言葉ではうまく言えないけど、沢山の事を考えたよ」
「そうだろ?たった30秒だ。ただ眺めてるだけでも、それだけの情報があんたの中に取り込まれる」
「そう言われれば、そうだね」
「その情報の全てが、今のあんたに必要な物だったと思うか?」
「……え」
「俺は目が悪いから、裸眼じゃほとんどの視界がぼやけちまう。だけど、全部がくっきり見える必要はないと俺は思ってる。全ての情報を受け入れてたら疲れちまうだろ」
――……それは。
竜一は周囲をもう一度見渡した。
「俺は視力が良いからその感覚はよくわからないけど……見えているのが当たり前の世界だから」
「まぁ、人それぞれだけどな。俺の場合、必要な情報や見たいと思った物は視線を下げて眼鏡を通して見りゃいい。他のことなんて、だいたいわかってりゃそれでいいんだ」
そんな意見を聞いたのは初めてで、桐野はやはり少し考え方が人とは違うなと思った。
でも、そう言われてみると、確かに一理ある。運転時などは別として、支障が無いなら全てを把握する必要は全く無い。
情報の氾濫する街や人の多さに疲れるのは、全てを見て、理解しようとしてしまうからなのだろう。
それと、桐野が遠回しに「見たくない物」があるのだと言っている気がした。その見たくない物は多分、実際の”なにか”だけではないのだろう。竜一の胸の奥が静かにざわついた。
「桐野さんって、ちょっと他の人と違うよね。悪い意味じゃなくて、考え方っていうのかな……そういうのが、少し変わってるって言うか」
「自分じゃ、わかんねぇな。普通だよ」
桐野は笑うと、視線を下げて竜一の方をじっと見つめた。
「俺ぐらいでかいと、必要な物はほとんど目線の下ってせいもあるかもな。あんたの顔を見たい時もこれで十分だ」
「確かに、俺そんなに背が高くないから。でも、これでも170はあるよ。最近測ってないけど」
「そっか。俺ももう10年ぐらい測ってないから縮んだかもな」
「まさか、そんな歳じゃないでしょ。最後に測った時はいくつあった?」
「190だな」
「凄い。やっぱり、それぐらいはあるかなって思ってた。便利そうで羨ましいよ」
「結構頭ぶつけることも多いけどな」
桐野が苦笑する。
今日は桐野がよく言っているという居酒屋へ連れて行ってもらう予定だ。暫くくだらない事を話しながら歩いていると、漸く飲み屋街へ辿り着いた。
COUNT0….|創作BL小説|メンズラブ|
シリーズ『俺の男に手を出すな』メインの長編連載小説サイトです。病弱、ホスト、バンドマン、医者、眼鏡、強気受け、リーマン。