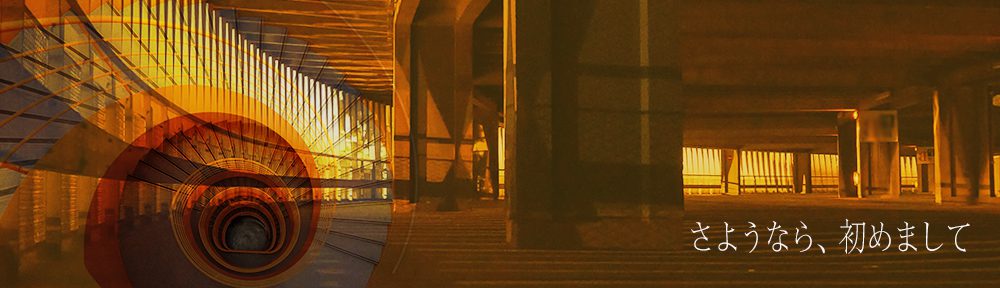──memory7──
金曜の夜、時刻は丁度会社員が帰宅する頃なので、どの店も賑わっているようだ。
もくもくと煙が店から溢れ、それにのって焼き鳥屋からいい匂いが漂ってくる。昼飯を抜いたわけでもないのに、食欲をそそるその匂いに小さく腹が鳴った。
周囲の賑やかさで桐野に聞こえなかったのが幸いである。
「ああ、ここここ、着いたぞ」
桐野が足を止めたので、竜一も同じく足を止める。よくみる暖簾によくみる引き戸奥の光景、特別に他と違うところは見当たらない。昔からある居酒屋のようで、入り口を入るとすでに2組の会社員らしき男達が飲んでいた。会社の飲み会にもほとんど参加しないので、こういう雰囲気も久し振りだ。
それにしても、わざわざここまで連れてきた桐野がこの店を選んだ理由は今の所わからなかった。
桐野は勝手にカウンター席の一番端へ向かい、竜一を奥へと座らせて自分も腰掛けた。まるで指定席のように馴染んでいる様子に、理由が浮かび上がる。この店は桐野の行きつけといった所か。
「いらっしゃい。桐野さん久し振りじゃない。元気にしてた?」
おしぼりを運んできた若い女の子が、桐野へ笑いかける。竜一の予想は当たった。
「よぉ、久し振り。俺も忙しいんだよ。そうしょっちゅう飲んでるわけにはいかないって」
「忙しいのはいい事よね、このご時世有難く思わなくっちゃ。うちは相変わらずよ」
そう言った女の子の台詞に被せるようにして、目の前のカウンターからオヤジの大きな声が届いた。よくみるとそっくりでどうみても娘だ。
親子で経営をしているのだろう。
「恭征か、随分顔見せねぇから、どっかで野垂れ死んだのかと思ったぞ」
「勝手に人を殺すなよ。まだ野垂れ死ぬような歳じゃないっての」
桐野が苦笑しながら竜一の方を見るので、竜一は慌てて「初めまして」と笑みを浮かべた。
なんだろうこの感覚。自分には行きつけの店なんてものは存在しないので、今までのやりとり全てが芝居を見ているような感覚だ。その芝居の中にいる自分はエキストラか、それ以下か。竜一がそんな事を考えていると、声をかけられた。
「おう、恭征のお友達さんかい?ゆっくりしていってくれ」
「はい」
「んじゃ、これな。ほら」
カウンター越しに腕が伸びてきて、何も言わなくても勝手にお通しが出された。
しかし、お通しと言うには些かボリュームがありすぎる。手早く作れるだし巻き卵と鶏皮の唐揚げ。これは普通なら頼んで出てくるメニューなのだろう。頼んでいないのにおかしいなと思っていると桐野の説明が入った。
「食っていいぞ。最初はこの二つを必ず出して貰うんだ。俺が好きだから。さてと、あんたは何にするんだ? これメニューな」
「そうなんだ。どれにしようかな」
メニューを広げながら、気になって桐野に視線を向けると、桐野はまっすぐに竜一だけを見ていた。
自分はエキストラなんかじゃない。今夜だけは桐野と二人でメインを張っているのだと実感する。途端に走る緊張が僅かに背筋を駆け上ったけれど、竜一はそれを隠してメニューに視線を落とした。
店主の直筆で幾つものメニューが書かれている。
竜一は桐野のお勧めだという焼き鳥と、つくねと大根の煮物を選び、最後に自分の好きな揚げ出し豆腐を選んだ。飲み物は特製サワーにしてみた。何が特製なのかわからないが、この店の名前がついていて一番人気と書いてあったからだ。
桐野が「もういいのか?」と優しく伺うように顔を覗き込み、最後に自分の注文を付け加える。
「俺は焼酎お湯割りで、あと手羽先の唐揚げとポテトフライ、宜しく」
「はーい」
女の子が今きいたメニューをカウンター内へ告げる。
見かけによらず、随分子供っぽいメニューを注文した桐野が意外だった。見た目的に『なめろう』や『ナスの煮浸し』とかを頼みそうなのに。これはただの偏見だけど。
「桐野さん、ポテトフライが好きなの?」
「ああ、大好きだ。一日三食ポテトフライでもいいぐらいにな」
「そんなに!?子供みたいだね」
思わず微笑む竜一に桐野が照れた様子を見せる。随分歳が上なのに、こうして時々可愛い一面を見つける度に、なんだか得した気分になる。
「いいだろ、別に」
筋金入りのポテトフライ好きに驚きつつ微笑ましくなっていると、カウンターの中から豪快な笑い声が聞こえた。
「こいつ、学生の頃からずーっとこれだよ。身体ばーっかりでかくなっちまってよ、味覚はてんで子供のまま。なぁ?恭征」
「いちいち余計な事教えてんじゃねえよ。その話何度聞いたと思ってんだ。もう耄碌してんじゃねぇのか?」
二人のやりとりを聞いていると、竜一の方がヒヤヒヤしてしまう。そんな事を言っていいのか!?と思ったけれど、毎度のことのようで互いにそういいながらも笑っている。
他人とこういうやりとりを楽しめるなんて、自分には考えられない事だった。
早速出されたポテトフライはよくある細いタイプの物ではなかった。どちらかというとじゃがいもの丸揚げといった方が近い。小ぶりのジャガイモに薄い味つきの衣がついていて、それを丸ごと揚げてある物だ。想像していたのと違って、とても美味しそうである。
「あんたも食ってみろよ」
「うん、じゃぁ頂きます」
一つ貰って取り皿で割ってから半分口に入れると、熱すぎて何も言えなくなった。しっとりとしたジャガイモに少しピリっとする衣が絶妙で本当に美味しい。
「うまいだろ」
まだ喋れる状態じゃないのに、桐野が聞いてくるので竜一は頬張ったまま「うんうん」と頷いた。漸く飲みこんでから一度サワーを飲み感想を告げる。
「ほんと、凄く美味しい。これなら、いくらでも食べられそう」
「いいぞ。沢山食えよ。また頼めばいいんだし」
お湯割りの焼酎を口に運びながら、桐野も一つ箸で掴んで、割らずに一口で口に入れた。
次々に頼んだメニューが並べられてカウンターは一気に賑やかになった。
特別に高級な材料を使っている風でもなく、舌を噛みそうな横文字の洒落たタイトルがつけられているわけでもないメニュー。
だけど、どの料理もどこか懐かしくて心から温まるような美味しい料理ばかりだった。揚げ出し豆腐に添えられている紅葉おろしを箸で満遍なく広げながら、竜一は口を開いた。
「桐野さんは、さっきオヤジさんが言ってたけど、学生の頃からここにきてるの?」
「ああ、そうだな。25年近くきてる」
「そんなに!?」
「ここ、昼は定食もやってんだよ。高校の頃は学校帰りに食いに来てて、酒飲みに来るようになったのは大学になってからだな。すぐそこだったから。授業に出た回数より、仲間とつるんでここで飲んでた回数の方が多いぐらいだ」
竜一は、その言葉で知ってしまった桐野の出身大学に内心ビックリしていた。
この周辺にある大学と附属高校と言えば、超難関の有名な私立大学しかない。桐野は本当に頭がいいのだ。
以前勤めていた会社も大手の玩具メーカーだし、今はどうしてあんな寂れた場所で一人で修理屋をやっているのか、その経緯に謎が深まるばかりだった。
「あんたは?」
「え?」
「学生の頃、よく行ってた店とか、今も行ったりしねぇのか?」
「俺は……、うん。大学じゃなくて写真の専門学校だったから、とにかく課題に追われてて。そんなに遊んだ記憶がないんだ。それに……機材を揃えるのにいっぱいバイトもしてたから、金がなくていつも学校の近くにあったスーパーの安い弁当食べてたよ。300円とかのやつ」
「へぇ、そうか。でも、案外そういう飯も美味かったりするんだよな。写真の学校って、あれか。やっぱり、撮影の方法を勉強したりするのか?」
「うん、それもするし、自分で撮った写真を暗室で現像したりもしたよ。後は機材の使い方とかスタジオでの撮影テクニックとか、そういうのも勉強したんだ。写真工学なんかの講義は寝てたからあまり覚えてないけど」
「講義の席に座ると何故か睡魔に襲われちまうんだよな。直前まで全く眠くなくても」
「そうそう、なんでだろうね」
「でも、自分で現像とか楽しそうだし、好きな分野で頑張れるのはいい経験になるよな。俺もそういうのは大好きだ。今度、あんたの撮った写真見せてくれよ。撮る才能はないけど、写真展を見に行くぐらい、写真には興味がある」
「ほんとに!?何だか嬉しいな。桐野さんがどういう写真が好きなのか知らないけど、今度良かったら持ってくるよ」
「おう、楽しみにしてるわ。って、まさか、ねぇちゃんのヌードとかじゃないよな?」
「残念ながら、そういうんじゃないよ」
自分の趣味の写真に興味を持って貰えた事が凄く嬉しかった。
そういえば、桐野の自宅、トイレのドアに貼ってあった写真があったのを思い出し、竜一は二杯目のサワーに口を付けて桐野の方へ視線を向けた。
「この前自宅にお邪魔したとき、桐野さんの家のトイレのドアに貼ってあった写真、あれ、誰が撮ったの?」
「そんなのあったか?」
「あったよ。ほら。オルゴールの写真、セピア色の」
「あー……。あれか」
「うん、そう。凄くいい写真だなって思ったから」
「あれは俺がガキの頃撮ったんだ。当時はまだスマホなんてなかったから古い一眼レフでな」
「桐野さんが? そうだったんだ。あの写真は技術的な意味での構図もいいけど、なにより、撮影者の気持ちがとてもこもってるいい写真だなって感じたんだよ」
「……あの被写体のオルゴールな。ブリキのやつ。俺がガキの頃に、兄貴に作って貰った物でさ」
「そうなんだ。想い出の品なんだね。だから、撮った写真にもその想いが感じられたのかな。そういうのって写真に出るもんだから」
「そう、だな……。昔は大切にしてた。実物はもう壊れて、引っ越しの時に処分しちまったけど」
「……え、そうなんだ……」
修理屋をやるほど手先が器用な桐野が、壊れたからと言って処分したというのはとても意外だった。
「気持ちがこもった写真……か……」
桐野が一度言葉を止めて、苦笑いを溢しながら酒で一度喉を潤す。
「こもってたのかもな、あんたの言うとおり」
桐野は【こもってる】ではなく【こもってた】と過去形にしている。何か意味があるのだろうが、それを突っ込んで聞くほど、まだ桐野との関係は深い物ではない。
竜一はこれ以上この話題が続くのを避けるように、自分の職場の話に話題を切り替えた。
桐野と店を出る頃には、もう10時を過ぎていた。
随分長い時間色々な話をして飲んでいた気がするが、時間が過ぎるのはあっという間だった。割り勘でちゃんと支払えるように多めの金を持ってきていたけれど、桐野は先程の店には付けで払っているらしく、受け取って貰えなかった。
今週で10月も終わりだ。めっきり冬らしくなった冷たい風が、スーツを通り抜ける。でも、美味しい料理で満たされた今は、寒さはさほど感じなかった。
「ご馳走様でした。おごってもらっちゃって、すみません。久し振りに美味しい物を食べた気がする。有難う」
「気に入ってくれたんなら、連れて来た甲斐があった。あんたさえ良ければ、また行こうぜ」
「うん、是非」
恋人同士(仮)の距離感は結構難しい。
竜一は桐野と離れた距離を保ちながら冷たくなった指先にハァと息を吹きかけた。少し歩いて駅に到着すると、改札口の側で抱き合ってキスしている恋人同士が居て、思わず目をそらした。学生なのだろうか、人目を気にしない抱擁は自分にはとてもじゃないができそうにない。見ているこちらが恥ずかしくなってドキドキする。
桐野は竜一のそんな様子を見ていたのだろう。顔を覗き込むととんでもない事を口にした。
「なんだ?俺たちも真似して、さよならのキスここでするか?」
「えっ!?な、まさか!す、するわけない」
「冗談だって。こんなおっさんが改札で男とキスしてたら写真撮られてどっかに晒されるのがオチだからな」
桐野が笑いながらナイナイと手を振った。冗談で良かった。一瞬真に受けて焦ってしまったけれど。
「あんた、今日は帰るのか?土日は休みなんだろ?」
「休みだけど、不動産屋を回ろうと思ってて」
「引っ越しでもするのか?」
「うん……。前から考えてたんだけど、少し家賃の安い物件に移ろうかと思って……」
「場所は?」
「そういうのまだ全然決めてないよ。職場にあまり遠いのは困るけど」
「そうか、いい所があるといいな」
桐野はそう言った瞬間、竜一の方へよろめき、身体がぶつかって驚いた竜一は桐野を咄嗟に見上げた。
「っと、桐野さん?大丈夫?」
「ああ、悪い悪い。ちょっと飲み過ぎただけだ」
「そう……?気分が悪いなら少しどこかで休もうか?」
「いや、大丈夫だって。気分は逆にいいぐらいだ。今日は楽しい酒だったからな。そのせいで酒が進んだ」
だから、一瞬よろめいただけという事なのだろうか。
確かに桐野は結構な量の酒を飲んでいた。すぐに元通りの軽い冗談を口にする桐野に、気のせいだったのかもと思い直す。
改札を入ってから「じゃぁ、またな」という軽い挨拶をして消えていく背中。桐野とはそこで別れた。乗る電車が違うのでホームは隣なのだ。
今日は楽しい一日だった。
少し疲れてはいるけれど、嫌な疲れではない。桐野と居ると、気取らずに素のままの自分で居られる。それがこんなに楽だというのを改めて実感していた。
竜一は、ホームから桐野の居るであろう方へ視線を向けた。そんなに人もいないので、同じくホームに向かった桐野の姿はすぐにみつかるだろうと思ったのだ。
しかし、いくら探してみても桐野らしき人物はいなかった。
もう電車に乗った?それとも……。別のホームにいったとか。見つけられなかった桐野の存在に視線が行き場を失い、しばし彷徨った。
――メッセージ、入れておこう……。
竜一は、桐野の携帯へ送るメッセージ画面を開くと文字を打ち込んだ。
『今日はご馳走様でした。楽しい時間を過ごせました。桐野さん、もしかしてもう電車に乗った?また連絡します。おやすみなさい』
送信して少しすると、既読の印がついて返信が届いた。
『また飲みに行こうぜ。気をつけて帰れよ。おやすみ』
ホームへ電車が入り込んでくる。
風が吹き抜けて竜一の額の前髪がフワリと舞った。
COUNT0….|創作BL小説|メンズラブ|
シリーズ『俺の男に手を出すな』メインの長編連載小説サイトです。病弱、ホスト、バンドマン、医者、眼鏡、強気受け、リーマン。