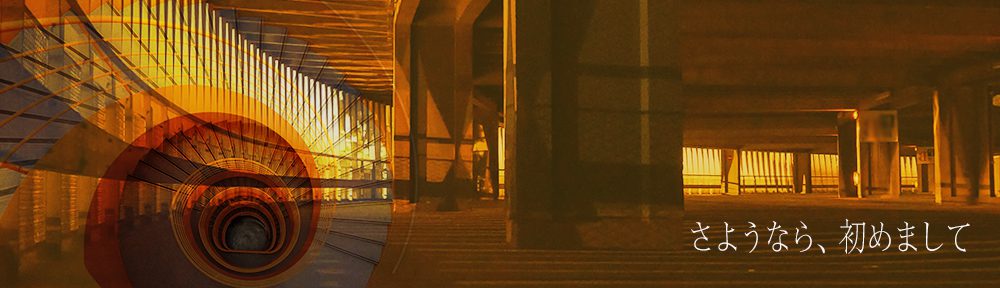──memory8──
竜一が電車に揺られて桐野の事を思い浮かべている時、桐野はまだ竜一と別れた駅のホームにいた。
竜一が向かった二番線のホームに背を向ける形で、ベンチに腰を下ろしている。激しい頭痛とともに訪れる左目の視野の狭窄。
只管耐え、痛みが引いていくのを待っていると自嘲気味な笑みが口元に浮かぶ。
こんなに寒いのに襟足の髪が嫌な汗で濡れていて、伸ばした指先をじっとりと湿らせた。
――俺も、焼きが回っちまったもんだな……。
心の中で呟く言葉でさえ頭に響き、桐野は「痛ってぇな」と小さく呟いた。
滲んだ視界の中では、電車の前照灯がやけに眩しく感じる。何本も電車を見送っているうちに、痛みは嘘のように引いていった。
唾を飲みこんで瞬きを数回、ベールが掛かっていたような膜が徐々に晴れていく。
戻った視界にはいつもの雑踏。よくある数分の出来事だった。
桐野は眼鏡の上からぼやける世界を見た。
人の姿さえ輪郭すらハッキリしない。そこに動く何かがあるだけ。
――ねぇ、桐野さん、どうしていつも眼鏡を上にあげないの?
竜一との先程の会話を思い出す。
眼鏡をずらしている理由を訊かれた時、自分は言った。全てを見る必要が無いからだと。あれは嘘ではない。だけれど、本当でもないのかも知れない。見ても仕方がないと、諦めているから見ないのだ。
「そろそろ、帰るか……」
重い腰を上げて俯き加減で歩き出す。
竜一と一緒にいる時にならなかったのだけは不幸中の幸いだ。
――あと三週間か……。
痛みの治まった頭をもちあげると、桐野は一人小さな笑いを溢し次の電車に乗り込んだ。
* * *
数日後、桐野は店のガレージに貼る為に用意した画用紙に向かい、太いマジックを握りしめていた。
マジック特有のツンとした溶剤の匂いが鼻に付く。
『臨時休業のお知らせ しばらく所用で店を閉めます。』
そこまで書いたはいいけれど、いつまで店を休業するのか、休業する理由についても書いた方がいいかと思うが、どうせそんな頻繁に直接店に客がやってくることはないので必要ないかとも思う。
「どうすっかなぁ……」と独り言を呟き、結局はこのまま外へ貼ることにした。雨に濡れてもいいようにラミネート加工をした物を手に取って、玄関のサンダルに足を突っ込む。
安物のゴムサンダルはサイズが三種類しかなくて、一番大きなLサイズを買ったにも拘わらず桐野の足はひどく窮屈そうに指を曲げていた。
今日はもう閉店時間なので外からガレージを閉め、そのまま貼るつもりだ。
錆びた外階段を降りて店側へ回りこむと、隣に住んでいる老婦人がちょうど外出から戻ったようで鉢合わせた。
「こんばんは」
「あら、こんばんは」
挨拶をしながら書いてきた紙を貼っていると、婦人は通り過ぎずに桐野の背後で足を止めた。
「お店、臨時休業なさるの?」
「ええ、まぁ」
「どこかご旅行にでも行かれるのかしら?」
「旅行じゃないですけど、ちょっと用事があって。暫くの間閉めるんですよ」
「そうなのね。今度、孫に頼まれてて桐野さんのお店で直して貰いたい物があったのよ、残念だわ」
「いや、また再開しますよ。その時は、是非店に持ってきて下さい。ご近所サービスで安くしますから」
「そうね。じゃぁその時にまた。宜しくお願いするわね。最近急に寒くなってきたから、桐野さんもお身体には気を付けて」
「ありがとうございます。おばあちゃんも気をつけて」
軽く下げられた頭に釣られて、桐野も笑みを浮かべ頭を下げる。
ガムテープでガレージに紙を貼り付けた後、桐野は一歩下がって顎をさすり、マジマジとそれを見た。この店を始めて以来、不定休でたまには休んでいるが、それ以外で臨時休業をしたことはない。どうせ上階が自宅なのだから、開けていても閉めていてもさして変わらないからだ。
なので、休業を知らせる紙が貼られたガレージは、正直、自分でも初めて見る光景で、少し不思議な気分だと思った。
フと息を吐き桐野が階段へ戻ろうとすると、背後で車が止まった。
奥まった路地のこんな場所に来るのは、この周辺に用事がある奴だけだ。
隣か、その隣の家の誰かなのか。そう思おうとしている時点で、自分の客である事をどこか確信している。
なんとなく嫌な予感がして振り返らないで居ると、車から降りてきたのは案の定予想通りの人物のようだ。
桐野が、小さく舌打ちをするのと同時に、硬質な足音が二度響きピタリと止まった。
「恭征さん」
「……」
この声、しかも名前で呼ぶ人間はそんなにいない。桐野は背後に居る人物には振り返らず、背を向けたまま言い放った。
「ここには、もう来るなって言ったろ」
呆れを滲ませたような小声に「ですが……」と口ごもる相手は、言葉とは裏腹に引く様子はない。それどころか階段の方へ向かってきて、真っ直ぐ背中に視線を向けてきた。
「お話があります」
引き留めるように短い言葉が投げられる。桐野は、言っても無駄だとわかりながらも溜め息交じりに呟いた。
「生憎、俺からは『お話』はねぇよ。帰ってくれ」
無視して階段を上る桐野の背後で一拍の間を置き、相手の声のボリュームが跳ね上がった。
「お父様も、お兄様も心配していらっしゃいます!」
「……っ、」
「私のお話を聞いて下さるだけでも、ダメですか?」
誰も辺りに居ない中、悲痛な声がやけに大きく周囲に響いた。
「外でそんな大きな声出すなよ。なんの嫌がらせだ。ったく……。わかったから、……とりあえず、あがってこい」
「す、すみません。では、失礼します」
駆け寄った男の名前は笹松 郁人という。
桐野がまだ高校生だった頃にはよく遊んでやっていたものだ。笹松の家は、桐野家代々と昔から深い繋がりがあり、特に父はそんな笹松の腕をえらく買っていて親友のように接し、仕事に関しては、秘書としても右腕としても長年側に置いていた。
笹松が事故で亡くなったのは六年前の話だ。
家族同然にしていた関係で、息子である郁人が笹松の仕事を受け継ぐのは自然な流れだった。
「お邪魔します。これ、お父様から」
郁人は、なにやら紙袋に入った菓子折りをそっと床へおろした。一瞥しただけでわかる。どうせ父親ではなく、郁人が「父親からだ」という体で買ってきた物なのだろう。土産のセンスが若すぎる。
郁人は散らかった部屋の中で立ったまま辺りを見回していた。
「で? 今日は何しに来たんだ。戻ってこいって話なら答えはノーだ。何度も言ってるだろ」
インスタントのコーヒーを二人分入れて、郁人の前にもそっと置く。郁人は「お気遣いなく」と小声で言ってカップに手を伸ばすことはなかった。
「戻ってきて欲しいのは勿論ですが、それ以前に、会って一度話したいと仰っておられます。誤解を解きたいと……。恭征さんがご実家に顔を出さなくなってから、もう五年ですよ? 仕事が関係なくても、会いたいと思うのは親として普通の事だと私は思いますが」
「そうだな。普通の関係だったら、な」
「お兄様も……会いたがっていらっしゃいます。恭征さんのデスクもまだそのままにしてあるんですよ。先日、寂しそうにそのデスクを眺めている会長を見ました。会長ももういいお年ですし、あまり心労をかけるのはどうかと……」
気が短い方ではないが、遠回しにしたうえに何重にもオブラートに包まれた言葉を聞き続けるのは気分のいいものではない。
桐野は、煙草の箱から一本抜き出すと口に咥えた。
返事を待っているのか、火を付ける際のジュッという音が聞こえるぐらい部屋は静かだった。
「……だったら」
「……?」
「郁人、お前をこうして寄こさずに直接会いに来ればいいじゃねぇか。何でそうしない? 俺は隠れているつもりはないし、来れば話ぐらいは聞いてやる」
「それは……、会長も社長も今とても多忙で、時間が取れないんですよ。ですから、私が代理でこうしてお願いに」
「だから、そこだよ。代理を寄こして様子を窺わせるなんて、ちっせぇ事ばっかしてるような奴に会うつもりはねぇよ。あいつらがした事……、郁人だって知ってんだろ。俺は、悪いが許す気はない」
「……でも、もう時効でしょう? あの後、会長や社長もだいぶ誠意を尽くしたはずです。知ってますか? あそこのご子息の学費だってこちら側で払って、今は立派に働いているそうですよ。もう。あの件を気にしている人はいないんじゃないでしょうか。それでもまだ、許せませんか……?」
「時効ね……。随分都合良く時が解決してくれると思ってんだな。なぁ、郁人」
「……はい」
「知ってるか? たとえ一生遊んで暮らせるほどの金で償っても、人の心についた傷や、苦い想い出。そういうものはな、二度と消せねぇんだよ。金なんてのは無力だ。加害者側の自責の念を軽くするだけの都合のいい道具でしかない」
「ですが……他の方法なんて。でしたら、恭征さんなら正しい償いを出来るのですか?」
「出来るわけねぇだろ。ひとつでも出来る事があるならとっくにやってる。今更もう何をしたって遅いんだよ。あの時の行動を変えられない限り、正しい償い方なんてあるわけない。過ちは過ちのままだ」
「……それがきっかけで、会長は恭征さんをこうして失った。もう十分苦しんでいらっしゃいます。だから、一度お会いになるだけでも」
「俺に言いたいことがあるなら、直接言いに来いって伝えておけ。それがせめてもの人としての礼儀だ」
「……」
きつく言い放った言葉に返せなくなった郁人が俯いて、膝の上で握りしめる拳を硬くする。
これは郁人への完全な八つ当たりだ。
言いながら、自分にも腹が立ってくる。郁人は何も悪くない。こんなに拗れた関係になっていなければ、今頃は郁人とだって二人で美味しい酒でも呑みながらくだらない話をするような関係になれていたかもしれない。
ただ、現実はそうならなかった。
「……おい、郁人」
「……はい」
「別に、俺はお前に怒ってるわけじゃないからな」
「……わかってます。相変わらず、恭征さんは優しいですね……」
「そんなんじゃねぇよ。っていうか……」
桐野は詰めていた息を吐き出すと、長く息を吐いた。あれからもう五年だ。長いようにも感じるが、最後の日のことは、相手の表情、台詞に至るまで鮮明に覚えている。立派な三つ揃いを着て、すっかり秘書っぽくなっている郁人は、もう完全に向う側の人間だ。
「いつまで、こんなこと続けるつもりだ?」
「いつまでとは?」
「お前も自分のやりたい事とかあんだろ。ずっと親父や兄貴にこきつかわれてそれでいいのか?」
「私は……、これが自分のやりたいことですから」
「……それが本心なら、俺は何も言わねぇけど。少しでも疑問を持ってるっていうなら、一度じっくり自分の未来を考え直したほうがいい。人生一度きりだぞ?」
「……」
気まずい空気がどんどん濃くなって窒息しそうだ。桐野は大袈裟に煙草の煙ごと息を吐いて乾いた笑いを溢した。
「まぁ、社会のはみ出し者の俺みたいになりたくねぇってのは、ちょっとはわかるけどさ」
「そんな、まさか」
郁人は即座に否定して、桐野に目を合わせた。
「そんな言い方しないで下さい。私は、恭征さんに昔から憧れていました」
「いました。って、過去形じゃねぇか。今はもう違うんだろ?」
「いえ……。今も、憧れていますよ。個人的な意見を言わせて貰うなら、恭征さんのように自分を強く持って流されない生き方には憧れがあります。……でも、私には出来ません。そういう人間なんです。私は変われません」
郁人のその言い方が悲しそうで、胸にモヤモヤしたものが汚泥のように積もる。
残った珈琲を飲み干そうと持ち上げた瞬間。急に激しい頭痛が襲い、桐野はカップから手を外すと低く呻き柱に手を突いてきつく目を閉じた。
マグカップが床へと落下し、カップは割れて中の珈琲が床に散る。
驚いた郁人が駆け寄って桐野の身体を支えた。
「恭征さん!? どうされたんですか? どこか体調が!?」
「……っ、大、丈夫だ」
運良く一瞬で収まったので、桐野はごまかすように曖昧な笑みを浮かべ髪をかき上げた。郁人の伸ばされた手から離れ平然を装って床へとしゃがみ、床に散らばったカップの破片に手を伸ばした。
「ああーあ、木葉微塵だな。これ、気に入ってたカップだったのになぁ」
「恭征さん……」
「ああ、心配要らねぇよ。偏頭痛だ。時々なるんだよ、季節の変わり目とか? 寝不足とかでさ。ほら俺、デリケートだから」
「……」
冗談ぽくそういって苦笑しても郁人は心配そうな表情を変えなかった。
無言で拾い上げたカップの欠片を机の上へのせ、「顔色が悪いようですが」と益々訝しげに顔を曇らせた。
「ほんとに、何でもねぇから。そんな顔すんなって」
「気をつけて下さいね? なにかあったら私にだけでも連絡下さい。会長に知られたくないなら私の心に留めておくことも出来ますから」
「おいおい、秘書がそんな事言っていいのか? 聞かなかった事にしとくから、お前も滅多なことでそんな事軽く口にするな」
「……。はい。今日は、帰ります。あの……」
「なんだ?」
「久し振りに恭征さんに会えて、良かったです」
「ああ……」
「すぐ休んで下さい。お大事に……」
腰を上げた郁人は、出したカップに最後まで手を付けないまま、それでも「ごちそうさまでした」と律儀に礼を言って玄関へ向かった。
ちょうど夕方と夜の境目の時間だったせいもあり、ドアをあけると外は真っ暗になっていた。淡く照らす街灯の下、階段を下りていく郁人の背中に、桐野は堪らず声をかけた。
「おい、……郁人」
足を止めた郁人が階段の上に居る恭征を見上げる。
「変われない人間なんて、いやしねぇぞ。今からでも遅くねぇだろ」
郁人はその言葉を切なげな笑みで流して、頭を下げると車に戻っていった。
戻って玄関を閉め、ソファに向かってどかっと腰を下ろす。
痛みはもうないが、鈍く燻る余韻が頭に残っている。桐野は一度眼鏡を外してマッサージをするように眉間を揉んだ。
――はぁ……。
郁人は真面目な性格で、父親譲りの頑固さもある。
だけど、どうみても現状に満足しているようには思えなかった。昔学生だった頃、郁人は料理が好きで大きくなったら自分の店を持つと夢を語っていた。
大学に通いながらも夜間の料理学校に通って調理師免許もとり、色々研究して新作の創作料理を作ってはよく試食させてくれていたのだ。
郁人の料理の腕は皆が褒めていたし、笹松も自分の跡を継がせるつもりはなく郁人の店を持ちたいという夢を応援していたはずだ。てっきり料理人になるのだと皆が思っていた。
しかし、父親である笹松が逝去してから、一切料理からは手を引き父の跡を継いで秘書になってしまったのだ。大学を出たばかりの社会も知らないような若さで、太いレールの上に投げ出された彼が、そのレールに乗ってしまうのは仕方がなかったのかも知れない。
今だからこそ、そのレールから外れる力があると思うのに、本人は『もう変われない』と決めつけている。全くの他人ではないからこそ、それが悔しい。
皆が皆、自分の思い通りの生き方が出来るわけではない事だって理解しているし、それを否定しようとも思っていない。ただそれは自身が納得していた場合の話だ。
そんな事を考えていると、再び玄関のインターフォンが鳴った。
郁人が何か忘れ物でもしたのかと周囲を一度見渡したが、目に付く範囲では何も残っていない。桐野は「はいはい」と呟きながら置いていた眼鏡を掛け玄関へ向かう。相手を確かめもせず鍵を開けてドアを開いた。
「どちらさま?」
――!?
ドアの先に見える革靴、そこには予想もしていなかった相手が立っていた。平日の約束もない日に訪ねて来るなんて初めてである。
「どうしたんだ? 俺に、会いたくなったとか?」
冗談交じりでそう言うと、目の前の竜一は手にしていた物をぐいと前に押し出して「それだけじゃないけど」とはにかんだ。それだけじゃない、という事は「会いたい」とも思ってくれていたのかと嬉しい気分になる。竜一が持っているのは何やら重そうな紙袋だった。
「急にごめん。今日、会社でこれ貰っちゃって。一人じゃこんなに食べきれないし、桐野さんにも食べて貰おうと思って。帰りに寄ってみたんだ」
「ん? ――林檎?」
紙袋の中には真っ赤な色をした大きなリンゴが幾つも入っていた。
「そう、桐野さん林檎苦手じゃないよね?」
「ああ、林檎は食うけど」
「良かった。お得意さんが会社に送ってくれて皆にも配ったんだけど、とにかく量が多くて」
「そうなのか、俺が貰っていいのか?」
「勿論、そのつもりで持ってきたんだし」
「ありがとな。じゃぁ、貰うわ。とりあえずあがれよ」
「……うん」
なにげなく竜一の手を掴んで玄関に引き入れたが、その手のあまりの冷たさにビックリする。
「すげぇ冷えてんな、あんたの手」
「あ、……これは、その」
「??」
「いや……、少し前から外に居たから……」
しまったとでも言うようにすぐに後ろに隠された手、言葉の真意を測りかね、桐野が不思議そうな顔をする。貰ったリンゴを床へと降ろし、何か温かい物でも飲ませてやろうとコンロの火を点けた瞬間、竜一が口を開いた。
「さっきの人、桐野さんの知り合い?」
さっきというのは、郁人のことを指しているのだろう。だとしたら、郁人が来て帰るまでの間、外で待っていたという事になる。どうりで身体が冷え切っているはずである。
「まさか、ずっと待ってたのか? 馬鹿だな。声掛けてくれれば良かったのに」
「ううん。俺が急に来ただけだし、……ちょうど向こうも来たばかりみたいで、ちょっと声掛けづらい雰囲気だったから。それに、お店のお客さんだったら悪いし」
「あー……。悪ぃ、あいつは昔からの知り合いで……まぁ、身内みたいなもんだ」
「……そっか」
竜一は通常通り裏から来たようで店の張り紙はどうやら見ていないらしい。触れてきたのは郁人のことだけだった。
「茶でもいいか? 今コーヒー飲んだばっかりだから」
「あ、うん。俺はなんでも。桐野さんもしかして忙しかった? 急に来ちゃって、迷惑だったかな。俺すぐ帰るから」
早口でそんな事を言う竜一が落ち着かない様子でソワソワしている。
桐野はカップに淹れた茶を手渡すと、竜一の頭にポンポンと手を置いた。
「全部ハズレだ。別になんにも忙しくもないし、迷惑でもない」
「ほんと?」
「ああ、ホント。だからすぐ帰るとか言うなよ」
竜一が照れたように笑ってカップから熱々の茶を一口飲む。先ほどまで郁人と会っていた時の嫌な感情が洗い流されるようで、桐野は暫く竜一を見て心が落ち着いていくのを感じていた。
「忙しくもないし迷惑でもないってのは本当だけど」
「え? うん」
「実は、ちょっと疲れてる」
「えっ!あ、じゃぁやっぱり俺、今日は」
竜一が一気に貰った茶をゴクリと飲んでテーブルに置き、コートに手を伸ばす。しかし、その手はコートに届く前に桐野にがっちりと掴まれた。
「桐野、さん?」
「今日、泊まっていけよ。ダメか?」
「……え、でも……」
桐野にまっすぐ見つめられてお願いされ、竜一は口ごもった。
明日も会社があるし、泊まるつもりで来たわけじゃない。
すぐに返事しなかった空気を察した桐野が「まぁ、急には無理か。勝手な事を言ってすまん」と苦笑する。
そうじゃない。泊まることに抵抗があるわけではない。だけど、多分今夜泊まって、もし桐野に夜誘われたら断る自信が全く無かった。
COUNT0….|創作BL小説|メンズラブ|
シリーズ『俺の男に手を出すな』メインの長編連載小説サイトです。病弱、ホスト、バンドマン、医者、眼鏡、強気受け、リーマン。