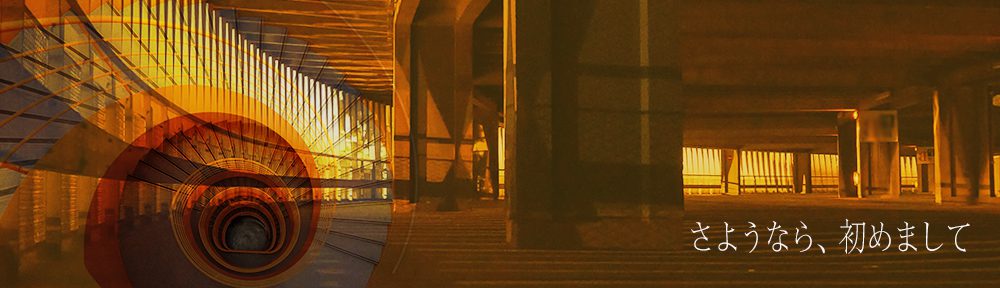──memory9──
「ええと……明後日、会う約束したし」
「ん、ああ。まぁ、……そうだったな」
「今日泊まったら。連続で会うことになって、その……」
恋人(仮)だとわかっているのに、その(仮)が付いていることが最近もどかしくてたまらないのだ。自分でもおかしな理由を口走っていると思うが、他の言葉が思いつかなかった。
最初にあった「好奇心」や「興味」の全てが、桐野に対しての「好き」へと変化してきている。
誰かを好きになるのがあんなに怖かったはずなのに。こんなに突然恋に落ちるなんて思ってもいなかった。
そして、自分自身がそれに気付いたばかりで心が落ち着かない。そんな状態で一晩一緒に過ごすなんて……。
「……そんなに嫌だったか?」
桐野が心配そうに顔を歪める。竜一は慌てて首を振った。
「ごめん、そうじゃないよ。あ、俺、お腹が空きすぎて、ちょっとボーッとしてた」
「ああ、そういや……もう夕飯の時間だな。俺もまだ食ってないから、まずはどこか近場で食いにでも行くか
「う、うん。そうだね」
竜一はわざと明るくそういって、「何食べに行く?」と笑みを浮かべた。
桐野が出掛ける準備をするのを玄関で先に待っているとすぐに桐野がやってきた。
すぐそこに脱ぎ捨ててあったジャケットは所々シワが寄っているが、それを拾って構わず腕を通す。そんな気取らなさを最初はだらしない男だと思っていたのに、今は違う。そんな桐野だからこそ、一緒に居て自分も素直になれるのだ。
捉え方一つで取り巻く空気でさえ変わって見える。
それは恋愛症状の最たる物なのではないか、竜一は次々に自覚してしまうその症状に自分でも呆れて嘆息を漏らした。
「どうしたよ、溜め息なんかついて。あ、もしかしておかしいか? これ」
「ううん。似合ってる」
「お、惚れ直したか? って。……あー、別に元が「惚れてる」わけじゃねぇから、直すってのは語弊があるな」
「そこ?」
互いに笑いながら家を出る。階段の下から三段目を二人で飛ばして、また笑った。
近場で適当にとなると、ファミレスかラーメン屋しかないと桐野は言う。
「どっちでも俺はいいけど」
「んじゃ、ファミレスにすっか。ラーメン屋は昨日行ったばっかだしな」
「昨日も外食?」
竜一は桐野の言葉に苦笑し「桐野さんって、あまり自炊しないの?」と隣を見上げた。
「自慢じゃねぇが、ほとんどしないな。買ってくるか、食いに行くかのどっちかだ」
「外食ばかりだとお金も掛かるし、それに身体に悪いのに」
「そうだけどさ。自分で作って美味くもねぇ飯食って腹が満たされると、こう……なんていうか食後に虚無感って言うの? 急に虚しくなっちまうんだよな。ああ、なんでこんなもんで腹一杯にしちまったんだ俺。って」
「あー……。それもなんとなくわかるけど」
「だろ? だったら、最初から美味い飯を食いに行った方がいい。あんたはどうなんだ?」
「俺は一応簡単な物なら自炊するよ。そんなに贅沢できないし、自分で作って美味しい時もあるから」
「んじゃ、練習あるのみだな。試食係になってやってもいいぞ」
「ほんとに? どうなっても知らないよ?」
「ちょっと待て、話がおかしくねぇか? 美味しい時もあるって言ったのはなんだったんだよ」
「五回に一回ぐらいだから。四回は美味しくないって事」
さらっと言ってのける竜一の顔を見て、桐野は参ったとでも言うように首を振った。
「結構覚悟が要りそうだな……」
どこにでもある有名チェーン店のファミレスに到着し、席へ案内される。夕飯時とあって客席はほぼ満席だった。
互いに好きなメニューをオーダーしてから、メニューを脇へと避ける。まっ先に運ばれてきた生ビールに口を付けるとようやく一息ついた。
「あー、冷たいビールは外が寒くてもやっぱり格別だな。疲れの50%ぐらいは一気に吹き飛んだ」
桐野の言い方があまりにも心がこもった物で、竜一は思わず吹き出した。
「さっきも疲れてるって言ってたけど、大丈夫? どこか昼間出掛けてたとか?」
「ああ、ちょっと沖縄まで自転車で行ってきてさ。流石に遠くて参ったぜ」
「何それ、嘘ばっかり」
竜一が呆れたように眉を寄せて苦笑する。
桐野はもう一口ビールを呷るとジョッキをテーブルへと置いた。
「いいんだよ。あんたと会えて、こうして楽しい夕飯タイムにありつけた。今日は凄くいい日だ。終わり良ければすべて良しってな」
「押し掛けちゃったけど、……そう言って貰えると助かる」
桐野が嬉しそうに少し顔を上げ、レンズを通して竜一の顔を見る。
「そっちは、仕事どうだ? 順調か?」
「うん、最近ちょっと大きな仕事を任されてて、頑張ってるとこ」
「へぇ、凄いな。どんな仕事なんだ? って、こういうのは外部には漏らしちゃダメか」
「ううん、別にそういうのはないけど」
竜一は大手化粧品メーカーの名は伏せて、今任されている仕事内容について桐野へ話して聞かせた。
途中で頼んでいた食事が運ばれてきたので、それに箸を付けつつ話を続ける。
「クリスマスはまだ先だけど、店頭に並んだら俺も見に行くとするか」
クリスマスに……。恋人お試し期間の終わった後のことを口にする桐野はその事に気付いていないようだった。なんだか普通の恋人同士になったみたいで竜一の胸が弾む。
「でも、女性の化粧品売り場だよ?」
「別にいいだろ。恋人にプレゼントを買う事だってあるんだから。おかしかねぇと思うが」
「それもそうか……。じゃぁ、並ぶようになったら教えるよ」
「ああ」
桐野が優しい笑みを浮かべる。竜一は、そんな桐野を見ながらフと前の彼と比べている自分に気付いていた。
こうやって仕事の話をする事は昔もよくあったけれど、さほど興味が無いのを隠そうともしない彼に遠慮して、なるべく短く切り上げていた。そして、そのうち仕事の話題を口にもしなくなった。
今こうして長々と話せているのは、桐野が真剣に聞いてくれているからだ。
「桐野さんって、優しいよね。俺の話ちゃんと聞いてくれて」
急に面と向かって褒められた桐野は、喉を詰まらせて側にあった水を一気に飲み干し声を潜めた。
「何だ急に」
「いや、だって。俺の仕事の話なのに、こうやって楽しそうに聞いてくれるから」
「そりゃ、嬉しいからな」
「桐野さんが?」
「そう。まっ、仕事内容に興味はあっても、ちょっとわからねぇ事が多いが。あんたが俺に楽しそうに話をしてくれることが嬉しいんだよ。どんな話でも」
「そんな、甘やかしすぎ。俺、調子に乗っちゃうよ」
「おお、乗れ乗れ。俺は大歓迎だぞ」
桐野のようにストレートに好意を向けてくるタイプは初めてで、竜一は返す言葉に詰まり赤面した。照れ隠しで、自分の頼んだハンバーグを大きく切り取って口に入れる。ファミレスのハンバーグってこんなに美味しかったっけ。そう思うほど食事が美味しく感じた。
しかし、目を細めて自分を見ている桐野は、こんな自分のどこが気に入って恋人になってくれと言ってきたのだろうか。考えれば考えるほどわからない。
期限付きの恋人だから、その契約期間だけは恋人として振る舞っているだけなのだとしたら、浮かれている自分が惨めである。そんな失礼な事まで浮かんできてしまう始末だ。
店はどんどん客が多くなり、待合席にも何人か集まりだしている。
ファミレスで長居するのは今の時間は遠慮した方が良さそうだ。あっという間に食べ終わった皿に箸を置くと、桐野も同じ事を考えていたのか「続きは帰ってからにするか」といって苦笑した。
腹も十分満たされた帰り道、コンビニによってつまみを買って帰るという事になり、来た時とは別の道を帰る
今夜の夜空はどこか透き通っていて、冷えた空気がそれをより一層感じさせる。これから訪れる冬の季節、その頃の自分はどうしているのだろうか。
途中、桐野と出会ったあのビルの前にさしかかり、竜一は足を止めた。
――……この場所……。
ほんのこの前なのに、随分昔のことのように感じる。
あの時飛び降りていたら、今こうして桐野と二人で楽しく食事をし、並んで歩くことも出来なかったはずだ。馬鹿だった自分の行動が今更ながら怖くなり足が竦んだ。
少し先に行っていた桐野が、立ち止まっている竜一に振り返り戻ってくる。
「どうした?」
静かに気遣うような低い声。
桐野が下げているコンビニの袋がガサガサと音を立てる。
「ううん……。なんでもない」
その音よりも小さい声で返した竜一は、一度唾を飲みこんだ。袋を左手に持ち替えた桐野が、右手を竜一の目の前にすっと差し出す。
「……え?」
自分の命を繋ぎ止めてくれた、逞しくて大きな手。
差し出された手の意味がわからず立ち止まったままでいると、桐野は竜一の手を強く握って自分の側へと引き寄せた。
特に理由も告げずそのまま歩き、ビルの手前の道で急に曲がる。
背を向けたビルからどんどん遠ざかっていく、桐野と手を繋いだまま二人で。
夜とは言え、人通りもあるのに男同士で手なんか繋いだら……。そう思う物の、自分から離す気もなかった。しかも、この方角は桐野の家と逆方向だ。
「あの、……桐野さん、こっち逆じゃ?」
「ああ、逆だな」
「ごめん。俺、平気だから。ちょっと思い出しちゃっただけで」
「ん? 何の事だ」
「いや、あの」
「この先に、可愛い猫がいるんだよ。あんたに見せてやろうと思って」
多分それは嘘で、桐野が気を遣ってくれているのだろう。繋がれた手がジンジンして、あったかくて、何だかたまらない気分になってしまう。
暫く会話はなかったけれど、桐野はずっと竜一の手を痛いほど強く握ったまま離さなかった。力強いその大きな手に居場所を与えられたような気がして、このままずっと繋いでいられたらと願ってしまう。
少し先にいくと桐野が「いたいた」と声を上げた。
「えっ? どこ!?」
「ほら、あそこ」
猫がいるというのは本当の事だったのかと竜一が桐野と同じ方へ視線を向けると、寂れた公園があって、中の遊具がパンダの形をしていた。
しかもとてもぶさいくなパンダで塗装も剥げかかっているため、暗がりに置かれているとぱっと見まるで化け物である。思わず吹き出した竜一が桐野に振り向いた。
「これ、パンダじゃないの? しかもちょっと変」
「パンダは中国語では熊猫って書くんだから猫グループの一員だろ?」
「そうかもしれないけど」
「前にさ、夜にコイツを発見した時。なんだか酷い状態だから可哀想になっちまってな。塗装し直せねぇか近寄って色々と調べてたんだよ。そしたら不審者と間違われて通報されちまって……。駆けつけた警察に職質されるわ疑いの目で見られるわで散々な目にあった」
「え? これに乗ってたの?」
「そりゃ、乗ってみるだろ。どれぐらい錆びてるのか確認するために」
竜一が涙が出るほど笑って指で目元を拭った。
「当たり前だよ。桐野さんみたいな大人が、こんな遊具にのってキョロキョロしてたら怖いもん」
「こんな優しい俺を捕まえて怖いはねぇだろ。……にしてもなぁ、ほんっと不細工な顔してんな、こいつ。これじゃ子供が寄りつかねぇわけだ」
「でもさっき、可愛いっていったくせに」
「あー、ありゃあ、まぁ成り行きで言っただけだ」
「なにそれ」
笑う桐野に釣られて竜一も一緒に笑う。夜中に一人でこのパンダに乗っていた桐野を想像すると笑いが止まらない。こんなに笑ったのは久し振りで、腹が痛くなるほどだ。
一緒に笑っていた桐野がフと息を吐き、繋いでいた手を離すと竜一の頬に手を添えた。
「あんた、最近はよく笑うようになったな」
「え?」
「笑う門には福来たるって言うだろ? くだらない事で笑えるってのは、幸せな証拠だ。俺も、あんたも。今この瞬間は、それで十分だ」
「……うん」
「んじゃ、帰るか。まーた通報されたらヤバイからな」
苦笑した桐野は再び竜一の手を取ると公園を出て歩き出す。竜一は次に言う台詞を心で反芻し覚悟を決めて息を呑んだ。緊張で繰り返す瞬きと切れかかった外灯の明かりが不規則に現実と瞼の裏を繰り返す。
ほんの少しだけ繋いだ手に力を込めた。
「桐野さん」
「ん?」
「俺、……今夜、泊まっていく……」
少し驚いた顔をした後、桐野はすぐに嬉しそうに笑みを浮かべ「ああ」と一言だけ呟いた。
* * *
少し遠回りをしたけれど、夜道の散歩はちょっとしたデートみたいで楽しかった。無事に家に辿り着いて上着を脱ぐと、すぐに桐野がグラスを用意して晩酌の準備をする。
つまみは先程コンビニで買ってきた乾き物とスモークチーズだけ。
「よし、それじゃ改めて乾杯」
「うん。お疲れ様」
350ml缶を一気に呷ったあと、桐野が残りをグラスに注ぐ。すでに半分も残っていない。竜一もグラスの半分ほどを飲んで一度テーブルへと置いた。
ネクタイを外し、何個かボタンを外すと解放された気分になる。
今夜は帰らなくてもいいのだと思うと、余計にリラックスした気分が増した。
「このチーズ美味しい。ビールに合うね」
「だろ? これはスモークだけど、わさび味もかなり美味いぞ」
「へぇ、今度俺も買ってみようかな。一人で宅飲みする事はあまりないんだけど」
「そうなのか?」
「うん、平日は帰宅したらすぐ寝るから、土日にたまに気が向いたらって感じ」
「まぁ、話す相手がいた方が楽しいのは間違いねぇな」
「最近は俺もそう思うよ」
食事も済ませてきているので、飲むペースはゆっくりだ。桐野と色々な話をしながら、ついつい煙草も本数が増える。
桐野が冷蔵庫に追加のビールを取りに行く背中を何気なく目で追いながら、竜一は僅かな違和感を抱き、吸っていた煙草を灰皿でもみ消すと部屋を見渡した。
前に自宅に来た時とは少し景色が違う原因はすぐにわかった。
ずらりと並んでいたおもちゃの棚が、今はほとんど空になっているからだ。がらんとした棚には代わりに工具箱が置かれていた。
「桐野さん」
「なんだ?」
再び目の前に腰を下ろした桐野がプルトップを開ける。
「おもちゃ、一気に修理終わらせたの? 棚、随分少なくなってるみたい」
「ああ……」
桐野は何故か少し気まずそうに視線を逸らした。あまり聞いて欲しくない事だったのかもしれない。
桐野は煙草を取り出して咥えると、一度深く煙を吸い込んだ。
「まぁ、あんたには関係ない話だが」
「……うん?」
そう前置きして、桐野が静かに店を休むことを告げる。想像もしていなかった事で竜一は驚いて桐野の顔を見上げた。
「どうして? 休むっていつまで?」
「いつまでっていうか。決めてねぇけど、ちょっとの間だけな。勿論、また再開する予定だ」
「なにか……理由があるの? 俺で良ければ話聞くよ」
「あんたが心配するような事じゃねぇよ。ずっと続けてきたから少し休むだけで、深い意味はねぇんだ。会社員だって、有給とって連休にしたりするだろ? それと同じ。もう何年もゆっくりしてなかったからなぁ」
「そう、……なの?」
「そうそう。たまには休まねぇと、もう若くないし」
「それならいいけど……」
桐野の言っている事がどうもひっかかる。恋人(仮)の契約期間終了と時期が重なるし、前に桐野が言っていた『本当のお願い』に何か関係がありそうな気がしてならない。得体の知れない不安感は、考えるほど脳内で膨張しあれやこれやと推測の域を出ない想像が駆け巡った。
だけれど、どの結末も不穏な物ばかりで、冗談でも口にしたくない。竜一は疑問を自分の胸に押し込め残ったビールを飲み干した。
COUNT0….|創作BL小説|メンズラブ|
シリーズ『俺の男に手を出すな』メインの長編連載小説サイトです。病弱、ホスト、バンドマン、医者、眼鏡、強気受け、リーマン。