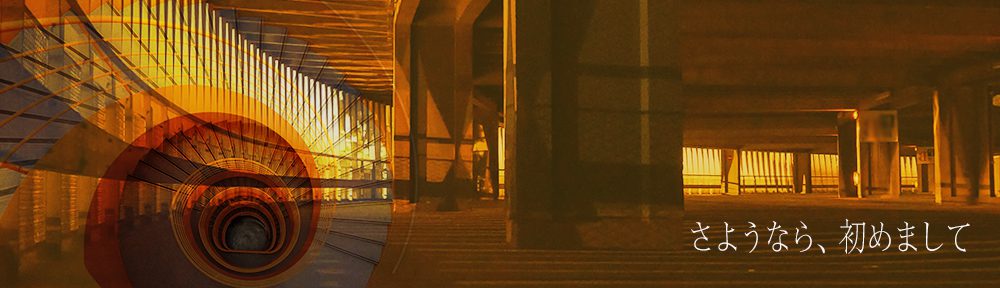──memory15──
* * *
永遠に終わらないかと思うほどの長い時間が過ぎ、手術中のランプが消えて桐野の手術が終わったと聞いた時は緊張の糸が一気に緩んだ。
医師に短く成功したとだけ聞かされ、笹松と二人で顔を見合わせ本当に良かったと心から安堵の笑みを浮かべた。
桐野が倒れたことは最悪の事態かも知れないが、それでもこの時は『もうこれで大丈夫なのだ』と何の確信もないのに思い込もうとしている自分がいた。
ナース室隣の集中治療室に呼ばれた笹松を横目に、竜一は薄暗い廊下の隅で脱力したように壁へと寄りかかった。
自分は身内ではなく赤の他人なので、笹松とは立場が違う。
「ここで待っています」という意味を込めて竜一が視線を向けると、その視線に答えるように笹松が足を止めた。
「佐久間さん」
小声で呼ばれて、それにまた小声で返す。
「はい」
「一緒に、説明を聞いていただけませんか……?」
疲労を滲ませた瞳が、少し細められる。笹松の背後から医師が送ってくる視線が明らかに急かしているのを感じ、竜一は慌てて壁から体を起こした。
「でも俺は……」
「お願いします」
一人では心細いというのもあるだろうが、気を遣ってくれているのだろう。竜一は黙って頷くとその気遣いを受け取り、笹松の後に続いて桐野の眠るベッドの側へ寄った。
繋がれている機械から規則正しく聞こえる電子音。
意識の無いまま静かに横たわる桐野に、笹松は「恭征さん……」と呟いてそっと手を握った。
緊張が緩んだのか、僅かに気だるげな声で医師が簡単な説明を始める。
暫くは目眩や吐き気、ふらつきがあるので安静にしていなければいけないこと。それでも順調にいけば十日程で退院出来るという事だ。
ただひとつ、肉体的な後遺症は別として、脳の機能については何が起こるか現時点では医師でも分からないのだそうだ。特に記憶の混乱や抜け落ちなどの症状は珍しくなく、一過性の物では無かった場合、退院してから一年ほどしてようやく気付くこともあるらしい。
しかし、いくら今説明されてもどこか教科書の症例を眺めている気分で、それが現実に桐野に起こるとは想像もしていなかった。医者は大抵最悪の事態を想定した言葉を言ってくると相場は決まっているからだ。
説明を終えた後、完全看護の病院なので付き添いは要らないと言われ、諸々の手続きを終えた笹松と後ろ髪を引かれつつも病院を後にすることになった。
夜間救急にタクシーで駆けつけた老夫婦が看護師に案内されているのを横目で見ながら自動ドアを抜ける。
当然だが、外は誰一人歩いてもおらず静まりかえっている。
澄んだ空気が余計に寒さを増長させているようで、竜一は真っ白な息を長く吐きだした。
出会ったばかりの笹松と二人で道を歩きながら話すのは桐野の事だ。
共通の話題がそれしかないので仕方がない。他に何を話せば良いのかもわからないままノロノロと歩き、フと疑問に思ったことを竜一は口にした。
「そういえば、笹松さんは桐野さんのお父様の秘書をされているんですよね?」
「ええ、そうです」
「連絡は……。ついたんですか? 心配されているんじゃ」
桐野が運ばれてすぐに笹松が連絡を入れているのを知っていたけれど、あえて聞いてみた。
結局桐野の元には誰も駆けつけてこなかったからだ。普通の親ならば、息子が倒れたとなれば何を置いても駆けつけるはずではないのだろうか。誰もこない病室を思い返すと、桐野が可哀想に思えた。
「心配は勿論されています。ですが、すぐには来られない理由があって……」
少し言いづらそうな笹松に気付き、竜一は慌てて言葉を取り消した。
「すみません。余計な事をきいて」
「…………いえ」
笹松が自嘲するように首を振り、「でも……」と言いかけてフッと苦笑する。
「……息子の顔を見に来るのに理由が必要なんて、ホントおかしな話ですよね。馬鹿馬鹿しい……」
らしからぬ物言いに面食らい、竜一は言葉を返せずにいた。笹松は言ったあとに冗談交じりで訂正を付け足す。
「すみません。今のは聞かなかったことにしておいてください」
色々と複雑な事情があるのだろう。
竜一は笑みを浮かべて「はい、もちろん」と一度だけ頷いて見せた。
「佐久間さん、少しどこかで話せませんか?」
「……今から、ですか?」
「ええ。何だか一人になりたくなくて……。少しで良いので付き合って頂けたら嬉しいです。あと、佐久間さんに渡したい物があるんですよ」
「渡したい物? ……わかりました。俺で良ければ」
「良かった。有難うございます」
笹松が安心したような笑みを浮かべる。
今夜は色々な事がありすぎて、一人になりたくないのは竜一も一緒だった。
終電も終わったこんな夜更けに開いている店は限られていて選べる状態ではない。少し離れた場所にある24時間営業の喫茶店が誘うように光を漏らしており二人で足を向けた。
店内は先客が一人いただけでガランとしている。
カウンターでオーダーしたコーヒーをトレイに載せて笹松と二人窓際の一番端の席へと腰掛ける。直接吹き付ける暖かい風で強張っていた体の緊張が僅かにほどけていくようだ。
店内をぐるりと見渡した笹松が静かに呟く。
「さすがに人が少ないですね」
「こんな時間だし。俺もこの時間に喫茶店へ来たのは初めてですよ」
少し笑ってそう言うと、笹松は「私もです」と苦笑した。
「今日は本当に佐久間さんが一緒に居て下さって助かりました。改めて御礼を言わせて下さい」
「いや、そんな。俺の方こそ、一人じゃどうなっていたか……」
深々と頭を下げた笹松に釣られて竜一も頭を下げる。自分のスーツとは全く違う仕立ての良さそうな三つ揃い、ブランドには詳しくないがはめている時計も高級そうに見える。
こんな事が無ければ、二人でお茶を飲む機会なんてなさそうな相手だ。
二人で熱い珈琲を一口飲み漸く一息つくと、笹松が早速話を切り出した。
「先程の話の続きですが、その前に私の名刺を渡しておきます。今後連絡を取らせて頂く事もあるかもしれないので」
「あ、じゃぁ俺のも」
慌てて名刺を鞄から取り出すと、雑に入れていたせいで角が少し折れている。爪で強引にまっすぐに直してから竜一は手を添えて差し出した。
「有難うございます」
交換した名刺に何気なく視線を落とし、竜一は目を瞠った。
笹松の名刺に書いてある社名、それは桐野と最初に出会った、彼が昔働いていた大手玩具メーカーだったのだ。瞬時にそういう事だったのかとパズルのピースがはまるように脳内で合致する。
「あの……。桐野さんのお父様はこちらの会社の……」
「ええ。恭征さんのお父様は最近引退されて今は会長です」
「……っ」
竜一は今まで知らなかった桐野の事情を初めて知った。
桐野はその会社の一社員ではなく社長の息子だったのだ。現在は桐野の兄が社長職に就いているそうだ。笹松は、長年秘書として桐野の父親についていた自分の父の後を継ぐ形で秘書になった事、桐野家とは長年家族同然にしていると手短に説明した。
昔はともかく、屋上で会った時の桐野の様子からして、まさかそんな大企業の子息だとは想像もしていなかった。以前竜一に、会社を辞める決断をさせてくれたのは竜一のおかげだったと話していたあの頃から、桐野は家族と確執があり、今ではすっかり疎遠になっている状態だそうだ。
「だから、今は一人であの店を……」
少し同情を含んだ言い方をしてしまった竜一に、笹松はそうではないというように首を振った。
「恭征さんは、昔からあぁいうオモチャ屋を自分で開くのが夢だったんです。だから、本人にとっては、うちの会社に勤めていた時より、夢を叶えた今の方が幸せなんじゃないかと思います」
「……そうだったんですか」
桐野が会社を辞めたきっかけを知りたいけれど、部外者の自分がそれを聞くのも図々しい気がして竜一は言葉の代わりに、手持ち無沙汰に珈琲カップを持ち上げた。
「佐久間さんは、恭征さんと……恋人として交際をしていらっしゃるのですか?」
ストレートに投げかけられた唐突な言葉に思わず珈琲を吹き出しそうになり、竜一は何度か咳をして一緒に持ってきていた水を一気に飲み込んだ。
「すみません。急に」
「いえ、っ」
「恋人かどうか深く追求するつもりはありませんが、恭征さんが貴方のことを特別に大切にされているので、そうかなと思いまして」
「え? 俺が特別……?」
笹松の言葉を不思議に思い、桐野との関係を詳しく話していないのに何故? という気持ちが湧いた。
「佐久間さん、今日、私が来る前まで恭征さんの自宅へいらしたんですよね?」
「はい。ここ最近よくお邪魔していて……何度かは泊まらせて貰ったりもしています」
「そうですか。ご存じないとは思いますが、恭征さんが身内以外で自宅に誰かを入れたのは佐久間さんが初めてだと思います」
「……え?」
驚いて竜一は目を丸くした。
屋上で再開したあの日だって、出会ってすぐに「うちに寄っていくか?」と誘ってきたはずだ。言葉に詰まる竜一に、笹松は優しく笑いかけた。
「あの人、結構自分のテリトリーに人を入れない性格なんです。幼い頃から接している私は許して貰っていますが、実の兄や父親でさえ、まだ一度も自宅へは招いたことがないはずです。それはまた別の理由があってのことだとは思いますが……」
「そ、そうだったんですか」
「はい。なので、佐久間さんは恭征さんにとって特別な……、心を許している方なのだと勝手に解釈しておりました。恭征さんに、そういう心を開ける相手がいて安心しました」
あんなに気さくな人間に見える桐野の意外な一面。
そして自分はそんな桐野に近づくことを許されていた一人だったのだ。
そこまで桐野に信頼されていたと知ってしまえば、静かに喜びの感情が湧いてくる。
「それと、これ。さっきお話しした物です。佐久間さんにお渡ししておきます」
手持ちの鞄から大切そうに取り出してスッとテーブルへ置いたのは手紙のようで、宛名には竜一の名前が書いてあった。
「これ、は……? 俺宛ですか?」
「病院で渡そうと思ったのですが、タイミングが無くて……。先日恭征さんに、『自分にもし何かあったら渡して欲しい』と頼まれていた物です」
「桐野さんに……」
「まるで倒れることを知っていたみたいですよね……。いや、あの人のことだから、医者からいつ倒れてもおかしくないと聞かされていたのかもしれません……。そういう部分は一切人に見せないので、あくまで私の予想でしかありませんが」
桐野は薄々こうなることを予期していたというのか。
竜一は、恐る恐る封筒を手に取ると笹松に「今開けてみても良いですか?」と訊ねた。
「どうぞ、私は中を見ていませんから安心して下さい」
笹松の言うとおり封は糊付けされている。
笹松の言葉に甘え、手紙を読んでみることにした。爪で上の部分をちぎり封を開けると、シンプルな便箋が一枚だけ入っていた。取り出した便箋を持つ手が震え、一度深呼吸をする。
これがもし本当に最後の別れの手紙だったら……。
そう思うと急に読むのが怖くなったが、ここまできて「やっぱり読まないでおきます」としまうのも気まずい。
笹松はわざわざ見ないようにしてくれているのか携帯を取りだして操作し始めている。
意を決して手紙に視線を落とすと、耳元で桐野の声が聞こえる気がした。
まるでこの手紙を傍で読んでくれているような……。
『佐久間 竜一様』
丁寧に書かれた文字を追っていく内に、文字が体に浸食してきて胸が苦しくなる。
堪えた感情が胸をいっぱいにして喉に溢れ、息をするのさえ邪魔してくるのだ。
一行、ツンと痛む鼻の奥をごまかすように鼻を擦り。
また一行、それでもごまかしきれない涙が竜一の目にうっすらと溜まっていく。
笹松と一緒にいるのに泣いたりしたら驚かれるだろう。必死で堪えて最後までを読みきる。
あまりに力を入れて握っていたからなのか、手紙を持っている部分が皺になっていた。
――桐野さん……。
心の中で、届かない愛しい相手の名前を呼ぶ。
自分があの時に感じた感情は間違っていなかったのだ。
別れ話を切り出されて最後に家を出るまで、桐野はまるで別人のようで違和感を拭えなかったし、なにより「もう俺みたいな男につかまるなよ」と言った桐野の表情がその言葉とは裏腹に酷く寂しそうだったのが頭から離れなかった。
あの時は気が動転してそのまま出て行ってしまったけれど、冷静になって考えて見るとおかしな点はいくつもあった。急にどうしてこんな事になったのかと何度も何度も考えていた。
その答えがこの手紙には書いてあったのだ。
自分は持病がありいつどうなるかわからない。その事に巻き込みたくないので関係を終わらせようとしたこと。
竜一との恋愛に嘘は無かった事。新しい恋人を作って幸せになってほしいと心から願っていること。
最後には、短い間だったが有難う、楽しかったと感謝の言葉が添えられていた。
読み終えた手紙を封筒に戻しながら、竜一は頭の中で、書かれていた沢山の言葉を反芻した。
ちゃんと互いに想いが通じていたのだという喜びと、桐野が目が覚めたら、また一から一緒にやり直したいという未来の希望。もし桐野に何か後遺症が残ったとしても、今度は自分が桐野を支えていきたいと強く思った。
「手紙、確かに受け取りました。有難うございます」
「いえ」
読み終えた手紙をそっと自分の鞄にしまうと、竜一は煙草を一本取り出した。
「吸っても?」
隣に短く問うと「どうぞ」と返ってきて、笹松は今まで見ていた携帯を閉じ、ぬるくなったコーヒーカップを持ち上げて口を付ける。そのあと小さく溜め息をついた。
「……佐久間さんが羨ましいです」
「……え?」
切なげな表情を浮かべている笹松が視界に映る。
「どうしてですか? 桐野さんも笹松さんには気を許しているじゃないですか」
「私は、貴方とは別の意味で恭征さんに必要だからって理由ですよ。先程少しお話ししたように、現状恭征さんは家族と疎遠です。私はお父様の秘書ですから、ただの橋渡し……いえ、伝書鳩程度の存在です」
「そんなことは……」
「私も、昔はこうではなかったんですよ」
笹松が何かを堪えるように口をぎゅっと結ぶ。
「こうして話しているのも何かの縁だと思うし、良かったら話して下さい」
「いいんですか? ただの昔話ですけど……」
「聞かせて下さい」
笹松は、普段はこんな事は話さないのだと前置きをしてからゆっくりと話出した。
「私は一人っ子なので、恭征さんがまだ自宅にいらした頃は実の兄のように慕っていました。急逝した父親の跡を継いで夢を諦め秘書になると決めた時も、最後まで私の事を思って反対し、一緒に何か別の方法がないかを探してくれたのも恭征さんです。私に夢を諦めるなと応援してくれて……」
「…………桐野さんらしいですね」
人の夢を馬鹿にせず、真剣に応援できる人間はそういない。笹松にとって桐野がどんなに心強い存在であったか、それは自分の想像を超える物だったのだろう。
「だけど、詳細は伏せますが……。恭征さんが会社を辞めた原因となる出来事がありました。その時、恭征さんがどんなに苦しんでいるかを知りながら、私は社長側につきました。立場的に社長秘書でもあったので当然なのですが……そのせいで恭征さんは社でも益々孤立し、最後には去って行きました。私は引き留めることもしなかった」
「それは……」
「社長命令とはいえ、恭征さんが一番嫌がる事を私は率先して実行していたんです。それからですね……。今のような関係になってしまったのは……。もう恭征さんには、愛想を尽かされていて家にも本当は来てほしくないと言われています」
「その過去のこと、後悔、しているんですか? 桐野さんなら、きっと話せば分かってくれるんじゃ」
「今の私では無理でしょうね……。私はこうなることを理解っていて選んだんです。自分の行動の責任は自分でとるしかないでしょう? 恭征さんのように強い意志を貫けない私には、選択肢がそれしか無かった。仕方がないんです」
「…………」
とても納得しているようには聞こえないけれど、笹松のプライベートな事情を知らない自分がかけられる言葉は少ない。
「笹松さん」
「……はい」
「笹松さんは、俺よりずっと若いですよね? まだこれから先は長いはずです。今は無理でも、諦めなければいつだって「もう遅い」事にはならないと思います」
「……っ、」
「俺も、桐野さんと付き合うようになって、やっとそう思えるようになったんです。だから……」
笹松は嬉しそうに目を細め竜一を見た。
「有難うございます。初めて会った佐久間さんにこんな話を聞かせてしまうなんて……」
「いえ、俺は部外者だし。口は堅いですから、笹松さんが話したくなったら聞くぐらいはいつでもできるから話して下さい」
「嬉しいです。なんだかずっと抱えていた重さが少し軽くなった気がします。佐久間さんのおかげで」
笹松は少しスッキリした表情をしていて、話を聞いてあげられて良かったと思った。
「恭征さんが、佐久間さんを選んだ理由、私にも少し分かる気がします」
「えぇ? 俺はただの会社員で、褒められるべき所も無いような人間ですから」
「そうでしょうか」
笹松がそう言った瞬間、笹松の携帯が鳴り響いた。静かな店内に響き渡ったその音に二人でびっくりして相手を確認すると、病院からである。
急いで携帯を持って店の外へ走って行った笹松が、電話を切ってすぐに戻ってきた。
「佐久間さん!」
「な、何かありましたか!?」
「恭征さんの意識が戻ったみたいです。一度顔を見に戻ってから帰りませんか」
「本当ですか!? 良かった! はい、行きましょう」
桐野の意識が戻った。成功したと言われた手術でも、意識が戻らないまま眠り続ける桐野を見ているだけでは実感が湧かなかった。自分が行ったら、桐野は驚くだろうか。
最初に、なんて声をかけよう。
そんな様々な事を考えながら、急いで喫茶店を出て病院へと戻った。
廊下を走ってはいけないとわかっているけれど、病院に辿り着いた途端早足以上の速度で桐野の元へ向かう。集中治療室の手前には看護師がいて、急いで戻ってきた自分と笹松に「良かったですね」と嬉しそうに微笑んでくれた。
中では医師の診察を終えたあとの桐野がベッドに目を開けて横たわっている。
――本当に意識があるんだ!
喜びを噛みしめて静かに入ると、桐野がすぐに笹松を見つけて気まずそうな笑みを浮かべた。
「郁人か……。なんだか……、迷惑掛けちまったみてぇだな……」
「迷惑だなんて、全然。でも本当に良かったです。自宅で恭征さんが倒れているところを発見した時は生きた心地がしませんでしたよ」
「……悪い」
「そうだ。私の顔は見たくないかも知れませんが、実は佐久間さんも来てくれてるんですよ」
喜ぶだろうと思ってそう言った笹松の言葉に、桐野は特に反応を示さなかった。
あまりベッド脇で騒がしくするのもまずいと思い、少し離れて立っていた竜一を笹松が手招きをして呼ぶ。
立ち上がった瞬間桐野と目が合った。
竜一はあまりの嬉しさに安堵の混じった笑みを浮かべて桐野を見つめた。
しかし、桐野は不思議そうな表情で竜一を見ているだけだった。声も掛けてこないし、すぐに外された視線は笹松の元に戻る。
――……どうして。
何かがおかしいと瞬時に察した竜一は、一歩を踏み出せないまま立ち竦んでいた。
次の瞬間、桐野の発した言葉に頭を殴られた気がした。
「そいつ誰だ? ……。郁人の知り合いか?」
そんな人間が今どうしてここにいるのかとでも言わんばかりの怪訝な表情。眼鏡を掛けていないせいで見えないというのも差し引いても、もうごまかしようがない。
桐野は、自分の事を覚えていないのだ。
ショックで笹松の言葉が遠くに聞こえ目の前が真っ暗になる。
「恭征さん、何を言ってるんですか……?」
竜一は自分の顔をもう一度まじまじと見る桐野の冷めた双眸に耐えられず顔を隠すように俯いた。自分と同様に驚きを隠せない笹松の腕を引っ張り、離れた場所から竜一は桐野に頭を下げて部屋を出た。
「笹松さん、ちょっと」
桐野の方を見ずに廊下へ笹松を引っ張っていくと、笹松も動揺した表情で竜一を見上げた。
「きっと、今は混乱しているだけですよ。そうに違いありません。だって、恭征さんが貴方のことを忘れるはずが」
「いいんです。俺は大丈夫。折角今意識が戻って安定しているのに。桐野さんを混乱させて負担を掛けたくない。だから、今夜はこのまま帰ります。笹松さん、一つお願いがあります。俺の事はうまく知り合いとか運転手だとか言ってごまかしてくれませんか」
「でも、それじゃ佐久間さんが……」
「桐野さん自身から、俺の話が出るまで俺の事には触れないでいてあげて下さい」
真剣な竜一の覚悟を悟ったのか、笹松は唇を噛みしめて頷いた。
「…………わかりました。佐久間さんがそう仰るなら」
「後は宜しくお願いします。今夜はお疲れ様でした。何かあったら電話下さい」
「はい……。気をつけて。佐久間さんもお疲れ様でした……」
「それじゃ、失礼します」
ずっと背中を見ていた笹松の視線が消えるのを感じると、竜一は走り出して病院を飛び出した。
桐野の中には自分への記憶が無い。
昔あったあの日のことも、再開してから今日までのことも、竜一を屋上で助けてくれたことも、なにもかも。
――俺が、あんたを修理してやる。何でも直せるってのは誇大広告じゃないんだぜ? だから、死ぬな
――じゃぁ、……一ヶ月。俺の恋人になってくれ
――大丈夫だって。約束しただろ? 俺が、あんたを治してやるって
次々と浮かんでくる桐野が掛けてくれた言葉、悪戯好きで冗談ばかり言う笑顔、心配そうに覗き込む優しげな瞳、抱き締めてくる腕はいつも力強くて、何度も救って貰った。
桐野が「大丈夫だ」というと本当に大丈夫な気がして、桐野の存在にいつも頼っていたように思う。自分の中に残る桐野との記憶が洪水のように溢れ出て乱暴に脳内を掻き乱す。
走って走って気付けば病院からはすっかり遠ざかっていた。
側にあった電柱にすがりつき、乱れた呼吸を整える。
医師の言っていた一過性の物かも知れない。そう思い込もうとするけれど、笹松のことはちゃんとわかっていて、状況だって把握しているようだった。そう考えると、桐野が自分の事がわからないのは一過性の物ではないとしか考えられない。
桐野が向けてきた何の感情もない視線を思いだして、ゾッとする。
電柱に背を預けずるずるとしゃがみ込んだ竜一の視線の先には、桐野と訪れた公園が見えた。
パンダに似た遊具で大笑いしたのはついこの前だったはずなのに。
「桐野さん、……」
竜一はヨロヨロと腰を上げ、公園に入っていった。
誰も居ない公園。錆びた遊具を静かに照らす月明かり。
大切な人の中から自分だけが消えてしまったという事実は、経験したことがないほどの苦しみだった。
嗚咽が漏れる。
癖がついた横隔膜が体を揺らし、声を押し殺したまま竜一の目からはとめどなく涙が溢れた。
感傷に包まれた背中は小さく震えたまま、消え入りそうに震え続けた。
COUNT0….|創作BL小説|メンズラブ|
シリーズ『俺の男に手を出すな』メインの長編連載小説サイトです。病弱、ホスト、バンドマン、医者、眼鏡、強気受け、リーマン。