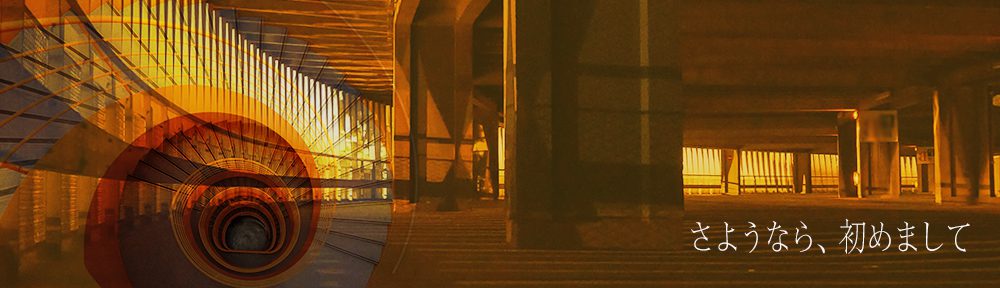──memory11──
ほんの数時間前まで竜一といたというのが嘘のように、桐野の気分は少しずつ下降線を辿っていた。
午後に雨が降ると天気予報で言っていた通り、今朝は眩しい朝陽さえ感じず、見上げた空は厚い雲で覆われたままだ。
自動ドアを抜け、消毒液のような独特の病院の匂いを感じながら診察券を出し、一番出口に近い席へと腰を下ろした。
待合室の窓から見える駐車場では、予備の傘を持った人間が出たり入ったりしている。
――夜になったら、降ってくるんだろうな……。
ぼんやりと、竜一は傘を持っていなかったなと思い出す。
今朝は二人して寝坊してしまい、それはもう嵐のように大慌てで桐野の家を出て行ったのだ。勿論のんびり天気予報を眺める時間もなく、焦る竜一に釣られて、自分でさえ傘を貸すという考えも浮かばなかった。
目覚ましを掛けたはずが鳴らなかったのか、それとも鳴ったけれどどちらかが止めてしまったのか、真相は不明である。しかも、今朝はそれだけではなかった。
慌てていたせいで、竜一が書類の入っているサブの鞄を置いたまま行ってしまったのだ。それに気付いたのは、竜一が出てから十分後。
そこから竜一に連絡を入れ、駅の改札まで走って行ってなんとか渡すことが出来たのだ。
結果オーライではあるが、こんな慌ただしい朝は滅多にないので、午前中だというのに疲労感が半端ない。自分の年齢を嫌というほど実感してしまった瞬間だ。
後ろ髪に豪快な寝癖を残したまま出て行った竜一の様子を思い浮かべ、桐野は少しだけ思い出し笑いをした。沈む気分がその瞬間だけフワリと軽くなる。
次々と思い浮かぶ竜一の表情は、出会った頃の陰鬱な物を塗り替えたように笑顔ばかりだ。すっかり警戒心を解いた竜一が「桐野さん」と懐いてくるのを見ていると、昔に戻ったのかと錯覚しそうになる。
来週で約束の期日が来る。
今になって思えば、あの約束をした事は失敗だった。そう考えているのがいい証拠だ。
こんな気持ちになるなら、いっそ出会った日に泊めたりせず、あのまま互いに別れていた方が良かったのではないかと思うほどに。
自分に向けられる竜一の笑顔がこんなにも大切だと思い知った今、自分がその笑顔を再び消してしまうのが怖い。押し寄せる後悔と、やりきれない気持ちがないまぜになって、澱のように胸の中に沈んでいく。
一ページも捲らないままの週刊誌を膝の上に広げたままいると、漸く順番が回ってきた。
「桐野さん~。14番でお待ちの桐野さん、お待たせしました。3番検査室へどうぞ」
少し先のドアから顔を覗かせた看護師が明るい声で順番を告げる。桐野はハッと我に返って「はい」と聞こえる程度の声で返事をし、硬い待合室のソファから腰を上げた。
入院棟から診察に来ているのか、点滴を下げたままの老人の横を通り、冷たい扉に手を掛ける。
薄暗い検査室へ入り一通り準備の説明を受けるが、もう何度目かわからぬほどの経験をしているので説明はほとんど聞いていなかった。いつも通り指定の服に着替え、身につけている物を外していく。
すぐに通された検査台に靴を脱いで身体を横たえると、検査室からの音声で始まりを告げられた。
「じゃぁ、今から機械に入りますね。頭の上で手は緩く組んだ状態で、動かないで下さい。中では声が聞こえないので、ご気分が悪くなったら手を挙げて下さいね」
「……はいはい」
閉所恐怖症でもないので、何の問題もない。
雑な返事を小声で呟き、桐野は目を閉じた。
耳に掛けられたヘッドフォンから聴き慣れたクラシック音楽が小さく流れだす。一分もその曲を聴かぬうちに機器が撮影をする際の轟音でかき消され、その後はひたすら騒がしいのを耐えるだけだ。
リラックスさせる効果を狙っているとしても、全く聞こえない曲にその効果はあるのか。寧ろ天井に綺麗な絵が描いてある方が見ているだけで楽しいので、そちらに切り替えたらいいのではと毎回同じ事を思ってしまう。
暫くガタガタと動いていた機器が動きを止め、検査室の向こう側から「これで終わりです。お疲れ様でした。楽にして下さい」とアナウンスが入る。
再び着替えて検査結果を聞くために待合室へ戻ると、すぐに名前を呼ばれた。
後ろ手でドアを閉め中に入っていくと、いつもの主治医が「どうぞ」と目の前の椅子へ着席を促す。
その姿を見て、三年前に初めて受診した時より、かなり白髪が増えたな。なんて、どうでもいい事を考えた。
「どうですか? 最近は。頭痛が酷くなったり、他の症状が出てるんじゃないですか?」
結果を見て、当然わかっているのだろう。ここで嘘を言っても脳内の写真まではごまかせない。桐野は出来るだけ軽い口調で答えた。
「数日に一回ぐらいは。でも、今はまだ出されている薬を飲むとなんとか治まります。あとは……、手が痺れる事が最近多くて、細かい作業が難しくなった……。顕著なのはそれぐらいかな」
「なるほど」
カルテに走り書きをした後、丸椅子をクルリと動かし、桐野に向かい合うと医師は腕を組んだ。
「桐野さん、それはね、あなたの運がいいだけですよ」
「どれぐらい喜ぶべきですか?」
桐野が苦笑すると、医師は困ったように眉を下げて組んでいた腕を解いた。
備え付けられた縦長の液晶画面に、ここ数年の自分の経過が写し出される。
「これ、右側が一年前の状態ね。そして真ん中が先月、今回のが左側。桐野さんの腫瘍はここ。よく見ていて下さいね」
「……」
見せられているのはコマ送りで進んで行く自分の脳内の写真だ。少しずつ変化する様が、まるで天気予報の雨雲レーダーのようだと感じた。
違うのは、翳された雨雲が通り抜けてなくならない事だけ。
相手の言わんとすることはわかった。途中何度か画面を停止させて説明をしながら最後まで見終えると、医師は神妙な顔で視線を一度落とした。
「ここ数ヶ月で急激に大きくなってきてるの、わかりますか?」
「ええ」
「今日の結果、ここを見てくれるとわかると思いますが、相当周囲を圧迫し始めてる。先日お伝えした手術の件、そろそろ覚悟を決めて頂かないとタイムリミットです」
「……そうですか」
納得したのかどうかも曖昧な返事に、医師の眉が少しだけ険しくなった。
「桐野さんが、まだ普通の生活が出来ているなんて、正直この結果から考えると不思議で仕方がない。そんなレベルです」
「はは……、運がいいのだけが取り柄なんで」
桐野の冗談に、医師が苦笑する。
本当はあと一週間猶予があるはずだったのだ。
先日の検査結果で、一ヶ月後を目処にして、手術をする段取りだった。
「来週あたりどうですかね?」
「来週? 明後日からの週ですか?」
卓上カレンダーを見ながら、心の中で既に何度目かの溜め息をついた。
「そうです。本来は今日にでも手術した方がいいような状態です。このままだと手術のリスクも益々高くなりますよ。覚悟、決めて下さい」
手術が怖いわけではない。ただ、その手術によって起こるかもしれないという事実が中々受け入れられなかった。
「……」
「先日お伝えした件で不安なのはわかりますが……、早ければ早い方が……」
促すように言葉を追加され、もう逃げ場がないことを痛感する。
「わかりました。じゃぁ、来週で……」
「日程は後ほど看護師から説明させますね。入院から手術までの流れと、その後の説明がありますから、わからない事があったら遠慮なく聞いて下さい」
「はい、宜しくお願いします」
最後にもう一度主治医に礼を言って、診察室から出た。
その後医師に言われたとおりに看護師から部屋に呼ばれ、様々な説明を受け、病院を出たのは昼頃だった。
症状が出ていない時は全く元気なので腹もちゃんと減っているが、気分的にどこかで昼を食う気にもならない。
桐野は自宅とは逆方向の駅に向かって歩き出した。
ほどなくして辿り着いた最寄り駅にはさほど人はおらず、改札を入ってすぐにタイミング良く電車も来た。途中で一度地下鉄へ乗り換え、そこから十五分。
駅から目的の場所までは結構時間が掛かった。
寂れた商店街の突き当たりを曲がっていくとようやく見えてくる小さな工場。昔は倍ほどの敷地を持つ立派な工場だったが、今は見る影も無い。
売り払って金にしたのであろう片方の土地には、二年ほど前に五階建てのマンションが建てられていた。そのせいで工場のほとんどは薄暗い影に覆われてしまっている。
錆びた出入り口にはめ込まれたガラス部分は割れた物を修理していないのかビニールシートをガムテープで貼っているだけ。数人の従業員を雇い、経営するだけで精一杯なのだろう。
桐野はその工場の数メートル手前で足を止め、ここへ来るといつも入る喫茶店へ身を隠すように足を踏み入れた。
工場が見える窓際の席へ腰を下ろし、よく見えるように眼鏡を指の背で数㎝押し上げる。
特に何かが起きるわけでもない。日常の風景。
頼んだホットコーヒーの湯気が消える頃、一台のトラックがきて荷を積んで再び去って行った。
荷を積む際に、見慣れた女性が工場から出て来たのに気付き、桐野は視線で追った。汚れた作業着に不似合いなほどの笑顔を浮かべ、何度も何度も業者相手に頭を下げる様子をひたすら見つめる。
昔はもう少しふっくらしていた頬も、今はこけて随分痩せたようだ。
――……っ、。
こめかみからズキリとした痛みが駆け抜け、桐野は強くこめかみを押さえた。
ぬるくなった酸味の強いコーヒーを口へ運び、ごくりと飲みこむ。ズキズキと脈打つ頭痛が自分を責めているようだった。
当時、何度も謝罪に行ったがずっと会ってもらえず、葬儀があった際に父と出向いた時も焼香さえあげさせてもらえなかった。それでも自分は通い続けた。
季節も変わる頃、偶然買い物帰りの彼女と工場前で出くわし、やっときちんとした謝罪がさせて貰えると頭を下げ続けた桐野に、彼女は最後に言ったのだ。
『この人殺し! 主人が死んだのはあなたのせいです。……もう二度と、うちにこないでください。……出てって……。出て行ってよ!!』
叫ぶような心の悲鳴を投げられてそれ以上何も言えなくなった。頭を下げたままの視界に写る、彼女の、やりきれない不幸を握りつぶして耐えるその拳、それが小刻みに震えていたのも鮮明に覚えている。
――……当然……、だよな。
桐野は酷くなる痛みに、掛けていた眼鏡を外し震える手で額を押さえた。
この頭痛は、いつもの発作とは違う。ここに来ると必ずなるのだ。
寧ろ、この痛みを味わうのが今の自分に出来る精一杯の罪滅ぼしだった。忘れることのないように、月に一度はこうして足を運び目に焼き付ける。無力な自分が唯一出来る事はこれぐらいしかないのだから。
痛みが引いていったあとも暫く見続け、一時間程して桐野は席を立った。
勘定を済ませ喫茶店を出ると、その気温差に首筋がぞくりとする。駅までの道を引き返そうとしていると、すぐの所で携帯を見ながら歩いてきた一人の男と思いっきりぶつかった。
「あ、すみません。おれ、スマホ弄ってて……。大丈夫ですか?」
「……っ!!」
心配そうに様子をうかがってくる目の前の若者に、桐野は言葉を失っていた。いかにも真面目な新入社員といった感じのスーツに真新しいビジネスバッグ。若者は、様子のおかしい桐野に「あの……本当に、大丈夫ですか?」と声を落とし、顔を覗き込もうとする。
その瞬間、桐野はすぐに距離を取って視線を逸らした。
「ああ、大丈夫だ。こっちも、前を見てなかったから、その……悪かった。じゃぁ」
すぐに歩き出したが、背中にまだ視線を感じる。足早に歩きながら、駅へ着くまで一度も後ろを振り返らなかった。
郁人の言っていた言葉を思い出す。
――あそこのご子息の学費だってこちら側で払って、今は立派に働いているそうですよ。
間違いない。あの当時は確か高校生だったはずだが、大人しそうな雰囲気や、外見もさほど変わっていなかった。向こうが桐野に気付かなかったのが幸いだ。
立派な社会人になったのだなと、先程の姿を思い出せば、ほんの少しだけ肩の荷が軽くなった気がした。
* * *
再び電車に乗り最寄り駅へ帰り着いた頃には四時を回っていた。雨は未だに降ってきていない。
突然の遭遇に落ち着かない気分のまま家までの道のりを歩いていると、竜一と出会ったビルの前に出た。
足を止めて一度深呼吸をする。
桐野はビルの屋上を見上げ、曇り空から薄く射す夕陽に目を眇めた。
「……竜一」
一度もまだ呼んだことのない名を口にしてみる。
時間もあるのでもう一度屋上へ行ってみる事にし、あの日竜一と二人で降りた階段を一人で登っていった。やっと辿り着いた屋上にはやはり誰も居なくて、しかし、あの日と違い今日は夜中ではないのでジメジメとした暗さは幾分和らいでいる。
剥がれたセメントが乾燥した空気に舞って少し埃っぽく、何度か咳き込んだ。
桐野はゆっくり歩いて行くと、あの日のように煙草を取り出して一本咥え、柵へと腕を乗せた。
淡い夕色に染まる街並みに、紫煙のフィルターを吐きかける。渋いような煙草の苦みを舌にのせたまま小さく笑った。
――何が720時間もある、だよ。あっという間過ぎんだろうが……。
最初に自分が言った台詞だ。
竜一が自殺しようとしていた日、あの夜は、自分も今日行っていた病院の帰りだった。
三年前、たまに起こる頭痛が市販薬で治まらなくなり、軽い気持ちで初めて脳神経外科を訪れた。偏頭痛の薬も出して貰えると聞いていたし、自分に効く頭痛薬を処方して貰えれば薬局で買う手間も省ける。その程度の気持ちでの受診だった。
しかし、告げられたのは予想もしていなかった言葉だった。
初診なので一通りの検査をする事になり、CTからMRI全てを終える。
「腫瘍がありますね。これが頭痛の原因でしょう」
「え?」
「まだそんなに大きくないけどね」
モノクロの何だかわからない脳の写真を見せられたが、腫瘍という言葉が衝撃的すぎてあまり覚えていない。しかし、それはまだ本当に小さくて、このまま大きくならなければ経過観察で手術をするほどでもないと聞き、ほっと胸をなで下ろした物だ。
その時に処方された鎮痛剤は良く効いたし、体質的に腫瘍が出来やすいという事もあると医者が言っていたので、このまま痛くなったら薬を飲む程度でずっと過ごせると思っていた。
現に今まではそうして普通の生活を送ってきたのだ。
状況に変化があったのはここ半年だった。
腫瘍が徐々に大きくなってきたのだ。定期的に診察を受け、それが明らかになった。急激に肥大する腫瘍は悪性に移行する可能性が高いらしい。
僅かな可能性として、ある程度で肥大が止まることも、逆に小さくなることもあるらしいので、もう少し経過観察を続けたいと自分から申し出て渋々許可された。
しかし、二ヶ月ぐらい前からは処方された鎮痛剤もあまり効かなくなり、飲む回数も増えてきた。頭の中が急に圧迫されたような嫌な感じがした後、吐きそうになるほどの痛みが数分続く。その発作が起きると視界も狭まり、手足が痺れて立って居られなくなる。
細かい作業をしている時に起これば、それ以上は続けることが出来なくなった。
その頻度が増えていることで、自分でも薄々、悪化しているのだと感じていた。そして先月、このままだと命に関わるとついに手術を勧められたのだ。
腫瘍を取ってしまえるなら、それに越したことはないし、すぐに承諾するつもりでいた。
しかし、その後の医師の説明を聞いて気持ちが揺らいだ。
自分にとって命を落とすことより怖い事がある。
それは、記憶を失うことだった。
記憶の一部、もしくは数年分のどこかの記憶、誰かの記憶、または全ての事、それらがなくなってしまう可能性が高いと告げられたのだ。腫瘍の場所により、手術後の後遺症で様々な事が起きるというのは、調べて知っていた。自分の場合、記憶を司る部分の近くに腫瘍があるかららしい。
すぐには答える事が出来なかった。
自分には絶対失ってはいけない記憶があるからだ。
一生背負って生きていくつもりだし、どんな理由であってもその記憶を失うことだけは自分自身が許すことが出来ない。だから手術を保留にした。
先延ばしにも限度があるにしろ、少し考える時間が欲しかった。
その事を告げられた日、事実を受け入れられず自棄になり一人で居酒屋に行って浴びるほどの酒を呑んだ。酩酊に近い状態で帰り道を歩いていた際、このビルの屋上からネクタイが落ちてきたのだ。
竜一との再会は本当に偶然だった。
そのネクタイを拾い上げて柄を見た時、頭の中で何かが弾けたような感覚がして、当初惹かれていた気持ちが即座に蘇った。蘇ったのは竜一への気持ちだけではなく、その当時の全てが鮮明に思い出された。
屋上にいるのは竜一なのだろうか。
家族や仕事に対しての絶望を抱え、表面上を取り繕って過ごす毎日。
見て見ぬフリをしながら自分をごまかし、現実から逃げたまま罪悪感に押し潰されそうな日々を送っていた。そんな中、初めて竜一と出会ったのだ。何度か会う内に親しくなり、当時、自分が失った物を全て持っていた竜一に、自分は少しずつ仕事相手とは違う好意を抱き始めていた。
竜一と過ごす間だけは、余計な事を考えずにいられたのだ。
竜一を喜ばせたくて、彼の会社を使ってくれるようにと何度も担当部署に頼み込んだが、元々大手の印刷会社と長く繋がっていて見込みは限りなく薄かった。だけど、その事を告げれば、竜一は諦めてもう来なくなってしまう。
そう考えた自分は、嘘をついた。出来るだけ長く引き延ばせるように……。
そんな中、打ち合わせという名目で時々昼休みに食事を共にするようになった頃のことだ。
いつものように食事をしながら、他愛もない会話の一部として竜一に言われた言葉。その言葉を聞いた瞬間、長い悪夢から急激に目が覚めた気分になった。
――桐野さんみたいに、真摯に仕事に向き合っている人って本当に尊敬します。たまに思うんですよ。僕の上司だったらなぁ……なんて。いや、ただの憧れなんですけど。……桐野さんと一緒に仕事が出来る取引先の方が、正直、羨ましいです。
ただの社交辞令だったのかも知れない。
苦笑いしか返せなかった当時の自分は、真摯や尊敬とは真逆の場所に立っていた。
あの時自分は、自らが立っている足下に地面がないことに漸く気付いたのだ。
竜一の言葉を聞いて――もう、ごまかしながら生きるのはやめよう。と強く思った。竜一が憧れてくれるような自分でいたいと。
その後竜一の会社を使うことが出来なくなったと正直に伝えて謝り、そのまま関係は途絶え、自分は間もなくして勤めていた会社を退社した。
退社後も、竜一の名刺を取り出して連絡を取ろうとした事も何度もあったが、今の自分ではまだダメだと思い直し、そのまま月日が流れていった。
気付いた頃にはもう、過ぎた時間が長すぎて連絡する口実さえ何一つ残っていなかった。
そんな竜一との再会がこんな形で叶うなんて。
竜一が自殺をしようとしているのだと理解した瞬間、もう階段を駆け上っていた。竜一はきっと自分の事を覚えていないだろう。彼にとって、見知らぬ男でも構わない。だけど、どうしても死んで欲しくなかった。
結果、何とか間に合って引き留めることは出来た。
その安堵感と同時に酷くショックを受けている自分がいた。助けた竜一はまるで別人だったのだ。
自分が知っている明るくて一生懸命で眩しかった頃の面影はなく、光を失った瞳と陰鬱な表情。酷く疲れた様子の竜一は、自棄になっていた先程の自分の比ではないほど、死に近い場所へ立っていた。
「あんた、死のうとしてる?」
精一杯の冷静さを装って声をかけた自分に返された、なげやりな返事。
何があったんだよ、と問いただしたくなるのを抑えて必死で言葉を選んだ。
記憶を失うかもしれない自分がこの場面に遭遇したことが奇跡だというなら、そうなのかもしれない。当時の記憶が残っている時間の中で、もう一度彼の笑顔を取り戻せるのは今しかないと思った。
桐野は何本目かの煙草の吸い殻をつま先でつつきながら、冷たい手摺りに腕を乗せたまま長く息を吐いた。
一ヶ月後、全てのことを話した上で、
『俺がもし記憶がなくなったら、俺がどんな男だったかを、あんたに教えて貰いたい』そう竜一に告げようと思っていた。それが約束した願いの全てだ。
出会って間もない相手に、そんな重い使命を背負わせようとしている自分の身勝手さに今更気付く。
やっと見せてくれるようになった笑顔が、フェードアウトのように記憶からぼやけていき、桐野の手の届かない空へと舞い上がる。
桐野は息苦しげに空を仰いで、何もない宙を掴んで悔しげに奥歯を噛みしめた。
竜一との出会いは、間違いだったのかもしれない。
――あんたはそれを聞いても、まだ笑ってくれんのか?
誰も居ない空間に呟いてみても、返事は返ってこない。
失いたくない記憶が、またひとつ増えただけだった。
COUNT0….|創作BL小説|メンズラブ|
シリーズ『俺の男に手を出すな』メインの長編連載小説サイトです。病弱、ホスト、バンドマン、医者、眼鏡、強気受け、リーマン。