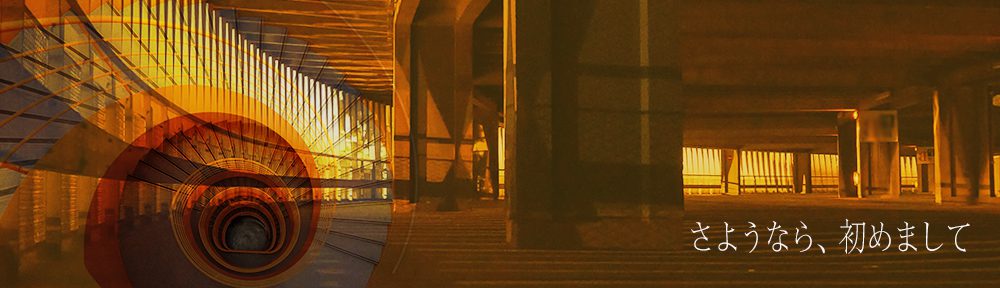──memory13──
暗い寝室のドアを開ける。
竜一の居るリビングの眩しさに、桐野は目を一瞬眇めた。竜一はとっくに拾い終えた缶をテーブルに置いて、戻ってきた桐野に安心したように振り向いた。
「何か思い出した用事でもあった?」
「ああ、まぁ、そんなところだ。もう終わったから気にしなくていい」
「そう? ならいいんだけど」
竜一は部屋の時計を確認して視線を戻す。
「そろそろ、一緒に夕飯買いに行かない? 俺、わざと買ってこなかったんだ。桐野さんと行こうと思って。この前食べたチーズもつまみに買ってこようよ」
何も知らぬ竜一から、変わらぬ楽しげ声が降ってきて、早くも決意が揺らぎそうだ。
桐野は竜一を目で追って、思い詰めたように表情を硬くした。和やかなムードを消し去るように、意を決して重い口を開く。
「飯の前に……あんたに話がある」
「え? ……うん。なに?」
「ちょっと、座ってくれ」
真剣な表情の桐野に驚いて、竜一は「うん」と小さく頷いて椅子を引いた。
食卓のテーブルに腰掛けると、入れ替わるように桐野はキッチンに向かいインスタントのコーヒーを淹れる。湯が沸くまでの数分、カップに注ぐ間の数分、少しずつ先延ばしされる時間を心に刻み、桐野はカップを二つ手に取ると竜一の目の前に置いた。
珈琲が目の前に置かれるまで、二人とも一言も口を開かなかった。
向かい側に腰掛けた桐野は、珈琲には手を付けず煙草を一本取り出して火を点ける。
邪魔そうに投げ出された桐野の組まれた足が僅かに揺れるのを見て竜一が息を呑む。
明らかな桐野の変化に不安になって、竜一は乾いた唇を一度珈琲で湿らせると急かすように自ら切り出した。
「話って、……何?」
「ああ……」
桐野は一本を吸い終わってから、低い抑揚のない声で話出した。
「俺たちの約束の件なんだが」
「うん。……あと一週間だっけ。いや、六日だったかな。あっという間だったなぁ……。桐野さんは、おぼえ、」
「今日で終わりにしてくれ」
――……え……?
竜一の言葉を遮って告げられた予想外の言葉に、頭の中が真っ白になる。
「……それって、どういう」
「急で悪いな」
「ちょ、ちょっと待って」
飲み込めない事態に、途中で一度竜一が深く息を吸う。
「それじゃ、桐野さんが俺にお願いしたいことを今日教えて貰えるって事?」
「いや、そういう話じゃない」
「じゃぁ、どういう意味……」
急展開を見せる状況に気持ちが追いつかず、竜一は不安気に表情を曇らして桐野をじっと見つめた。会った時から様子が違うと感じた原因は、最初からこの話をするつもりだったからなのだろう。さらに驚きの言葉が桐野から発せられた。
「約束も、なかった事にして欲しい」
「……、……」
明らかな拒絶に面食らい、先程までのんきに夕飯のことを話題にしていたのが嘘みたいだった。
この雰囲気はよく知っている。別れ話をするときの空気だ。今までだって何度も経験してきている、だけど、こんな予兆もなく突然訪れることは滅多になかった。
「……急にそんな、なにがあったの? 俺の、せい……?」
桐野の、身勝手としか説明しようがない言葉にも、竜一は怒るどころか酷く心配しているような表情を浮かべていた。いっそ「馬鹿にするな」と怒鳴ってくれた方がまだ楽になれたのにと桐野は思う。
そんな竜一を真っ直ぐ見るなんて到底出来るはずもなく、長く息を吐くと、もう一本煙草を取り出して咥えた。本当ならば、ちゃんと訳を話して、これからも傍にいて欲しいと、他の誰でもなく、竜一じゃないとだめなのだと。そう言ってしまえればどんなに良かっただろう。
ここへきてまだそんな事を考えているなんてどうしようもないなと思わず自嘲的な笑みが零れた。
桐野は気持ちとは裏腹の態度をとる事でなんとか気持ちを宥めた。
思い詰めていた空気を一掃するように盛大な溜め息をついてみせ、咥えたままの煙草を唇の上で揺らし小さく笑う。雰囲気の変わった桐野に、竜一は驚いたように目を瞠った。
今この状況は、笑えることなんてひとつだってありはしないのだから。
「あぁーあ。面倒くせぇな……。そんな深刻な顔すんなよ」
「そんな顔って……、桐野さん、どうしちゃったの」
「どうしちゃったって、別にどうもしねぇよ。とにかくそういう事だから、俺たちは今日で終わりだ」
「こんなの桐野さんらしくないよ。ちゃんと説明してくれないとわからない」
「俺らしくない? 随分俺の事に詳しくなった気でいるみてぇだな」
「っ、」
「短い間だったけど、十分楽しませて貰った。だからもう十分だって言ってんだ。あんたが知らないだけで、もともと俺はこういう男なんだよ。熱しやすく冷めやすいっていうか、飽きっぽくてな。恋人とだって長く続いた試しがねぇ」
「そんな……」
「それに、最初にちゃんと言ったはずだぞ。期限が来て、お互い付き合う意思がなければ関係は解消するって。まさか忘れてねぇよな?」
「……それは」
はっきり覚えているその約束は、事態を重く感じさせず安心させるための冗談だと思っていた。だけど、そうではなかったのだ。
「俺は、やっぱりあんたとは付き合っていけそうにねぇ」
「……どう、……して?」
「どうしてって、そりゃ、お試し期間で合わねぇなって思ったからだ。それ以外にあんのか?」
どうってこともない軽い口調でそんな事を言う桐野を、竜一は未だに信じられないという目で見ていた。桐野がこんな事を言うはずがないと今だって思っているが、それすら桐野の言う「詳しくなった気分」でいるだけだというのか。
目の前に居る桐野と、今まで一緒に過ごしてきた桐野がまるで別人で、どちらが本当の桐野なのか、わからなくなる。
思わず口をついた竜一の声は僅かに震えていた。
「…………合わないって。じゃぁ、……俺は? 俺の気持ちは?」
「なんだよ。俺の事、本気で好きになっちゃったとか?」
面倒くさそうにそんな事を言う桐野に、竜一は縋る思いで素直な気持ちをぶつけた。
「俺は、……俺は桐野さんが好きだよ。早く仮が取れればいいって、……ずっと思ってた」
「へぇ」
「そう思ってくれてるって、桐野さんも同じだって信じてたのに……。今までのは全部嘘だったんだ? ……俺の傍にいてくれるって、言ったのも全部」
「何ムキになってんだよ。人聞き悪ぃな。別に嘘じゃねぇだろ? 『恋人期間』はらしく振る舞ってやったじゃねぇか。お互い楽しんだんだ。それで十分だろ」
桐野のあまりに酷い言い種に、竜一は絶句した。
「…………」
今にも溢れそうな涙を堪えている竜一を目の前に、桐野は机の下で握りしめている拳に力を込めた。心が揺らぐ。竜一の泣いた顔を見たくない。だけど、これは一瞬だ。
真実を教えたら、竜一をずっと苦しめることになる。
それならば、泣かれようが恨まれようが、この方がずっといいと何度も自分に言い聞かせた。
「恋人期間だから……優しくしてくれてたんだ……。じゃぁ、最初のこの提案も、そんな気持ちで言ってたってこと?」
「あそこで死なれたら寝覚めが悪ぃからな。恋人ごっこにしては上出来だっただろ?」
竜一が言葉を一度ぐっと飲みこみ、爪が食い込むほど手を強く握っているのが見えた。 桐野は竜一から目をそらし、視線を彷徨わせた。今口を開いたら、全部嘘だと言ってしまいそうになる。
抑え込んだ幾つもの感情を持て余したまま、もう吸いたくない煙草に何度も火を灯す事しか出来ない。肺の奥が軋むように痛んだ。
互いに何も話さないまま、目の前の灰皿には吸い殻が溜まっていく。
暫く続いた沈黙の後、竜一が静かに呟いた。
「……わかったよ。約束通り、今日で桐野さんとの関係は終わりにする。勝手に期待した俺が馬鹿だったけど……、でも、俺は後悔してないよ」
「……」
「だけど、最後にひとつだけいいかな」
竜一は深く傷ついたのを隠しもせず、椅子から腰を上げる。桐野の前まで来ると静かに手を差し出し、儚げな笑みを浮かべた。
ほんの少し震えている指先が竜一の気持ちを代弁する。桐野は喉の奥に詰まった鉛を飲みこむように、苦しげな息を吐いた。
「……なんだよ」
「握手、してほしい」
顔を上げた竜一の目元には堪えきれない涙がぷくりと眦に溜まっている。黒目がちな潤んだ瞳から、それがこぼれ落ちないように竜一は指で素早くそれを拭う。胸を切り裂くような切なさを押し込めながら、桐野も大きな手を差し出した。
竜一の温かな手が重なり、握った手にギュッと力を込められる。何度も確かめるように、竜一は桐野の掌を握り返し精一杯の笑みを浮かべた。
「桐野さん、俺、最後はこんな終わり方になるとは思ってなかったけど、それでも感謝してるんだ。恋人期間、本当に毎日が楽しかったよ。あの時は、助けてくれて……、有難う……ございました。命の恩人です……」
「……、……」
握手したままの手を引き寄せて、今すぐ竜一を腕の中に抱きたくなる。傷つけたことを謝って、くだらない冗談を言って笑わせて……。
桐野は握られていた手を引き剥がすようにして離すと、ポケットへと突っ込んだ。
「それじゃ、帰るね」
「ああ」
玄関先まで無言でついていき、竜一の背中に視線を送る。もう二度と会う事はないであろうその背中が、今はやけに小さく見える。
靴を履いた竜一が振り返って、優しい笑みを浮かべる。その瞬間、竜一の頬を一筋の涙がツゥと零れ落ちた。
「さようなら、桐野さん」
ドアが閉まる直前、思わず「待ってくれ」と声をかけてしまった自分に、桐野は驚いて首を振った。一体何を言おうとしたのだと、自分でも呆れるしかない。
少し迷った後、引き留めたその背中に、桐野は別れの言葉を告げた。最後の言葉は、桐野の本心だった。
「もう、俺みたいな男にひっかかるんじゃねぇぞ」
竜一には、新しい恋をして幸せになって欲しいと心から思う。
その言葉に返事はなくて、一度も振り向くこともなく竜一が玄関を出て行く。閉まったドアの向こう、竜一が階段を下りていく足音が聞こえ、それも少しして聞こえなくなる。
桐野は静まりかえった部屋に戻ることもせず、玄関でいつまでも立ち尽くしていた。
――これで、良かったんだ。
「さようなら、桐野さん」涙声でそう言った竜一の顔、そして言葉が耳にこびりついたように離れない。鼓膜を何度も同じ台詞が通り過ぎ、急に目の前が暗くなった。いつもと違い激しい痛みは感じない。ただ意識が揺らいでいく中、足下が溶けて沈み込む感覚がする。
――……っ、
縋るように柱についた手は身体を支えきれず、桐野は滑る柱に必死で爪を立てる。視界が暗い、飲みこまれていく闇の中、最後に見えたのは竜一の笑顔だった。
――……竜一、ごめんな……。
誰も居ない部屋の中、桐野が床へと倒れ込む音が大きく響いた。
* * *
数時間前に桐野の家に向かっていた時はあんなに浮かれていたのに、あれは夢だったのではないかと思うほどに状況は変わってしまった。油断すると溢れそうになる涙をぐっと堪え、竜一は階段を下りた。
今だって、桐野が言ってきた全てを信じられないでいる。
閉まっている店のシャッター前で足を止めると、先程まで見ていた中の様子が思い出される。あの時には既に別れ話をする予定だったのだろう。
――どうして? 何故?
桐野が自分とは合わないと思った直接的な理由を知りたかった。そうしたら、今だってもっとちゃんと受け入れられたはずなのに。
最後に桐野がかけてきた言葉、その言い方が酷く寂しそうで余計に混乱する。
一晩ゆっくり考えて、納得するしかないのだろうか。それでも無理ならば、もう一度だけでいいから桐野と話す機会があれば……そう思いながらも暫くその場で考えていると、背後から足音が近づいてくる事に気付いた。
泣き顔を見られてはまずいと咄嗟に俯いて顔を隠すと、足音の主は竜一の背中を通り過ぎて、いましがた下りてきた桐野の家へ続く階段を上っていった。
――……あれ?
一瞬見た横顔、きちんとした身なりのすらっとした体躯、その姿には見覚えがあった。
いつだったか、桐野の家へ会社の帰りに急に寄った際にいた先客だ。桐野曰く、身内のような物だと言っていたはずだ。
桐野が出て来るかもしれない。そうしたら、まだここに居たのかと思われてしまう。足早にその場を去ろうとした時、背後から男の悲痛な叫びが聞こえた。
――……!?
今向かって行った男の声だ。それにびっくりして竜一は思わず足を止めた。
「恭征さん!!! 恭征さんっ!! どうしたんですか! しっかりしてください」
桐野に何かあったのだろうか、そう考えた瞬間心臓が縮み上がり背筋が冷たくなる。
ただ事ではない様子を感じたと同時に、身体が反射的に方転換をし走り出した。竜一は急いで階段を駆け上った。
「恭征さんっ!!!」
縋り付くように体を揺すっている男の声の奥へ視線を向けると、信じられない光景が広がっていた。
そこには数分前まで一緒に居た桐野が倒れている。精悍な顔立ちは色を失い、乱れた長めの髪が床に無造作に散らばっている。
――何が、起きて、……。
衝撃を受けて足が竦み、掛けようとしていた声が出せなくなった。震える膝をなんとか押して近寄った瞬間、恐怖で全身が泡立つ。
「き、桐野さん、っ……」
恐る恐る腕を伸ばして桐野に触れると酷く冷たくて、もう息を引き取ってしまったかのように感じてゾッとする。引き攣った声が竜一から聞こえたことで男が驚き、弾かれたように振り向いた。
「あ、貴方は!? さきほど下にいた方ですか……」
見開かれた男の瞳の中に自分が写っていて、竜一は状況を飲み込めないままなんとか我に返った。
「……っ。突然、すみません。さっきまで桐野さんと一緒に居たんです。数分前までは普通に話してて」
「私も今来たばかりで、鍵が、空いていたので。そうしたら、恭征さんが……倒れてて」
どうしようと言いながら口元を抑えている男は、端から見ても酷く動揺している。
「と、とにかく、救急車を。救急車を呼ばないと」
男の譫言を聞きながら、竜一は膝を払って立ち上がった。一度深く息を吸い携帯を取り出すと、すぐさま救急車を呼んだ。
救急隊員に様子を聞かれ、先程までの桐野の様子を話す。その時咄嗟に頭の中に薬のシートの存在が浮かんだ。
「あ! そういえば。ちょっと待っていて下さい。飲んでいた薬がわかります!」
何かの役に立つかも知れないと思い、携帯を耳に押し当てたまま靴を乱暴に脱いでキッチンへと走って行き拾い上げた薬の名前を告げると、救急隊員からどこの病院へ掛かっていたかを訊ねられた。
そこまでは自分は何も知らない。勝手に桐野の私物を漁るのは後ろめたさがあったが、今はそんな悠長なことを言っている場合ではないだろう。
思いきって部屋を探し、ジャケットの中にあった桐野の財布を開いて床にぶちまける。
――……あっ!
床へ広がった中身、クレジットカードの間に診察券が見つかった。
念の為もう一度探したがどうやらこの一枚だけのようなので、その病院の名称を伝えてから電話を切る。
玄関へ戻ると、青ざめた顔で座り込んでいるその男に、もうすぐ救急車が来る事を知らせた。
しっかりとした三つ揃いのスーツに身を包んだその男は、前に見かけた際には竜一とそう年が変わらないように見えたのに、よく見るとまだとても若い。未だに状況を受け入れられないのか、呆然とした表情の中で目があちこちへと落ち着きなく動いていた。
状況をすぐに受け入れられないのは自分だって同じだったが、こういう時、自分より動揺している人間がいると「しっかりしなくては」という意識が働くのか、なんとかこうして冷静な行動が出来ている。
「大丈夫ですか?」
竜一は、男に声をかけながら、自身を奮い立たせるとコートを脱いで桐野の体の上へそっとかけた。
「すみません……。大丈夫です。あ、あの……。貴方は、恭征さんのご友人ですか?」
「……、……そうです」
「助かりました。私、取り乱してしまって、本当に申し訳ありません」
「いえ」
男はゆっくり立ち上がると、心から申し訳なさそうに深々と頭を下げた。
「恭征さんのお父様の秘書をしております。笹松郁人と申します」
「どうも……俺は、佐久間竜一です。桐野さんとは親しくさせて頂いていて……」
具体的には数時間前別れたばかりだが、今ここでそんな事を説明している場合ではない。短く挨拶を切り上げて竜一は口を噤んだ。
――あと十分、いや五分でもいい。長く一緒に居れば、桐野の様子の変化に気付いてもっと早く対処が出来たのではないか。
そんな過ぎた時間に後悔ばかりが積み重なる。
救急車は中々到着せず、二人で何度も腕時計を確認しては酷く長く感じる時間を過ごした。辺りはすっかり暗くなり、外灯が灯りだしている。
「もう、そろそろ来るはずです」
自分に言い聞かせるように呟き、竜一は倒れたままの桐野に視線を向けた。
電話をした際、救急隊員に動かさないよう言われたので、桐野に触れることも叶わず、竜一は目を閉じてひたすら心の中で祈った。桐野が無事でありますように、と。
その後まもなくしてサイレンの音が聞こえ、到着した救急車から担架が運ばれてきた。
ここへ向かう前に先程伝えた病院と連絡が取れたらしく、桐野はすぐに搬送されることが既に決まっていたようだ。
なりゆきで笹松と一緒に救急車で病院へ向かうことになり、忙しなく乗り込むとすぐに救急車は発車した。
初めて乗った救急車の狭さに驚くが、そんな事より目の前で一切意識がない桐野の様子から目を離せない。
救急隊員の大きな声での様々な呼びかけにも、桐野は一切反応を示さなかった。
このまま桐野が死んでしまったら……。
嫌な方へ考えが進みそうになるのを必死に留め、担架から投げ出されている桐野の手を只管握る。
数分前に交わした握手と同じなはずなのに、握り返してくれない桐野の手がとてつもなく寂しくて泣きたくなった。
――……桐野さん。
笹松と二人で桐野に話しかけ続けている内に、病院は近くだったようで、すぐに到着した。
騒がしく運ばれていった桐野を見送り笹松と二人きりになると、一気に静寂が訪れる。足音が聞こえビクッとして振り向くと、廊下の向こうから歩いてきた執刀医に声をかけられた。
「桐野さんのご家族の方ですか?」
何も言えないでいる竜一の横で笹松が「はい、そうです」と口にする。
医師は竜一をチラッと見た後、二人に向き合うと表情を硬くした。
「桐野恭征さんの主治医をさせてもらっている後藤と申します。精一杯力を尽くしますが、危険な状態です。別の医師が説明に向かいますので待合室でお待ち下さい」
返事を待たず一礼をするとすぐに手術室へ消え、手術中のランプが真っ赤に点灯する。暫く呆然と立ち尽くしていたが、看護師に声をかけられ、二人で待合室へと向かった。
外来の時間もとっくに過ぎている院内は、薄暗くて人気もなく、鼻に付く消毒の匂いが滅入る気分に追い打ちを掛ける。
折りたたみ椅子と会議室にあるような机がおかれた簡素な部屋に通され、仕方なく腰掛ける。今自分が何故ここに座っているのかさえ、頭を整理しないとわからなくなりそうだった。
隣で悲痛な面持ちで黙り込んでいた笹松が、ポツリポツリと話し出す。
「先日……、私が恭征さんの自宅へ行った時も、あの人、頭痛が酷いって途中で気分が悪くなったんです」
「……、……」
「でもその時は「いつもの偏頭痛だから心配要らない」って言われて、それ以上問い詰められなかったんです……」
「それって……いつ頃の話ですか?」
恐る恐る訊ねてみると、その日は竜一が笹松と鉢合わせたあの日だった。あのあと、桐野と一緒に過ごしていた時にも体調の変化には一切気がつかなかった。
話を聞いて予想する限り、桐野には多分持病があってそれを誰にも話していなかったのだろう。竜一にも、そして身内同然だと言っていた笹松にでさえ。
「今日は……、私個人でどうしても恭征さんの様子が気になって、見に来たところだったんです。まさか、こんな事に……。恭征さんは怒るでしょうけど……、もっとちゃんと調べておけば良かった……。そうすれば、こうなる前に……」
自分を責める笹松に、かける言葉が見つからない。
立場は違えど、竜一だってそれは同じだからだ。今日だって、もっとしつこく薬のことを問い詰めていれば、あるいは……。
しかし、それもこれも今更後悔してもどうにもならない事なのだ。
「すみません。社にもう一度連絡をいれてきます」
「……はい」
そう言って出て行った笹松は十分程して戻ってきた。重く沈んだ空気のまま、それ以来話す事もなく二人とも口を開かなかった。
部屋に備え付けられた巨大な時計が、音のない空間で正確に時を進める音を立てている。ずっとそれを聞いているだけで、ジメジメとした不安感がどんどん増していく気がした。
その後、言われたとおり医師が部屋に説明に来て、桐野には脳に腫瘍があり、今週摘出手術を受ける予定だったと聞かされた。数ヶ月前から経過が悪くいつこうして倒れてもおかしくないほどの状態だったらしい。手術が成功することがまず第一の関門だが、その手術が成功しても、本人が目を覚ました後、どんな後遺症をもたらすかはその時になってみないとわからないそうだ。
こんなに頻繁に会って傍にいたのに、何一つ知らなかった。
医師が去った後の部屋で、竜一は桐野の言っていた台詞を思い出し、今頃になってようやく意味を理解していた。
自分の鈍さに、行き場のない苛立ちを向けることしか出来ない。
いつも大らかで明るかった桐野が、誰にも見せないようにしていた不安や焦燥。
いつか自分がこうなることを覚悟していたのかもしれない。
出会った日に告げられたあまりにも具体的な恋人契約の期限。今日急に別れてくれと言ってきた事。そう考えると納得がいく。
桐野がこの事を知られたくなくて別れたいと言ったのであれば、もう一度ちゃんと話をして……。そこまで考えてフと頭をよぎる最悪の結末。
――桐野と、本当にまた話せるようになるのだろうか。
前みたいに普通に話せるようになる保障はどこにもない。
意識のない先程の桐野の姿が、脳裏に焼き付いて離れなかった。
また元気になって、あの店で笑って過ごしてくれるなら、恋人になりたいなんて贅沢は言わない。だから、生きていて欲しい。
竜一は、滲みそうになる涙をゴシゴシとハンカチで拭うと、腰を上げた。
「何か、飲み物でも買ってきます」
「あ、すみません。さっき私が買ってくれば良かったですよね。すみません、気が回らなくて、私が代わりに行って、」
「いや、笹松さんはここに居て下さい。何か連絡が来るかも知れませんし。それに俺、外で一服もしてくるんで、そのついでですから」
「そうですか? ……じゃぁ、お言葉に甘えて。すみません。お願いします」
笹松と二人でいた部屋を抜けて、竜一は自販機を探しに廊下へ出た。
ひんやりとする廊下の突き当たり、手術室の赤いランプが不吉に光っているのを横目にゆっくりと歩き出す。
廊下には自分の足音だけが響いていた。
COUNT0….|創作BL小説|メンズラブ|
シリーズ『俺の男に手を出すな』メインの長編連載小説サイトです。病弱、ホスト、バンドマン、医者、眼鏡、強気受け、リーマン。